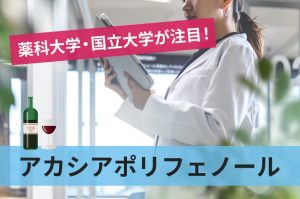血糖値は、体の健康状態を把握する上で欠かせない指標のひとつです。
血糖値は食前と食後で変動しますが、健康な人は正常値の範囲内で一定に保たれます。
血糖値が正常値から逸脱すると、糖尿病や低血糖、脳心血管病などを発症するリスクが高まります。
血糖値は、日常の食事の改善でコントロールが可能です。
この記事では、血糖値の基本的な考え方から血糖値の上がりにくい食品を紹介します。
- 食事と血糖値の関係
- 血糖値とインスリンの関係
- 血糖値の上がりにくい食品
血糖値を安定させるために意識的に取り入れたい食品やコンビニで購入できる食品なども紹介しているため、ぜひ参考にしてください。
血液中に含まれるブドウ糖は体のエネルギー源となる
食事をすると、食べ物に含まれる炭水化物が分解されてブドウ糖になり、小腸から吸収されてエネルギー源として血液により全身に運ばれます。
体内でブドウ糖の供給と消費が繰り返されているため、血糖値はある一定の範囲内に維持されます。
血糖値が正常値を上回ると高血糖、正常値を下回ると低血糖と呼ばれてふるえや動悸、手足のしびれなどの様々な症状が現れます。
膵臓から分泌されるインスリンは血糖値を一定に保つ働きをもつ

食後に血糖値が上昇すると、インスリンが血液中のブドウ糖を必要な分細胞に取り込んでエネルギー源として利用します。
さらに余ったブドウ糖は、インスリンの働きによりグリコーゲンや中性脂肪に合成されて蓄えられます。
インスリンの分泌異常は、血液中のブドウ糖の処理ができなくなり、血糖値が上昇する原因になります。
血糖値が上昇して正常値を上回ると、糖尿病や動脈硬化、脳心血管病などの命に関わる病気を引き起こすリスクが高まります。
インスリンの機能を維持するためにも、血糖値の上がりにくい食品の意識的な取り入れが大切です。
血糖値を安定させるために血糖値の上がりにくい食品を取り入れる
食事と血糖値は深く関係しており、血糖値を安定させるためには、血糖値の上がりにくい食品への理解が必要です。
同じ炭水化物でも食品の種類により、血糖値が急上昇する食品と緩やかな食品があります。
血糖値を急上昇させる代表的な食品としては、以下の6つが挙げられます。
- 清涼飲料水(ジュースやコーラ、栄養ドリンク)
- 菓子パン(あんパンやジャムパン、クリームパン)
- 菓子(ようかんやまんじゅう、大福)
- 精白米
- 麺類(うどんやそうめん)
- 果物
他にも食物繊維やミネラル、ビタミンなどの栄養素と炭水化物を組み合わせて摂取すると、血糖値の急上昇を予防できます。
上記のような食品や栄養素の特徴を理解して、自分のできる範囲で血糖値を安定させる食品を積極的に取り入れましょう。
低GL食品は食後血糖値の上昇を緩やかにする

低GL食品は、食後血糖値の上昇を緩やかにする効果をもちます。
GL値により以下のように3つに分類されます。
- GL値20以上が高GL食品
- GL値10~20が中GL食品
- GL値10未満が低GL食品
代表的な低GL食品としては、以下が挙げられます。
- 低脂肪ヨーグルト
- グレープフルーツ
- りんご
- いちご
- ブロッコリー
- きのこ
- 豆乳
- にんじん
- 大根
血糖値を安定させるためにも、上記のような低GL食品を意識的に摂取するよう心がけましょう。
低GI食品は食後血糖値の上昇を緩やかにする
低GI食品は、糖質が体内で消化吸収されるまでに時間がかかるため、食後血糖値の上昇を緩やかにする効果をもちます。
代表的な低GI食品としては、以下が挙げられます。
- 海藻類(昆布や青のり、もずく)
- きのこ類(しめじや椎茸、えのき)
- 大豆食品(いんげん豆や納豆、おから)
- 肉や魚(鶏肉や豚肉、まぐろ)
- 乳製品(牛乳やチーズ、プレーンヨーグルト)
- 精製されていない麺やパン(玄米のおかゆや全粒粉パン、そば)
- 果物(グレープフルーツやりんご、いちご)
上記の食品は低GIだけでなく、食物繊維やたんぱく質も含まれているため、食後血糖値の上昇を予防できます。
ただし過剰摂取は肥満につながるため、避けるようにしましょう。
低GL食品は低GI食品よりも実用的に活用できる
GI値は、50gの炭水化物を食べた時の血糖値の上昇スピード値を表しているため、1回に食べる量を想定していません。
一方でGL値は、1回に食べる量を想定して1人前の常識的な食事の中で、食材がどのくらい血糖値を上昇させるか示しています。
ただしGL値は、一般的に1回で摂取する量を想定しているため、参考値として活用するようにしてください。
さらに低GIや低GL食品であっても、過剰摂取は肥満につながる可能性があるため、適量摂取して食後血糖値の急上昇を避けましょう。
食物繊維を多く含む食品は食後血糖値の急上昇を予防する
食物繊維は、消化や吸収を穏やかにして血糖値の急上昇を予防する効果があります。
適量を意識して、以下の食物繊維を多く含む食品を摂取しましょう。
- 野菜(キャベツやブロッコリー)
- 果物(りんごやバナナ)
- 全粒穀物(玄米や麦入りご飯)
- 豆類(大豆やひよこ豆)
- 海藻(わかめや昆布)
- ナッツ(アーモンドやピーナッツ)
- きのこ類(えのきやしいたけ)
- イモ類(さつまいもやじゃがいも)
食事では、食物繊維の多い野菜からたんぱく質、炭水化物の順番で食べるのが理想的です。

血糖値対策には、食事からの糖をコントロールすることが大切です。
最近の研究で、ポリフェノールの一種に体内での糖の吸収を抑える効果があることも知られています。
詳しくは「糖質の吸収を抑え、食後血糖値が上がりにくくする成分」の記事をご覧ください。
ミネラルやビタミンを多く含む食品は食後血糖値の急上昇を予防する


ミネラルやビタミンには、エネルギー代謝を促進して血糖値を下げる働きがあります。
ミネラルやビタミンを多く含む食品としては、以下が挙げられます。
ミネラルを多く含む食品
- 玉ねぎ
- オクラ
- バナナ
ビタミンを多く含む食品
- オレンジ
- りんご
- キウイ
- ゴーヤ
ミネラルやビタミンを多く含む食品と炭水化物を組み合わせて摂取すると、食後血糖値の急上昇を予防できます。
ただしミネラルやビタミンは、年齢や性別、種類により人それぞれ適正摂取量が異なります。
そのため、自身の適正摂取量を把握した上で意識的に適量摂取するよう心がけましょう。
消化吸収に時間がかかるたんぱく質と脂質は血糖値の上昇を緩やかにする
食事に含まれる三大栄養素のうち、炭水化物だけでなくたんぱく質と脂質も血糖値に影響を与えます。
たんぱく質や脂質は、消化や吸収に時間がかかるため、食後血糖値の上昇を緩やかにする効果があります。
朝食でたんぱく質を摂取すると、朝食後だけでなく昼食後血糖値の上昇を抑える効果もあるため、積極的に摂取しましょう。
脂質は、飽和脂肪酸でなく不飽和脂肪酸に置き換えると、食後血糖値の急上昇を予防できるため効果的です。
不飽和脂肪酸は、以下のように一価不飽和脂肪酸と多価不飽和脂肪酸に分類されます。
一価不飽和脂肪酸
- n-9系脂肪酸(オリーブオイルやなたね油)
多価不飽和脂肪酸
- n-6系脂肪酸(ごま油や紅花油)
- n-3系脂肪酸(魚油)
血糖値が上がりにくい食品はコンビニでも購入できる
疲れていて自炊が難しいときにも、コンビニで血糖値の上がりにくい食品を購入できます。
血糖を安定させるためには、主食と主菜、副菜のバランスが大切です。
そのため、コンビニではバランスを意識しながら、以下のような食品を購入しましょう。
主食
- 雑穀やもち麦を使用したおにぎり
- 野菜や低脂質のたんぱく質が含まれたサンドイッチ
- 低糖質パンや糖質オフ麺
主菜
- ゆで卵
- 焼き鳥
- サラダチキン
- 焼き魚
- おでん
副菜
- サラダ
- スティック野菜
- 納豆
- 野菜スープ
- 味噌汁
- 冷ややっこ
コンビニ弁当は、主食や脂質の量が多かったり、食物繊維やたんぱく質が不足したりします。
そのため、コンビニ弁当ではなく単品を組み合わせて摂取するのが理想的です。
おやつは血糖値の上がりにくい食品を適量摂取する


食事と食事の間隔を空けると、血糖値を下げる時間ができて血糖値が安定します。
しかし、間食でおやつを摂取すると、血糖値に影響が及びます。
血糖値に及ぼす影響を少なくするためにも、間食をする場合は1日200kcalを目安にして以下のおやつを選びましょう。
たんぱく質を含むおやつ
- ギリシャヨーグルトや無糖ヨーグルト
- ごまやチーズが入っている煎餅
- ツナやたまごの入ったサンドイッチ
マグネシウムや良質な油を含むおやつ
- アーモンド
- カシューナッツ
- くるみ
果物
- キウイ
- グレープフルーツ
- いちご
- りんご
- みかん
ただし就寝中はエネルギーの消費が少ないため、就寝前に摂取すると肥満につながります。
おやつを摂取する際には、活動量の多い昼間や運動を始める前にして就寝前は避けるようにしてください。



ブルーベリーなどに多く含まれるプロアントシアニジンには、糖の吸収を抑えたり、血糖値の上昇を抑制する効果が確認されています。
プロアントシアニジンを多く含む食材を意識するなど心がけましょう。
プロアントシアニジンを多く含む食品一覧
血糖値の上がりにくい食品を意識的に取り入れると長く健康的に生きられる
炭水化物は、体に欠かせないエネルギー源であり、適正なカロリーを摂取する必要があります。
血糖値の上昇を予防するために安易に炭水化物の摂取量を減らすと、筋力低下や疲れなどの弊害が生じて健康的ではありません。
低GIや低GL食品の置き換え、血糖値の上昇を緩やかにする栄養素の取り入れなどにより血糖値が安定します。
血糖値が安定すると病気の発症も予防できるため、自分のできる範囲から血糖値の上がりにくい食品を意識的に取り入れましょう。