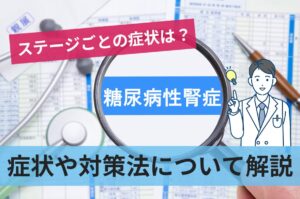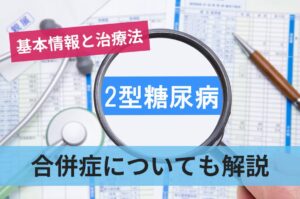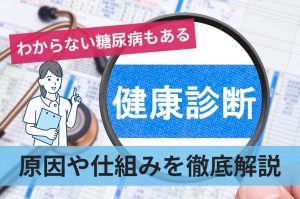会社や市町村の健康診断の血糖値の項目で、精密検査を受けるように言われた経験がある人がいるのではないでしょうか。
血糖値は、血液中の糖が増えてしまう糖尿病の状態を把握する上で、最もよく使用される指標です。
今回は血糖値の基本と目標値、糖尿病の怖さと治療についても解説します。
- 血糖値と糖尿病診断のための検査
- 糖尿病の合併症
- 血糖値が高くなる要因
- 血糖値を下げる方法
- 高血糖を指摘された時の対処法
一度の検査だけで、必ず投薬治療が必要と診断されるわけではないので、記事を参考にして対処を考えていきましょう。
糖尿病治療は血糖値と病気の関連をしっかり押さえるのが基本

血糖値には、健康診断などの採血検査で測定する食後血糖値や空腹時血糖値があります。
食後血糖値が高い状態は、糖尿病の可能性があるため、早期にかかりつけ医へ相談しましょう。
糖尿病は、血糖値が高い状態が続く病気で、診断には血液検査で血糖値を調べます。
- 随時血糖値が200mg/dL以上
- 空腹時血糖値が126mg/dL以上
- ブドウ糖負荷試験という検査の2時間後の血糖値が200mg/dL以上
上記のいずれかを二度確認すると、糖尿病と診断されます。
さらに、一度の血液検査の結果と下記のうちいずれか1つを認められた場合も、糖尿病と診断されます。
- 糖尿病の典型的な症状である口渇や多飲、多尿、体重減少がある
- 血糖値の血液検査時のHbA1cが6.5%以上
- 糖尿病網膜症がある
糖尿病は、慢性的な高血糖を表す身体の状態や検査結果によって診断されます。
食事内容や検査のタイミングなどにより、たまたま血糖値が高い場合もあります。
しかし、自己判断での治療や検査の放置は危険です。
血糖値が高い状態を治療しないと、合併症が進み、体のあちこちに治療が必要になります。
糖尿病の放置によって起こり得る怖い合併症には正しい理解が必須
糖尿病には様々な合併症があり、大きく2つに分けられます。
高血糖状態がわかった段階で適切な治療を受けると、合併症や悪化を予防できます。
糖尿病の治療は、合併症を防いで、糖尿病ではない人と同じように健康状態を維持した生活を過ごせるのが目的です。
血糖値や体調の適切な自己管理で、糖尿病の人でも健康的な生活は送れます。
糖尿病の特徴的な合併症について知識を深め、血糖値のコントロールの目的を明確にしましょう。
生命をおびやかし速やかで適切な治療を要する急性合併症

どちらも発症すると一刻も早く入院治療が必要になり、命の危険があります。
糖尿病性ケトアシドーシスは、血液が酸性に傾き高度の脱水状態となり、意識消失の可能性がある状態です。
体中で血糖値を下げるインスリンが不足して血糖値が十分に下がらなくなり、発症します。
そのため、糖をエネルギー源に利用できずに体の中がエネルギー不足になってしまいます。
糖の代わりに脂肪をエネルギー源として分解するため、アシドーシスになってしまうのです。
下記のような急激な症状は、すぐに主治医へ相談しましょう。
- 強いのどの渇き
- 多飲、多尿
- 全身のだるさ
- 吐き気、嘔吐
- 腹痛
糖尿病性ケトアシドーシスは、感染症や重症疾患になった場合や、清涼飲料水の多量摂取で血糖値が急上昇して起こる場合があります。
高浸透圧高血糖症候群は、血糖値が600mg/dL以上の著しい高血糖と極度の脱水により、意識障害が起きる状態です。
特徴的な症状はなく、高血糖や脱水による倦怠感、口喝を感じる場合があります。
急性合併症は、どちらも腎臓や肝臓などの臓器に負担をかけてしまいます。
血栓症を起こし、脳や足などの動脈が詰まってしまう可能性もあるため、普段の糖尿病治療と体調の変化を感じた時は速やかに主治医への相談が大切です。
数年に渡る高血糖状態で起こる生活への影響が大きい慢性合併症
糖尿病の合併症というと、慢性合併症を指す場合が多いです。
血管は、体全体に栄養や酸素を運ぶ通路の役割を担います。
血糖値が高い状態が長く続くと、血管が傷つき血流が滞ってしまい、血管と血管から繋がる臓器が障害されます。
慢性合併症は、毎日の生活スタイルに影響が大きく、予防が必要です。
細小血管症には、網膜症や腎症、神経障害が分類されます。
網膜の細い血管が傷み、光の感知が悪くなるのが網膜症です。
進行すると、眼底出血や網膜剥離により失明する場合があります。
初期では全く症状がないため、早期発見と治療に努める必要があります。
症状が出る前に血糖値の良い状態を保ち、1年に1回以上の眼科受診が大切です。
腎症は、血液をろ過して体の余分な老廃物や水分を尿にする腎臓の働きが悪くなる状態を指します。
水分が体に溜まってしまい、体のむくみや高血圧が見られるようになるのは、腎臓の働きの低下が原因です。
糖尿病性腎症が進行すると、血液中に有害な老廃物が溜まるため、透析治療が必要になります。
糖尿病性腎症も初期では全く症状がないため、定期的な血液検査と尿検査により、早期の発見が可能です。
糖尿病性腎症を予防し、進行を防ぐためには、血糖値だけでなく血圧も良い状態を保たなければいけません。
体内や血液中にあふれる余分な糖が神経を傷つけ、神経周囲の細い血管を傷めて、神経の働きが悪くなる状態が神経障害です。
糖尿病性神経障害には、末梢神経障害と自律神経障害があります。
血糖値が高い状態が続くと、痛みや温度を感じる末梢神経に症状が起こります。
初期では血糖値が良い状態になると、症状がなくなったり、軽くなったりします。
血糖値の高い状態が続くと激痛を感じる場合や、逆に感覚が麻痺して傷に気付かず、壊疽や切断が必要となる場合があります。
自律神経障害は、自分の意志と関係なく内臓の動きを調節する自律神経が障害される状態です。
胃もたれや便秘、下痢やたちくらみ、そして勃起障害などが起こります。
末梢神経障害も自律神経障害も、血糖値を良い状態に保つと発症や進行の予防が可能です。
高い血糖状態では、細い血管だけでなく、大血管症も起こる可能性があります。
動脈硬化は心筋梗塞や脳梗塞、閉塞性動脈硬化症などの生命が危険にさらされる病気や、日常生活に支障が出る病気を引き起こします。
動脈硬化は糖尿病特有の病気ではありませんが、糖尿病ではない人と比べて起こる確率が高いです。
慢性的に血糖値が高い状態が続くと、感染症にかかる可能性が高くなり、治すのも簡単ではありません。
肺炎やインフルエンザなど様々な感染症にかかった場合、重症化するリスクが糖尿病ではない人より高くなります。
特に皮膚は足の指や爪の水虫の発生も多く、放置すると足の壊疽に繋がってしまいます。
さらに、歯周病も治療に時間がかかり、歯の脱落につながる点も留意が必要です。
手足の先や口腔内など、十分な観察と定期的な検診を行い、感染症の早期発見と治療に努めましょう。
糖尿病があると認知症の発症率が1.5~2倍になり、高血糖状態の継続や重症な低血糖により認知症を引き起こすリスクが高くなります。
認知症になると、適切な食事や薬の管理が困難になります。
糖尿病の悪化を招く原因になるため、認知症になる前から良い血糖値の維持が最も重要です。
血糖コントロールの鍵であるインスリンの反応が低下するインスリン抵抗性に注目

血糖値が上がる要因には、以下の3点が挙げられます。
- インスリンが十分に出ていない、または十分に効かない
- カロリーの高い食事、または過食
- 運動不足
インスリンは、高い血糖値を下げる唯一のホルモンで、以下のような血糖値の調整や糖を脂肪や筋肉に蓄える働きをしています。
- 血液の中の糖を細胞に取り込んで血糖値を下げる
- 血液の中の糖を脂肪として蓄える
- 血液の中の糖をエネルギーのもとになるグリコーゲンに変えて肝臓や筋肉に蓄える
食後は食べた物が消化と吸収を経て全身に運ばれるため、一時的な高血糖は誰にでも起こります。
時間の経過とともに血糖値が一定の範囲に収まっていくのは、血糖値が上がるとインスリンが働くためです。
しかし、インスリンがうまく働かない場合があります。
脂肪がたまって肥満になると、インスリンの作用を向上させるホルモンが低下し、インスリン抵抗性が見られます。
その結果、インスリンが足りなくなったり、効果が少なくなったりします。
インスリンがうまく働かない状態が、血糖値の高くなる要因です。
糖尿病治療で重要な3つのポイントの実施で血糖値の低下は可能!

血糖値を下げるためには、どのような生活を送れば良いのでしょうか。
効果的な糖尿病治療の基本は、体重の適正なコントロールです。
摂取エネルギー量の適正な維持により体重が適正に保たれると、インスリンを分泌する能力や効果が改善します。
体重や血糖をコントロールできない主な原因は、不規則な食事や運動不足です。
生活の見直しで、良好な血糖コントロールを得られる場合があります。
血糖値を下げるために、規則正しい生活を続けましょう。
そして、食事や運動に加えて、必要な場合は薬物療法の励行が大切です。
肥満で血糖値が高い人に最も効果的ですべての人が見直すべき食事療法
肥満で血糖値が高い人は、食事の見直しが重要です。
肥満が改善されると、過去1〜2か月の血糖値の状態を示すHbA1cの値が改善します。
血糖値を下げるために炭水化物だけを制限すると、体に悪影響を及ぼす可能性もあるため、次のポイントが大切です。
- 適切なカロリーを摂取する
- 糖質、脂質、タンパク質をバランスよく摂取する
- 塩分の適正な摂取量を守る
人により活動量や筋肉量が異なるため、一人ひとりに合ったカロリー摂取が必要です。
合併症の有無によっても状況が異なるため、主治医の指導に従ってください。
エネルギーのもととなるのは、炭水化物とタンパク質、脂質から構成される三大栄養素です。
どれも欠かせない栄養素で、体の調子を整えるためには、さらにミネラルやビタミンなどを摂取する必要があります。
様々な栄養素を適量摂るためには、バランスの良い食事が大切です。
1日の中で様々な食品を組み合わせると、栄養素を十分に取れる良い食事に近づきます。
しかし、手軽なカレーライスや丼ぶりなどは糖質と脂質を取りすぎる場合があります。
糖質や脂質が過剰にならないように、野菜を使った副菜を積極的に取り入れましょう。
加えて、食後血糖値を上昇させないために食物繊維の多い野菜から先に食べて、ゆっくりとよく噛む工夫が大切です。
食塩の過剰摂取は高血圧の原因になり、糖尿病の合併症を悪化させます。
体脂肪やエネルギーの消費により体脂肪や体重を減らせる運動療法

体脂肪や体重の減少は、高血圧や高脂血症も改善し、心筋梗塞や脳卒中の予防にも効果的です。
食後に運動をすると、筋肉での糖や脂肪の利用が増えるため、食後血糖値の急激な上昇が改善されます。
運動の継続は、インスリンの効果が高まり、血糖値のコントロールが良くなります。
有酸素運動や筋力トレーニングの2日に1回程度の継続が、血糖値の改善には効果的です。
低血糖が頻繁に起こっている場合や、糖尿病の合併症や他の病気によっては運動を勧められない場合もあるので、主治医に了承を得てから行いましょう。
高血糖状態の人には重要な飲み薬やインスリンの注射による薬物療法
糖尿病治療は食事療法と運動療法が基本となりますが、それだけでは十分な血糖管理が得られない場合、薬物療法は補助的な役割を担います。
飲み薬はインスリンの効き目をよくしたり、インスリンの分泌を促したり、糖の吸収や排せつを調節したりと、薬によって効果は様々です。
検査の結果から、血糖値が高い原因を主治医が判断して、薬を調整します。
自己判断での薬の調整は、体への影響が大きいため行わないでください。
高血糖の怖さを知って良い血糖値の維持が健康的な生活のためには大切
血糖値が200mg/dLを超える高い状態は糖尿病のリスクが高いため、指摘された時は、早期のかかりつけ医への相談が必要です。
検査の結果により、糖尿病と診断されたとしても、治療すれば命に関わる心筋梗塞や脳卒中、意識障害などが予防できます。
さらに、慢性合併症と呼ばれる生活スタイルに関わる病気の予防にもつながるため、早めの治療開始が何より大切です。
糖尿病と診断されなくても、血糖値が高い状態が続かないように食生活や運動習慣について見直すと、健康的な生活が維持できます。
定期的に会社や市町村の健康診断を受け、自分の血糖値について把握して、コントロールできるよう心がけましょう。