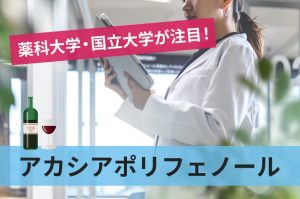皮膚の下に水分が貯留し、手や足などといった身体のいたるところが腫れてしまっている状態をむくみといいます。
むくみの原因には心臓や腎臓、肝臓といった重要な臓器に障害を受けている場合が多く、糖尿病などの重大な病気が隠れている可能性が少なくありません。
糖尿病と腎臓には密接な関係があり、高血糖状態が持続していると臓器の機能を維持できなくなります。
腎臓が障害を受けると身体にむくみが生じますが、それだけが原因とは限らないのが糖尿病の特徴です。
本記事では、糖尿病と腎臓の関係をはじめ、身体にどのような事態が発生するとむくみが起こるのか解説していきます。
- むくみの原因となる糖尿病と腎機能の関係
- 糖尿病性腎症の治療法や原因
- むくみの原因になり得る静脈血栓塞栓症
- むくみと糖尿病治療薬の副作用
糖尿病は腎の機能に影響を与えるためむくみが起こる
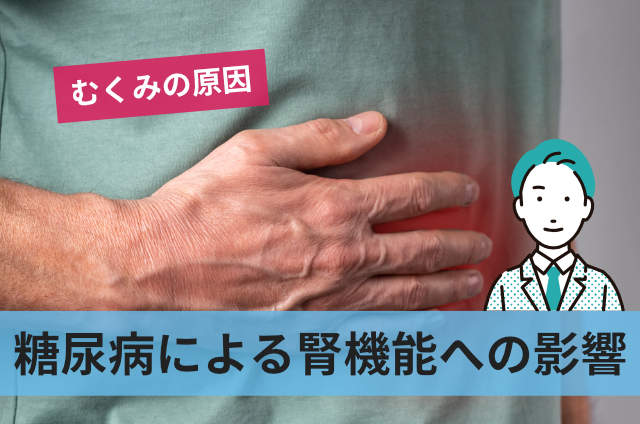
糖尿病には1型糖尿病と2型糖尿病との2種類があり、1型糖尿病は生まれつきや小児期に発病するのが基本的なケースです。
一方2型糖尿病は不規則な食生活や運動不足、飲酒や喫煙などの生活習慣が原因となり、ほとんどの人は中年期以降に発病します。
2型糖尿病は1型糖尿病と異なり、長期間にわたって血糖値が高い状態が持続しているため、全身の血管では様々な疾患の原因となる動脈硬化が起こります。
動脈は、心臓から各々の臓器に必要な栄養や酸素を運ぶ役目を担います。
しかし血液の流れが悪いと、身体の重要な一つひとつの臓器に対し、必要な栄養や酸素が十分に供給されません。
特に、血液を濾過する役割を担う腎臓は、毛細血管が豊富な臓器です。
動脈硬化は腎臓にある血管にも例外なく起こるため、血液を濾過して尿を生成するという機能が徐々に低下していきます。
糖尿病によって本来持っている腎臓の機能が障害を受け、働けなくなった状態を糖尿病性腎症といいます。
糖尿病性腎症は、糖尿病の進行に伴って発症する合併症で、進行を食い止めるには両者とも早期発見と治療が大切です。
しかし腎臓は沈黙の臓器といわれており、初期の腎機能障害では自覚症状に乏しいという特徴を持っています。
むくみが出現している段階で糖尿病性腎症を指摘された場合、腎機能障害はある程度進行していると捉えた方がよいでしょう。
糖尿病性腎症にはの5つのステージがある
糖尿病性腎症には、症状や腎機能を反映する血液検査の数値によって、進行具合がステージ化されています。
末期まで進行すると、血液を濾過して不要な物質を身体から取り除くために人工透析が必要です。
以下の表に、糖尿病性腎症の5つのステージを表しました。
| 病期 | 検査値 | 自覚症状 |
|---|---|---|
| 1期(腎症前期) | ・尿蛋白(g/gCr)あるいはアルブミン値(mg/gCr)→正常(30未満) ・腎機能・eGFR(ml/分/1.73m2)→30以上 | なし |
| 2期(早期腎症期) | ・尿蛋白(g/gCr)あるいはアルブミン値(mg/gCr)→微量アルブミン尿(30〜299) ・腎機能・eGFR(ml/分/1.73m2)→30以上 | たんぱく質に尿が混ざるため、尿自体が泡立ってなかなか消えない |
| 3期A(顕性腎症期) | ・尿蛋白(g/gCr)あるいはアルブミン値(mg/gCr)→顕性アルブミン尿(300以上) / 持続性タンパク尿(0.5以上) ・腎機能・eGFR(ml/分/1.73m2)→30以上 | むくみ息切れ倦怠感疲労感食欲の低下腹部の張り など |
| 4期(腎不全期) | ・尿蛋白(g/gCr)あるいはアルブミン値(mg/gCr)→問わない ・腎機能・eGFR(ml/分/1.73m2)→30未満 | 顔色が悪い(土色)嘔気や嘔吐こむら返り腹痛や発熱 など |
| 5期(透析療法期) | ・尿蛋白(g/gCr)あるいはアルブミン値(mg/gCr) ・腎機能・eGFR(ml/分/1.73m2)→どちらも透析実施のため判定しない | 顔色が悪い(土色)嘔気や嘔吐こむら返り腹痛や発熱強い倦怠感 など |
上記で示したように、糖尿病によって腎機能が低下していても、むくみを自覚するまでには時間がかかります。
そのため糖尿病と診断されたら、腎機能を維持するためにも、早い段階で腎機能を検査するのが大切です。
糖尿病腎症はステージに応じて治療法が異なっている
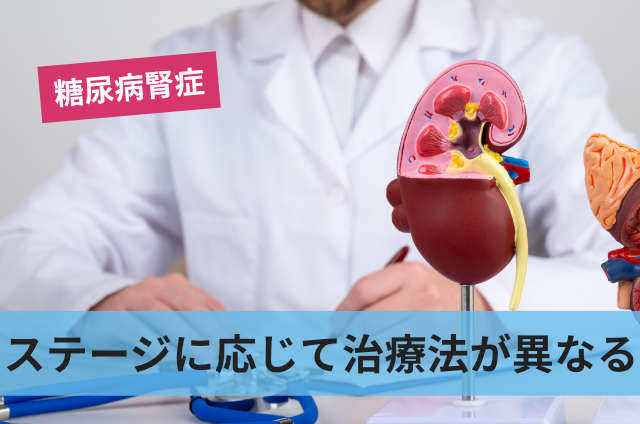
糖尿病性腎症には、以下の治療法があります。
- 血糖コントロール
- 血圧の管理
- たんぱく質制限
- 透析療法
- 腎移植
上記に示した治療の方法は、あくまでも腎機能障害の進行を遅らせ、可能な限り生活の質を維持していくために行います。
ステージに応じて治療が選択されるものの、治療したからといって腎機能が元に戻るわけではありません。
そして治療は単に薬を飲めばよいわけではなく、しっかりとした自己管理が必要です。
血糖コントロールや血圧の管理は、食事療法と運動療法、さらに必要に応じて薬物療法を行ないます。
たんぱく質制限は、食事療法が基本であるため、日々の食事を見直して献立を考えるのが大切です。
透析療法の場合は、単に透析を実施している施設に通うだけではなく、血糖や血圧を管理する薬の服用も同時に行います。
いずれの治療もしっかりとした自己管理をすると、より快適な生活が維持できます。
最終的な治療の手段となる腎移植は、脳死移植と生体移植で術後の自己管理方法は異なりますが、移植をしても元通りの身体に戻れないのが現状です。
糖尿病による腎機能障害は、進行を食い止めるのが大切であるため、気になる症状があった場合には躊躇せずに医療機関への受診をおすすめします。

糖尿病腎症を含む三大合併症について詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。
糖尿病の三大合併症とは?
糖尿病が原因の静脈血栓塞栓症によってむくみが出現する場合もある
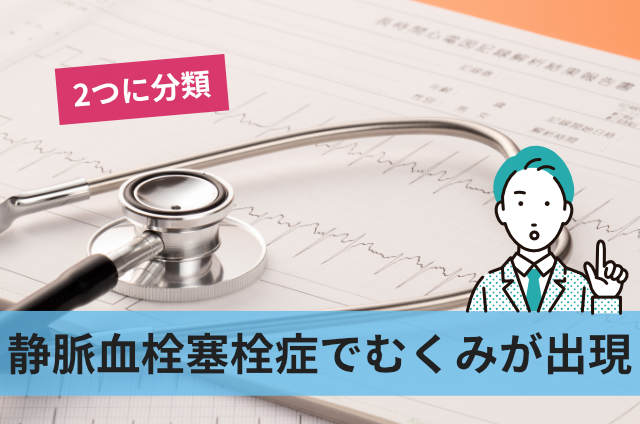
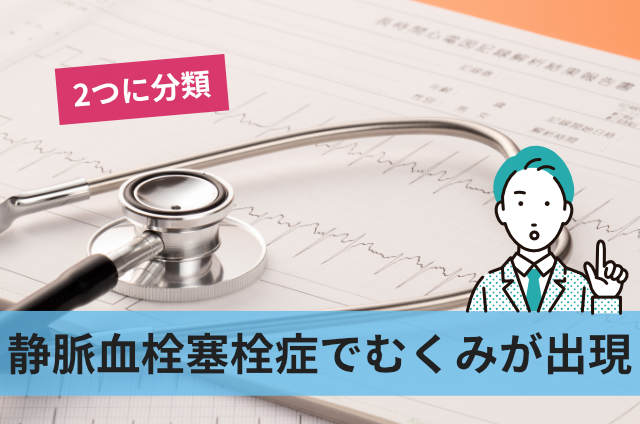
糖尿病は全身の血管において動脈硬化を促進させるだけではなく、静脈血栓塞栓症の原因にもなり得る疾患です。
糖尿病患者に多い疾患として知られるものには、脳血管疾患や心疾患が挙げられますが、実は静脈血栓塞栓症を発症する人も多くいます。
静脈血栓塞栓症は主に、深部静脈血栓症と肺血栓塞栓症の2つに分類されます。
深部静脈血栓症は、ふくらはぎをはじめ、いたるところの静脈に血栓が生じる病態です。
深部静脈血栓症の前兆として、局所的なむくみが現れます。
いずれも血管に問題が生じるため、治療に遅れが生じると命に関わります。
特に肺血栓塞栓症は、生きていくための呼吸機能や循環機能が障害を受けるため、深部静脈血栓症の予兆を見逃さないのが大切です。
深部静脈血栓症は下肢の血管が詰まる病気
血栓ができる血管は、必ずしも足の血管であるとは限らず、腹部や下大静脈でも起こり得ます。
深部静脈血栓症が問題となるのは、骨盤や膝下静脈など、身体の太い血管に血栓が形成された場合です。
特に膝や太ももの静脈に血栓がある状態で身体を動かすと、その弾みで血栓がさらに太い肺静脈に移動して、肺静脈塞栓症を発症します。
下肢の血管が血栓によって閉塞し、血流が滞って老廃物などが運搬できなくなった結果、血栓症が起きた方の下肢にむくみが起きます。
その際、血流が正常に保たれている方の足はむくみません。
むくみの程度としては、血流が滞った側だけが正常な足に比べて明らかに大きさが違うほどにむくみます。
腎臓や肝臓などの重要な臓器が障害を受けて下肢がむくむ場合には、左右差なくむくみます。
肺静脈塞栓症は深部静脈血栓症が発端となり起こる


「エコノミークラス症候群」とも呼ばれる肺静脈塞栓症は、深部静脈血栓症が発端となる病気で、両者とも共通した原因を持っています。
肺静脈塞栓症は肺静脈に血栓ができるため、肺のガス交換機能が障害されるのが特徴です。
症状としては、肺静脈塞栓症を起こす前兆に深部静脈血栓症があります。
前述したように深部静脈血栓症を発症すると、血栓が出来た側の足だけにむくみが生じるため、それが肺静脈塞栓症の前兆となります。
肺静脈塞栓症を発症した場合の特徴的な症状を、以下にまとめました。
- 息苦しさ
- チアノーゼ
- 動悸
- 息切れ
- 血痰
- 背中の痛み
肺静脈塞栓症に陥っている場合には、上記の症状が起こると瞬く間に状態が悪化するのも特徴です。
これらの血栓症は命に関わる病気のひとつであるため、疑わしき症状が出現した場合には、迅速に医療機関で適切な検査と治療を行う必要があります。
静脈血栓塞栓症の基本的な治療は抗凝固療法
深部静脈血栓症と肺塞栓症の両者をまとめて、静脈血栓塞栓症とよびます。
静脈血栓塞栓症の治療にはいくつかの選択肢があり、重症の場合には外科手術やカテーテルで血栓を溶かす線溶療法などが選択されます。
ただし、基本的な治療は抗凝固薬の服用です。
抗凝固薬を服用する目的は、主に二つあります。
- 形成された血栓を溶かす
- 再び血栓が形成されないよう予防する
抗凝固薬による治療には、点滴を使用して薬を持続的に体内に流す方法と、内服薬を一定期間服用する方法があります。
人によっては、生まれつき血液を固めないようにする因子の不足によって起こるため、その人の身体の状態に応じた内服薬が選択されます。
抗凝固薬を服用する場合、副作用として止血に時間がかかるという副作用が生じるため、日常生活を送るうえでは注意が必要です。
怪我のないような生活を心がけたり、薬が効きすぎている場合には鼻血が出やすくなるため留意するなど、日頃から自分の体調観察が欠かせません。
ほかにも糖尿病患者で血糖降下薬を服用している人の場合、抗凝固薬との相互作用が原因で低血糖や出血が起こる場合があります。
抗凝固薬との飲み合わせによって血糖降下薬の作用が増強され、結果的にむくみが起こる場合もあるため、血栓症の既往で抗凝固薬を服用している人は前もって医師に伝えましょう。
内服薬の副作用や相互作用によってむくみが起こる場合もある
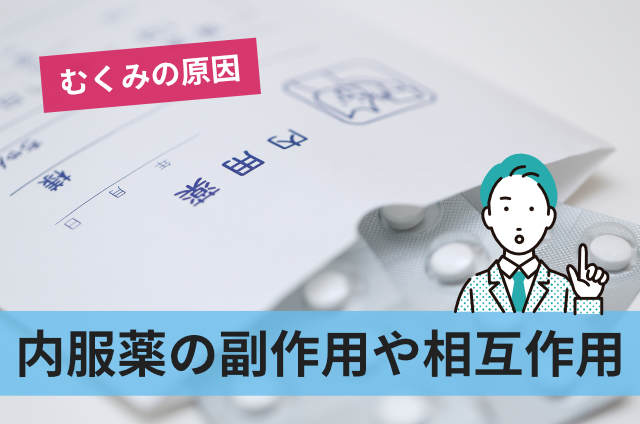
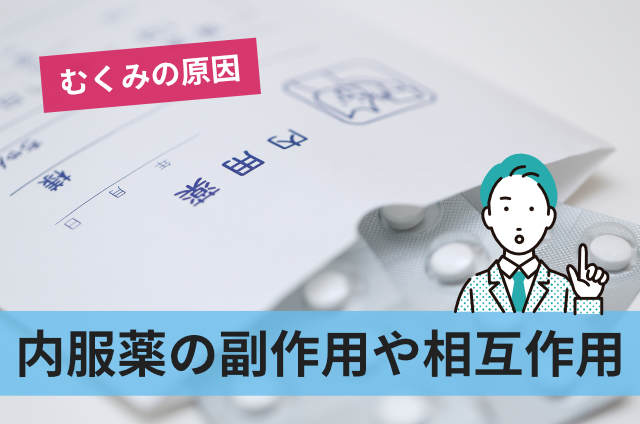
糖尿病の内服薬には、多剤との併用による相互作用でむくみが生じるものがいくつかあります。
スルホニル尿素薬やチアゾリジン薬といった薬を服用している場合に注意したい症状のひとつが、薬剤そのものの副作用により生じる身体のむくみです。
治療薬のなかでも、インスリン抵抗性の改善に働きかけるものを服用している場合、副作用のむくみは心疾患の有無に関わらず起こり得ます。
糖尿病治療薬だけではなく、多くの内服薬の毒素を分解したり排泄したりする臓器は、腎臓や肝臓です。
そのため薬の内服によって肝機能や腎機能、心機能が悪化すると、むくみが出現する人は年齢を問わず一定数います。
さらに心不全や劇状肝炎のように、内服薬に由来した重篤な副作用が起こる場合もあります。
糖尿病治療薬のなかには、肝機能や腎機能障害を持っている人が服用すると、人によっては状態の悪化を招くケースがあるのを知っておくのも大切です。
同様に腎疾患や肝疾患を持つ人も、内服治療を開始した際には体調変化に気を配る必要があります。
持病のある人が薬を服用する際は、必ずかかりつけの医療機関に知らせましょう。
インスリン抵抗性の改善が関与して身体にむくみの症状が出現する男女比は、男性よりも女性の方が多い傾向にあります。
インスリン抵抗性の改善に働きかけるような種類の薬を服用する場合、身体にむくみの症状が出ていないか定期的に確認しておくのも大切です。
糖尿病治療薬でむくみが起こるのは、内服薬だけが原因ではありません。
高血糖状態の身体にインスリン注射をすると、インスリン浮腫と呼ばれる状態に発展する可能性があります。
インスリン浮腫は決して頻度が高い副反応ではなく、多くは極端な高血糖に対してインスリン注射をした場合に起こります。
しかし稀に一般的な2型糖尿病で新たにインスリン療法を開始した場合でも、インスリン浮腫や心不全などに陥る可能性があるため、注意が必要です。



・食後や空腹時の血糖値を抑制する
・インスリンの効き目を高め分泌を促す
など、糖尿病予防におけるポリフェノールの研究が進んでいます。
ぜひ、こちらの記事も確認してみてください。
薬科大学・国立大学が注目するポリフェノール研究
むくみの有無をしっかり観察するのが体調悪化を防ぐポイント


糖尿病とむくみは一見、関係しないようにも感じられるものの、実は重大な病気の前触れという可能性があります。
特に血栓症や心不全、肝機能障害や腎機能障害によって起こるむくみは、適切な治療が遅れると重篤な状態になり得ます。
しかしむくみの原因や程度は様々で、生理的なものが原因であるときもあれば、そうでない場合もあります。
生理的な変化によって起こるむくみは、長時間立ち仕事をこなしていたり重力が原因であったりするケースがほとんどです。
生理的なむくみである場合、左右で明らかに足の太さが違ったり靴が入らなかったりするまでむくむケースは非常に少ないです。
一方、何らかの異常が身体に起きている場合のむくみには、靴が履けないほど足が太くなったり体重が数日で数キロ増えたりする特徴があります。
むくみの症状が徐々に増してくる場合、自分の身体を日々しっかり観察していても、なかなか気づきません。
身体の異常にいち早く気づくためには、1〜2日おきにふくらはぎの周囲の長さや体重を測定して記録しておくのがよいでしょう。
足の甲を押してみて、元に戻るまでの時間を測定するのも、むくみの程度を知るには効果的な方法です。
その際には元に戻るまでの時間を測定し、血圧手帳などに記録しておくと自分の身体を把握する手がかりになります。
少しでも心配な症状が出現した場合や身体に違和感を覚えた際には、しっかりとした検査をするためにも医療機関を受診するのが大切です。