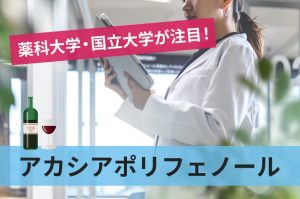40代以降の男女を中心に、健康診断や人間ドックがきっかけで糖尿病と診断されるケースが増えています。
食の欧米化や職場の人員不足といった多くの社会的要因から、不規則な生活習慣を送っている人は少なくなく、糖尿病という病気は今や他人事ではなくなっています。
糖尿病の治療は医療の進歩とともに進化しており、日々新しい治療法や薬が研究されたり開発されたりしています。
糖尿病は早期発見できた場合、内服療法やインスリン療法をせずに生活習慣の改善のみで対処できるケースもあり、その経過は千差万別です。
しかし糖尿病であると診断されてしまった人にとって心配なのは、治る病気であるか、いつまで治療すべきかという経過に関するものではないでしょうか。
本記事では、糖尿病は治る病気なのかという点について、病気についての基本的な知識や治療方法を含めて解説していきます。
- 糖尿病は治る病気なのか
- 糖尿病の経過を左右する要因
- 血糖コントロールと治療目標の目処について
- 回復の後押しとなり得る糖尿病治療方法
- 近年注目されている新しい糖尿病治療方法
糖尿病は適切な治療で治る病気なのか
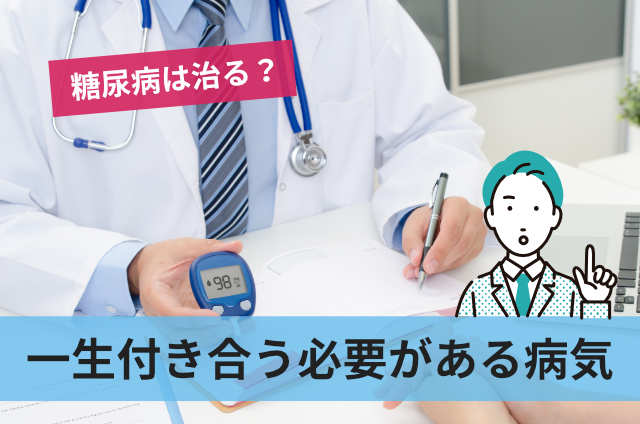
結論から言うと、糖尿病は治るものではなく、一生付き合う必要がある病気です。
病気そのものに危険はありませんが、そのまま放置しておくと糖尿病に起因した病気あるいは合併症に発展し、命に関わるリスクが出てきます。
そのため、糖尿病治療は治すという考えではなく、病気に起因する合併症や他の疾患を防ぐという考え方のもと治療を進めます。
一般的に行われる主な治療は、食事・運動療法、インスリン療法と内服療法の3種類です。
糖尿病の進行具合や合併症の有無などで選択される治療法は異なりますが、ほとんどの人は、食事・運動療法と内服療法を組み合わせて治療します。
病気がある程度進行しており、血糖やインスリンの分泌に問題となった場合は、前述した2つの治療法の他にインスリン療法が加わるケースもあります。
病気の発見が早く、薬を内服する必要性はないと判断された人は、食事・運動療法のみの治療も可能です。
反対に早期発見ができてもしっかり治療に取り組まなければ、血糖値のコントロールは悪化して病気は進行の一途をたどります。
内服治療やインスリン治療をしている人も同様で、真面目に取り組む姿勢で現状維持、あるいはそれ以上の回復がかなう可能性もゼロではありません。
しかし薬を飲み忘れたり好きな食事のみ摂っていたりすると、血糖コントロールが悪化して、急激に病気や合併症が進行します。
つまり、糖尿病という病気をどの程度まで回復させられるかについては、患者一人ひとりの病状と治療への取り組み方次第によるということです。
そして治る病気ではない糖尿病は、ある程度まで回復させられても、発病前のような不規則生活習慣に戻ると病気は急激に進行します。
そのため糖尿病と診断されても健康的に長生きしていくには、病状に関係なく、医師から指導された生活習慣をしっかりと継続していくのが大切です。
糖尿病は長期的な治療に対する取り組み方が今後の経過を左右する

膵臓の機能は一度低下してしまうと、元の状態には戻らないため、ある程度回復しても血糖値を下げる治療は欠かせません。
糖尿病の根本的な原因は高血糖であり、血糖を下げる働きが低下する病気となってしまった以上、血糖値を上げないような生活習慣は必須となります。
状態が改善したからといって元の生活に戻り、適切な血糖値が保てなくなると経過は悪化し、やがて合併症の発症や進行につながります。
治療の成果があり、内服療法が不要な状態になったとしても、病気を進行させずに良い状態を維持していくには食事療法と運動療法の継続が大切です。
糖尿病治療でいちばん大切なのが血糖コントロール
糖尿病は長期間に及ぶ高血糖の持続により、インスリンを分泌する膵臓が疲弊し、機能が低下した結果生じる病気です。
インスリンは食事や飲み物の摂取によって上昇した血糖値を、適正な値まで下げて調節する働きを持ち、膵臓のランゲルハンス島β細胞から分泌されます。
血糖値を上げる働きを担うグルカゴンも膵臓から分泌されますが、膵臓の機能が低下しても分泌状態にさほど変化は起こりません。
血糖値が下がっても、グルカゴンの他に血糖を上昇させるホルモンが存在するだけではなく、食べ物の摂取で血糖を上昇させられるためです。
しかし高血糖に陥った場合は体内でインスリンが分泌されない限り、血糖値は元に戻らず、上がったままの状態となります。
前述したように高血糖が持続した結果として招かれるのが、病気自体や合併症の進行です。
こうした糖尿病の進行や合併症を防ぐためにも、血糖値が上がったときに是正できるよう、病状に合わせて血糖をコントロールする治療が必要となります。

近年の研究では、ポリフェノールの一種にインスリンの分泌を促し効き目を高める作用が発見されています。
詳しくはこちらの記事をご確認ください。
糖尿病治療は基本的な生活習慣の見直しと内服治療
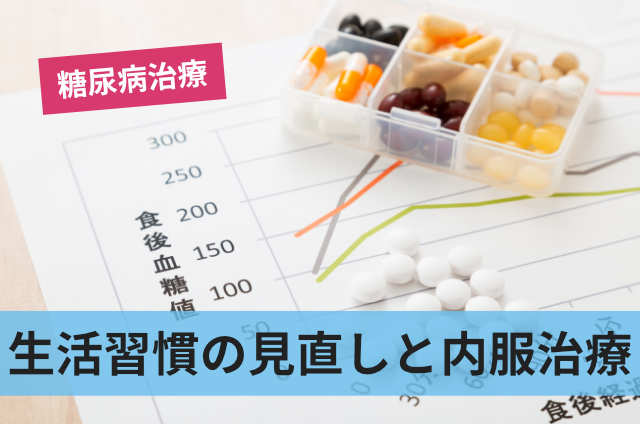
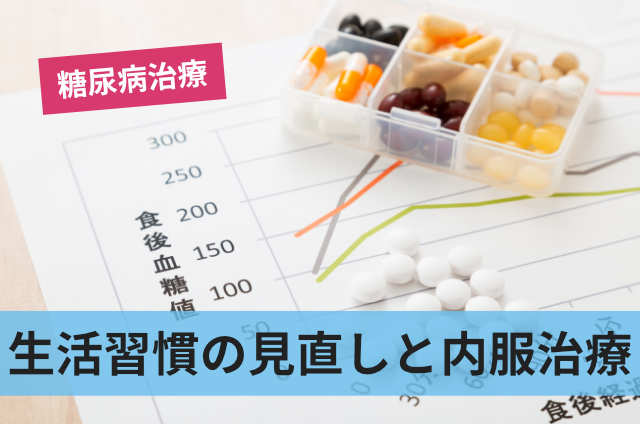
血糖値の正常化を目指す目的で行われる主体的な治療が、生活習慣の見直しと血糖降下薬の服用です。
高血糖の原因となるような生活習慣の改善は、血糖コントロールの良し悪しは関係なく、全ての糖尿病患者に対して必須な治療法となります。
あまりにもヘモグロビンA1cや血糖値が高く、急いで血糖値を適正な数値に戻す必要がない限りは、生活習慣の改善から始めるのが一般的です。
その場合は、患者の体重や日頃の運動習慣などを考慮しながら、無理のない食生活の改善と負担の少ない運動量でのエクササイズから始めていきます。
食事療法や運動療法を2〜3ヶ月間実施し、目標としているヘモグロビンヘモグロビンA1cや血糖値に到達できると、内服治療をしない状態での経過観察が可能です。
しかし食事療法や運動療法に真面目に取り組んでいても、目標となる血糖値に到達できなかった場合、薬物療法が開始されます。
糖尿病に用いる代表的な経口治療薬は、以下の通りです。
- α-グルコシダーゼ阻害薬
- SLGT2阻害薬
- チアゾリジン薬
- ビグアナイド薬
- スルホニル尿素(SU)薬 など
上記のように経口治療薬は豊富な種類があり、一人ひとりの病態に見合った薬を選択して効果があるかどうかを判定していきます。
糖尿病治療薬は豊富な種類があり、患者の病態や他の薬との飲み合わせを考慮しながら、どの薬を使用するのか検討します。
そのため薬物療法を開始してすぐに効果が出なかったとしても、すぐにインスリン治療などが開始されるわけではありません。
そういったときは、さまざまな薬を組み合わせたり使用する薬を変更したりして、薬物療法を継続しながら経過観察していくパターンが一般的です。
薬物療法を開始して間もない時期には、すぐに血糖やヘモグロビンA1cの値が下がらないからと諦めずに、粘り強く薬の内服と生活習慣の改善を続けてみてください。
病状の安定化と現状維持を目指すために大切なヘモグロビンA1c
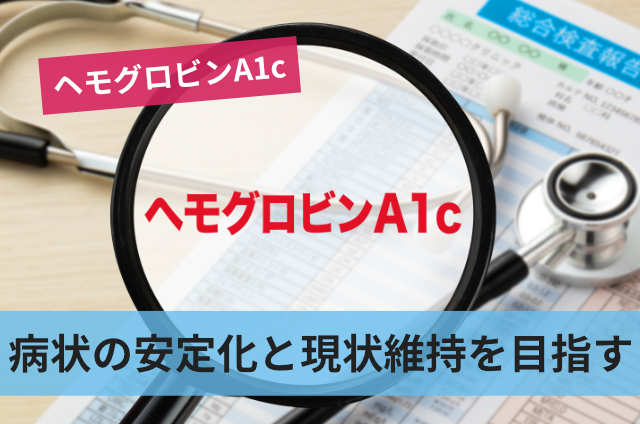
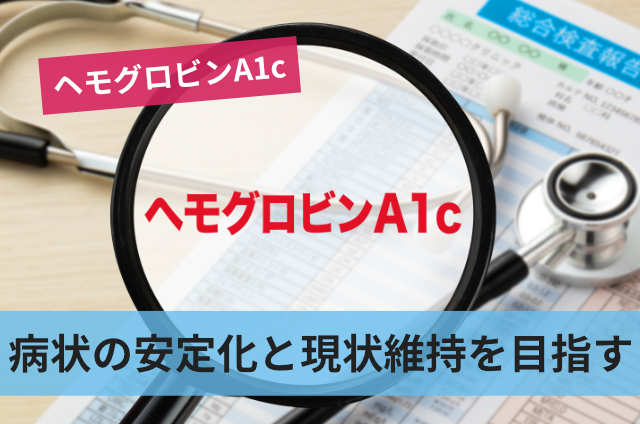
糖尿病で薬を内服する必要がない程度まで回復させて、健康な生活を送るには、血糖値を正常な値に可能な限り近づけて維持する必要があります。
そのために必要なのは、高血糖の根本的な原因となる食生活や運動不足といった生活習慣の改善です。
血糖の正常な値は空腹時が約70〜100mL/dL、食後で約140mg/dL以下とされていますが、いちばん重視されるのはヘモグロビンA1cの値です。
約1〜2ヶ月で寿命が尽きるヘモグロビンの特徴を活かした検査で、食事やストレスなどの要因で左右されないのがヘモグロビンA1cの利点です。
糖尿病治療において血糖の推移を推測したり評価したりする場合は、血糖値よりもヘモグロビンA1cの方が向いています。
現在実施している治療を評価し、今後の治療目標や方針を見直すためにヘモグロビンA1cの測定が重要です。
日本糖尿病学会では、妊婦や高齢者を除く一般成人を対象とした糖尿病の治療目標となるヘモグロビンA1cの数値の目安を、以下のように定めています。
- 血糖値の正常化を目指す場合の目標値:ヘモグロビンA1c 6.0%未満
- 合併症の予防を目指す場合の目標値:ヘモグロビンA1c 7.0%未満
- 治療強化が困難な場合の目標値:ヘモグロビンA1c 8.0%未満
上記に示した治療目標を目安として、低血糖などの副作用なく、達成可能なヘモグロビンA1cの数値を目標として設定します。
血糖値の正常化が目指せるケース
一般的に、治療目標として血糖値の正常化を目指せる人は、ヘモグロビンA1cが6.0〜7.0%未満であるのが前提です。
さらに、食事や運動療法のみで達成できる見込みがあるのに加え、薬物療法をしていても血糖値が大きく変動したり低血糖に陥ったりするリスクが少ない人という条件があります。
この目標で治療を開始する人は、糖尿病と診断されても努力次第で健康な人と同じような生活がかないます。
しかし達成できたからといって元の生活に戻してしまうと、すぐに血糖値が上がり、場合によっては薬物治療が必要な状態まで悪化してしまう人もいます。
そのため健康的な身体づくりには、継続的な食事・運動療法による血糖コントロールの維持が大切です。
合併症予防もしくは進行を遅らせるのを目標とするケース
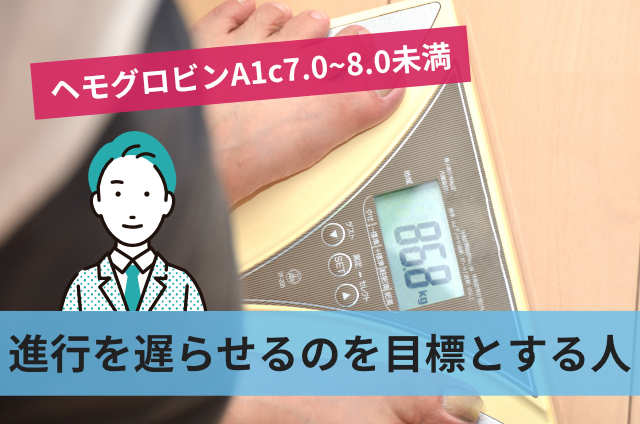
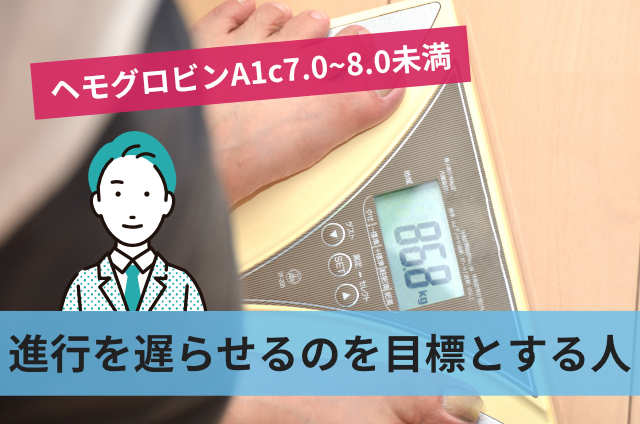
糖尿病合併症を予防するもしくは合併症の進行を遅らせるのを治療目標とする人は、基本的にヘモグロビンA1cが7.0〜8.0%未満である場合です。
一般的にヘモグロビンA1cの数値が7.0%を上回ると、糖尿病合併症を発症するリスクが一段と高くなります。
ヘモグロビンA1cが7.0〜8.0%未満の人は、一貫して、合併症のリスクを回避するためにヘモグロビンA1cの目標値を7.0%とします。
そのため、ヘモグロビンA1cが7.0〜8.0%未満でも血糖値が高い場合は、必要に応じて血糖降下薬の追加が必要になるケースも存在します。
合併症予防を目的とした治療においては、定期的な体重測定、血糖や尿の検査も必要になります。
血糖やヘモグロビンA1cの値を測定して状態をみながら、必要に応じて薬の種類を変更したり、服薬する量を増やしたりといった処方の調整も必要です。
目標が達成できて血糖コントロールやその他の全身状態が良い人は、薬の量を徐々に加減していきながら血糖の正常化を目指していきます。
すでに合併症を起こしている時は、血糖の正常化を目指す治療をしていても合併症そのものは良くならないという点に留意しておきましょう。
糖尿病腎症や網膜症、神経障害からなる糖尿病合併症は一度発症すると元通りには戻らず、進行を予防する他に方法がありません。
合併症を起こしている場合は、糖尿病の血糖コントロールが良好であるときでも、専門医を受診して経過を観察してください。
治療強化が必要とされるケース
糖尿病の治療強化が必要とされる検査値の目安は、ヘモグロビンA1cが8.0%以上です。
そのため糖尿病と診断されたときのヘモグロビンA1c値が8.0%以上の場合は、すでに糖尿病合併症を発症している可能性も高いです。
血糖コントロールが不良と判断されるような検査結果では、最初に血糖値を早急に元に戻すような治療が開始されます。
ヘモグロビンA1cが8.0%以上となるまで高血糖が持続しているケースでは、腎臓の糸球体に負担がかかり、腎機能障害を起こします。
腎臓の機能がどの程度障害を受けているのか、早急に治療が必要な状態ではないかどうかを調べるための検査も同時に行います。
腎機能が低下していた場合は、糖尿病治療と並行して泌尿器科や腎臓内科などでしっかりと治療を受けていく必要があります。
そしてこれ以上の合併症が起きないよう、インスリン注射や血糖降下薬などを利用しながら、血糖を改善させる治療をしなければなりません。
ここで、何らかが原因となってうまく血糖をコントロールできない状態となったケースでは、ヘモグロビンA1cの目標値を8.0%と設定して治療していきます。
持病がなかったり、食事療法や運動療法を含めて日常生活面での自己管理がしっかりできていたりする人は、徐々にヘモグロビンA1cの目標値を下げていきます。
ヘモグロビンA1cの治療目標が7.0%以下に設定できるまでに回復する人もいる一方で、現状維持に止まる人もいるため、治療経過は人によって違ってくるでしょう。
回復の後押しとなり得る教育入院やインスリン療法


糖尿病治療において、ヘモグロビンA1cの数値が高くなるたびに、回復から遠ざかってしまうのではと不安に思う人もいるのではないでしょうか。
確かに糖尿病は、基本的な内服治療や食事療法、運動療法という基本的な治療を行っていくのみで回復させるには限界があります。
そこで利用されているのが、教育入院やインスリンを取り入れた治療法です。
教育入院は一定期間入院し、糖尿病患者が自分の病気を正しく理解したうえで、治療に必要な知識や自己管理を学ぶ治療法を指します。
より強力な治療に加え、生活を見直して、自分に見合った食事療法や運動療法をしっかりと身につけられる利点もあります。
ほかにも専門医が行う外来より詳細な検査の実施や診察を通して、さらに血糖をコントロールできるような治療を導入できます。
一方で、インスリン療法が選択されるのは以下の場合です。
- 内服薬のみでは血糖コントロールが難しい場合
- 膵臓の機能を回復させたい場合
インスリン療法は内服治療と並行しながら行うものから、食直前に注射を欠かさずに実施するものなど注射の仕方も豊富です。
インスリン療法は膵臓の機能を温存するだけでなく、正常なインスリン分泌のパターンを再現してより強化的な血糖コントロールができる利点を持ちます。
当然治療によって良好な血糖コントロールが維持できた際には、再び内服治療に切り替えてさらなる血糖値の改善も目指せます。
インスリン療法は外来で導入するケースもありますが、教育入院のもと時間をかけて行う場合もあり、導入方法は対象となる人の理解度や病状次第です。
このように教育入院やインスリン治療を取り入れた結果、血糖コントロールが大幅に改善する人も少なくありません。
インスリン療法や教育入院は糖尿病治療の最後の砦ではなく、病気の進行や合併症を食い止めるための有効な治療といえるでしょう。



・食後や空腹時の血糖値を抑制する
・インスリンの効き目を高め分泌を促す
など、糖尿病予防におけるポリフェノールの研究が進んでいます。
ぜひ、こちらの記事も確認してみてください。
薬科大学・国立大学が注目するポリフェノール研究
将来的には日常生活での不便さを感じない糖尿病治療が可能


糖尿病は日本の国民病というだけではなく、世界的にも罹患者数の多い病気です。
そのため糖尿病の完治を目指して、さまざまな病態のメカニズムを解明したり新たな治療薬を開発したりする研究が日々行われています。
特に、糖尿病治療における新しい医療機器として注目されているのが、持続血糖測定器という機械です。
特に、新しくつくられた持続血糖測定器はスマホ連携機能が付いており、日常的な血糖値の推移をスマホアプリで管理できる利点も持っています。
装着方法を練習やアプリの入手が必要となりますが、高血糖や低血糖に陥るとアラームが鳴るなどの機能が備わっているのは、利点のひとつです。
将来的に治る病気を目指して、世界中でこうした医療機器や治療薬の開発、保険適用の拡大は年々進歩しています。
糖尿病だから治らないと落ち込む必要はなく、治療に対する努力次第で、これまでと変わらない生活の実現も期待されています。
糖尿病だからと絶望視せず前向きな姿勢で治療に取り組むのが大切
糖尿病は、一度罹患してしまったら一生付き合っていかなければならないと聞くと、先の将来について考えてしまう人がいるのではないでしょうか。
病気を診断されるのは、40代以降の中年期から増える傾向にあり、これから家族の進学や結婚などといったライフイベントを控えている人が多い世代です。
こうしたライフイベントを目前に、糖尿病の治療やその合併症に伴う治療が必要となると、仕事に関する不安や金銭的な心配を抱える人もたくさんいます。
前向きな治療の継続は、個人差はありますが内服薬が不要になるまでの回復をもたらしたり長期間、現状維持できるケースも少なくありません。
糖尿病になってしまったからと絶望視せず、しっかりと一歩ずつ自分に見合った治療に取り組んでいくのが回復に向けての第一歩です。
医師や看護師の手助けを借りながら、できる治療に取り組んでいきましょう。