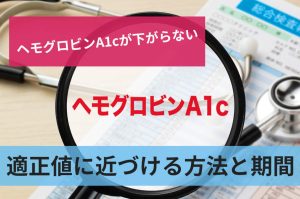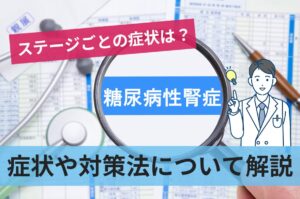近年では糖尿病予防やダイエットなどを目的に、血糖値を意識した食事をする人が増えています。
しかし血糖値を上げる麺類やパン類をはじめとする炭水化物は、日々の食事で欠かせない主食であり、大好物としている人もいるのではないでしょうか。
血糖値の急上昇を防ぐには血糖を上げない食事が必要ですが、糖質を絶対に摂ってはいけないわけではありません。
血糖値を上げる食べ物を楽しみながらでも、いくつかの工夫を実践すると上手に高血糖の予防ができます。
本記事では甘いお菓子や麺類など、好きなものを楽しみながら健康的な食生活を送るための方法を紹介していきます。
- 血糖値をコントロールするための食材の選び
- 一日の食事の組み立て方
- 血糖値上昇を防ぐための食前の工夫
- 食事を楽しんだあとの過ごし方
甘いものを無理に我慢せずに健康的に糖質制限をしたい人は、ぜひ参考にしてください。
甘いものや炭水化物は食べ方の工夫をすると怖くない

血糖値を上げる食べ物の代表は甘い食べ物や炭水化物で、下記のような食材が当てはまります。
- ご飯やもち米
- パン
- 果物やドライフルーツ
- ジュース類
- 麺類
- いも類
- かぼちゃや根菜
これらは、血糖値を上昇させる原因物質であるブドウ糖やデンプンを豊富に含んでいます。
炭水化物でも各食材で含まれるデンプンの量や構造は異なり、デンプンが糖質に変化して血液中に吸収される速度は異なります。
ブドウ糖は、血糖値(グルコース)の原材料で、血液中に吸収される糖質のなかでは最も吸収速度が早い物質です。
そのため糖質でもブドウ糖やデンプンを豊富に含む食べ物は、食後に高血糖を招くといわれています。
確かに炭水化物をはじめとする甘い食べ物は血糖値を上げますが、一切食べてはいけないものではありません。
炭水化物に含まれる糖質は、身体の筋肉を作ったり脳に栄養を送ったりするうえで欠かせない栄養素です。
毎日の食卓で炭水化物を我慢したくない場合は、用いる食材の種類や摂取量、食べるタイミングを考えて献立を組み立てるとよいでしょう。
炭水化物はそれぞれの食材のGI値を考えて選択する
炭水化物を選ぶ際はどの食材を選ぶと血糖値が上昇するかという視点で、食品のGI値を確認するとよいです。
ここで示している吸収速度は、食後2時間までが目安です。
血液への吸収速度が最も早いブドウ糖のGI値を100とし、その値に近い場合は高GI、低い場合は低GIと示されます。
糖質の吸収速度が早い高GI食品を取り入れると血糖値は急激に上昇し、吸収速度が低い低GI食品を取り入れた場合は緩やかに上昇していきます。
急激な血糖値の上昇は血液中に占める糖の濃度が増して血流が滞るため、血液をサラサラの状態にするには体内で血糖値の修正が必要です。
そこで血糖値の上昇を脳が察知すると膵臓からインスリンを分泌させて、血糖値を適正な値まで戻します。
食事による血糖値の上昇具合が高ければ高いほど、インスリンが多量に分泌されて血糖値が急降下します。
その際、急速に糖質が処理されるため、脳や筋肉をはじめとする体内の臓器に十分な栄養が供給されません。
結果的に体内の臓器が飢餓状態になって生じるのが、食後の頭痛や眠気です。
このように食事によって血糖値が急上昇したあと、急降下する現象を血糖値スパイクといいます。
血糖値スパイクがもたらす食後の眠気や頭痛を防ぐには、血糖値を上げない食事の工夫が必要です。
糖質の吸収速度が遅い低GI食品を摂取した場合、食後の糖質も緩やかに上昇するためインスリンも徐々に分泌されていきます。
この仕組みを利用して一日に摂取する食事を組み立て、食後血糖値の急激な上昇を防ぎます。
その日の食卓の主役となる炭水化物を決める場合には、以下の表を参考に食材を決めてください。
| GI値とその分類 | 該当食品 |
|---|---|
| 高GI食品(GI値:70以上) | クロワッサン、白米、食パン、シリアルそうめん、うどん、餅、赤飯、氷砂糖、焼き菓子 じゃがいも、にんじん、とうもろこし |
| 中GI食品(GI値:56〜69) | パスタ、白米のおかゆ、玄米+精白米 かぼちゃ、長芋、里芋、パイナップル、桃缶、 |
| 低GI食品(GI値:55以下) | そば、中華麺、ライ麦パン、全粒粉パン、麦、オートミール、玄米、全粒粉パスタ りんご、さつまいも、れんこん、きのこ類 |
糖質を多く含む小麦製品全般は高血糖の原因になると認識されていますが、中華麺やパスタは白米よりもGI値が低い食材です。
毎回のように食事のメインを白米にする必要はなく、中華麺やそばを適量摂取した方が食後の血糖値を抑えられるケースもあります。
どうしても高GI食品を摂取したくなった場合は、摂取する時間帯やほかに摂取する食べ物の選び方を工夫すると血糖値の上昇が抑えられます。
高GI食品が欲しいときは食べるタイミングと組み合わせを工夫

時間のない朝には、朝食をパンとコーヒーで済ませてしまうという人もいるのではないでしょうか。
つまり朝食が何時であれ、その日の始まりに摂取するものは低GI食品にする必要があるということです。
人間は朝起きたときの代謝が最も低く、朝食を食べて太陽の光を浴びたり活動したりしながら徐々に代謝を上げていきます。
代謝の低いときに血糖値が急上昇するような食事をすると、身体が糖を適切に処理できず、血管内に不要な糖が残って朝食後の血糖値が上がります。
食後に急上昇した血糖が大量のインスリン分泌を促し、一気に血糖値が下降する状態が前述した血糖値スパイクです。
血糖値スパイクは血糖値の急上昇と急降下によって疲労感や倦怠感をもたらすだけではなく、脳が血糖値を上げようとして過剰な食欲を招きます。
その結果、空腹感から昼食でも糖質を欲してしまい、食後の血糖値が再び上がるという悪循環に陥ります。
一方で朝食にたんぱく質と野菜を中心とした食事を摂り、血糖値を緩やかに上昇させた場合にはさほど空腹感を感じません。
このセカンドミール効果を有効に活用して朝食に摂る血糖を最小限にすると、食後高血糖や血糖値スパイクを予防できます。
朝食にGI値が高い食べ物を摂取したくなった場合は、昼食に甘みの少ないものを食べるようにするとよいです。
同じパンでも甘いパンと甘味のない惣菜パンでは、含まれている糖質の量が異なります。
クリームパンやメロンパンより、クロワッサンやチーズが含まれたパンを選択するといった食べ物の選択をしてみてください。
そして炭水化物以外にも、豊富な食物繊維を含む緑黄色野菜やきのこ類と組み合わせて食べるのが大切です。
食物繊維は体内で糖質を包んで腸管内をゆっくりと移動するため、糖質が血液に吸収されるのを遅らせます。
朝にパンを食べる場合は先に緑黄色野菜などで食物繊維を摂取してから、メインとなるクロワッサンや食パンなどを食べるよう順番を工夫します。
食物繊維が胃や腸に分解されるまで15分程度必要なため、十分な時間を空けてからメインとなる高GI食品を食べるのが大切です。
白米を食べる場合もルールは同じで、納豆やおひたしなどの副菜を食べてから15分程度時間を置いてご飯を食べるようにしましょう。
朝食にパンやシリアルと一緒にコーヒーを飲む習慣がある人は、コーヒーの飲み方にもひと工夫が必要です。
コーヒーを飲む習慣がある人はミルク類に気をつける
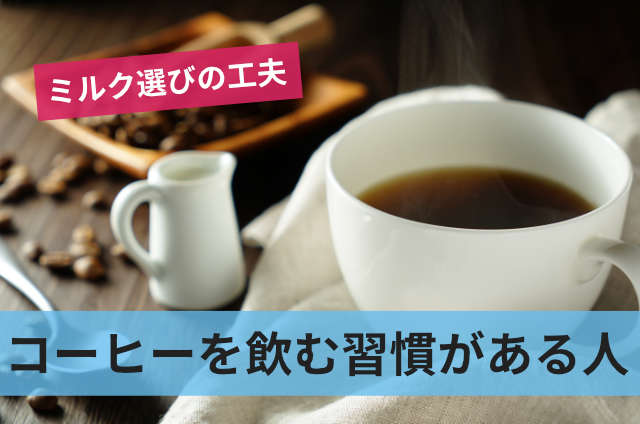
朝に眠気覚ましとして、コーヒーを飲む習慣がある人は少なくありません。
コーヒーは脳を活性化するため、忙しい朝に身体にスイッチを入れたい人にとって欠かせない飲み物です。
朝起きたときにコーヒーを飲みたい場合は、砂糖やミルクを含まないブラックコーヒーやエスプレッソが適しています。
しかしブラックコーヒーやエスプレッソに含まれているカフェインは、胃酸の分泌をあと押しします。
さらにコーヒーに含まれるタンニンは、胃の粘膜に負担をかける物質です。
朝に限らず空腹時にコーヒーを飲むと、カフェインやタンニンが及ぼす作用から胃粘膜を保護するものが無いため胃の不調につながります。
胃の負担を軽くするためにミルクを足すのがよいのですが、その場合ミルク選びの工夫が必要です。
最近では市販の牛乳には成分が調整されていないものから、低脂肪乳、無脂肪乳など種類がいくつかあります。
ほかにも豆乳やオーツミルク、アーモンドミルクなどの選択肢も増え、牛乳と異なる風味を楽しめるようになりました。
ただし朝にコーヒーを飲む場合は、糖質に目を向けてミルクを選択するのが大切です。
ミルクの種類ごとに含まれる糖質量を、下記にまとめました。
| ミルクの種類 | 糖質量の目安(200mLあたり) |
|---|---|
| 牛乳 | 9.0g以上 |
| 豆乳 | 3.0g以上 |
| オーツミルク | 10.0g以上 |
| アーモンドミルク | 1.0g未満 |
上記にまとめた表からわかるように、オーツミルクや牛乳は他のミルクより糖質量が多めです。
ラテやコーヒー牛乳として朝のコーヒーを楽しみたい場合は、アーモンドミルクや豆乳を選択するとよいでしょう。
砂糖を水に溶かして作ったコーヒーシロップはブドウ糖と同程度、あるいはそれ以上の高GI調味料です。
それに対してオリゴ糖やココナッツシュガーなどのGI値は10〜30程度で、上白糖やコーヒーシロップよりも圧倒的にGI値が低い特徴を持ちます。
自宅やカフェでコーヒーを飲んでいる人は、可能な限りコーヒーやラテのGI値が低くなるよう調整します。
調味料が限られている職場などの場所では、ミルクを多めにしてシロップや砂糖を半量に減らす工夫をしてみてください。
さらに1日の食べ物を通じて血糖値の急上昇を防ぐには、献立の組み立て方や食べるタイミングなどの工夫も大切です。
1日3食で血糖値をコントロールする食事の考え方
24時間のうち最低でも3回やってくる食事で、私たちはさまざまな食事を口にします。
血糖値の上昇を防ぐには、好きなものを自分のタイミングで食べるのではなく、それぞれの食材を適したタイミングで食べるのがポイントです。
そして血糖値の上昇を抑えるために徹底して糖質摂取を控えても、効果を実感していない人は自分の食事方法を見直してみてください。
豊富な食材や食品のなかには糖分が少ないように思えるものでも、実は糖質が豊富な食べ物も存在します。
食事メニューを決める際に欠かせない食材選びやメニューの組み立て方は、ちょっとしたポイントを押さえると血糖値の調整に役立ちます。
朝食はたんぱく質を意識した献立にするのがよい

朝食を摂取するにあたって、糖分を意識した食事をしている人を見かけます。
糖質が必要なのは事実ですが、朝食は糖質よりたんぱく質の摂取を意識した方がよいです。
パンやご飯などの食材から気軽に摂取できる糖質に対して、肉などに含まれるたんぱく質は朝食に摂らない人もいます。
しかしたんぱく質は体内時計を整える働きを持つ栄養素で、朝・昼・夜と3食それぞれのタイミングで摂取するのが大切です。
たんぱく質は多くのアミノ酸が複雑に組み合って構成されており、そのなかのトリプトファンがというアミノ酸が体内時計と密接に関係しています。
トリプトファンを体内に取り込むと、ビタミンB6と結合して脳内でセロトニンやメラトニンに変化します。
メラトニンは睡眠と覚醒のリズムを調整するホルモンで、夜になると多量に分泌され、朝方にかけて徐々に減少します。
セロトニンとメラトニンの分泌量が充実していると、体内時計が整って血糖値や血圧などを調節する作用が高まります。
トリプトファンは日中摂取したものがセロトニンになり、夕方以降に摂取した分がメラトニンに変化するのが特徴です。
朝食からトリプトファンを含むたんぱく質を摂取すると、その分生成されるセロトニンの量が増えて1日の活動にスイッチを入れてくれます。
これらの食材はパンに乗せたりトーストしたりする工夫で、気軽にたんぱく質を摂取できます。
その際、主食とするパンはGI値の低いライ麦パンや全粒粉を用いたパンがよいでしょう。
前の日のおかずを活用して、ご飯とおかずを摂取するのもよいです。
ただしその際はご飯よりGI値が低いおかずを先に食べ、そのあとにご飯を食べるなどして順番を変えると血糖の上昇が防げます。
和食、洋食ともにメインとなる炭水化物のみで済ませず、たんぱく質を意識して身体に取り入れるようにしてください。
朝食より、ボリュームのある食事を摂る人が多い昼と夜では、重要視するポイントが異なるため、次に解説しますり
昼食と夕食はPFCバランスを重視した食べ方を実践

朝よりも食事量が増える傾向にある昼と夜は、血糖値を急上昇させないようPFCバランスを考慮して摂取するのが理想です。
日本人に適したPFCバランスは通常でP:F:C=2:2:6、運動習慣がある人はP:F:C=3:2:5の割合です。
このバランスを考慮したうえで、さらにたんぱく質を摂取できているかを意識すると基礎代謝の維持にもつながります。
たんぱく質は前述したように体内時計を整える栄養素であるのに加えて、筋肉を作るためにも欠かせない栄養素です。
1日で必要なたんぱく質量を十分に摂取して筋肉を発達させると、自ずと基礎代謝量も上がります。
基礎代謝量の増加により1日で必要なエネルギーが増え、糖質をより効果的に消費できるようになります。
日本人の多くは1日あたり必要なたんぱく質量を摂取できている人が少なく、幅広い年齢でたんぱく質不足の人が目立ちます。
1日に必要なたんぱく質量を満たすためには、1食あたり20gの摂取を目安に献立を組んでみてください。
食材を選ぶ際は白身魚や鶏胸肉などを毎食の主役にすると、効率よくたんぱく質を摂取できます。
ほかにもレンズ豆やひよこ豆、豆腐など食物繊維が豊富な豆類は、糖質の吸収を抑える役目も担える貴重なたんぱく源です。
ほかにもフェタチーズやモッツァレラチーズは、脂肪分が少ないうえに豊富なたんぱく質を含んでいます。
できる限り脂質を抑えたいと考えている人は、こうした脂肪分少なめの乳製品なども活用してみてください。
さらに食後に急速な血糖の上昇を防ぐためには、食事の前後で口にする飲み物に対しても関心を持つようにしましょう。
食前に摂る水分としてお酢やレモンの水割りを活用する

食事の時間が遅れてどうしようもないくらい空腹を感じたとき、飴やガムを食べて空腹を紛らわせているのではないでしょうか。
飴やガムはほんの少量で空腹を満たせるお菓子であると同時に、ブドウ糖や果糖、エリスリトールといった糖質のかたまりです。
何か小腹を満たしたいときは、飴を舐めるより果実酢やレモンの水割りが適しています。
お酢は果実酢のみならず、米酢や黒酢と豊富な種類がありますが特に種類は問いません。
食前にお酢やレモンの水割りがよいのは、それらには豊富な酢酸やクエン酸が含まれているからです。
お酢に含まれる酢酸は酸味のある調味料に用いられている成分で、胃腸の動きを鈍らせる働きがあります。
そしてレモンやライムに含まれるクエン酸は、消化管を膨張させたり空腹感を満たしたりする働きを持つ成分です。
これらの成分を食前に取り込むと血糖値を高めようとする身体の働きが落ち着いて、食事を楽しんだあとも血糖値の上昇が穏やかになります。
お酢に含まれる酢酸やレモンに含まれるクエン酸は、酸性度が高いため原液で摂取するのは避けた方がよいです。
特にレモン汁のpHは胃酸よりも低く、頻繁に原液を口にすると歯のエナメル質を溶かす恐れもあります。
歯のエナメル質を保護する視点でいうと、酢酸も同様に歯にとってはよくないため水割りで飲むのがよいでしょう。
炭酸水で割ると炭酸散水に含まれるガスが胃を膨張させるため、満腹感が得られて食事量が抑えられます。
お酢やレモン汁を割った水は、食前に加え間食したいときや食後でも満腹感が得られないときも飲めるのが利点です。
ただし晩酌にアルコールを入れて楽しむのは、肝臓に負担をかけたり高血圧の原因となったりするため焼酎などは使用せずに飲んでください。
さらに高血糖を防ぐのに大切なのが、バランスの良い食事と身体への負担が少ない運動の組み合わせです。
食後の散歩やヨガは高血糖を予防できる有用なエクササイズ

食後にゆっくりお腹を休めているとつい眠気に襲われてしまう人は、散歩やヨガなどで気分転換しましょう。
会社勤めの人はランチを楽しんだあとに会社まで徒歩で戻ると、ただ座っている食後の休憩よりも質のよい時間が過ごせます。
食後に眠くなったり横になりたくなったりする人は、タイマーをかけて4〜5分お腹を休めたあとに、胃腸に負担がかからない程度の静かな運動をしてみてください。
運動の種類は心拍数がほんの少し上がる程度の体操やウォーキング、ヨガやピラティスといった有酸素運動が有効です。
特にウォーキングやヨガによる動作は、全身の血流を促進して筋力を鍛えます。
筋肉を使うと糖の消費量が増えるだけではなく、筋肉が発達するため基礎代謝を上げられます。
食後の軽い運動は、筋肉を動かすように意識するのがポイントです。
自宅で掃除機をかけたり食材の買い物に行ったりする家事を、食後に行う方法もあります。
軽い運動でもよいので食後にほんの少し身体を動かし、血糖の上昇を防ぎながら気分転換を図りましょう。
血糖を上げる食べ物を楽しむときは食事の工夫が大切
ダイエットや糖尿病予防のために糖質が含まれた食べ物を控えようと努力している人でも、どうしても無性に甘いものが欲しくなるときはあります。
血糖値を上げる食べ物は身体にとって良くないですが、我慢するあまりストレスを溜め込みすぎるのもよくありません。
溜め込んだストレスがコルチゾールなどのストレスホルモンを放出させると、かえって血糖の上昇を招きます。
食べる順番や食材選び、食後の運動といった取り組みの積み重ねは、血糖値に加えて高血圧や肥満の予防にも貢献するでしょう。
無理に食事を我慢せず、健康的な食習慣をつける工夫を継続してみてください。