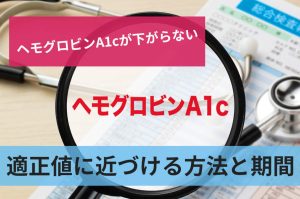現代において糖尿病は国民病であり、予備軍の人も合わせると患者数は約2,000万人にのぼります。
参照元:糖尿病診療の現状 – 厚生労働省
治療は食事と運動が基本となるため、食品選びが大切です。
納豆は栄養価が高く、体に良い影響を及ぼす成分が多く含まれています。
今回は納豆が持つ健康効果や食べる時の注意点、効果的な食べ方についてまとめました。
- 納豆は糖尿病の人や血糖値が気になる人に適した食品
- 糖尿病の人が納豆を食べる時の注意点
- 納豆の健康効果を高めるのに効果的な食べ方
糖尿病の人や納豆が血糖値に与える効果が知りたい人は、ぜひ参考にしてください。
納豆は糖尿病の人や血糖値が気になる人に適した食品である

納豆にはさまざまな栄養素や血糖値に良い影響を与える成分が含まれており、糖尿病の人や血糖値が気になる人に適した食品です。
納豆が糖尿病の人や血糖値が気になる人に適している理由は、以下の6つが挙げられます。
- 植物性タンパク質が血糖値の上昇を抑える
- 大豆イソフラボンが耐糖能異常を改善する
- 水溶性食物繊維が豊富に含まれている
- ナットウキナーゼが血栓を分解する
- 脂肪肝の予防や改善に役立つ
- 腸内環境を整えて慢性炎症を防ぐ
納豆は大豆を原料にして作られる、発酵食品です。
昔から日本人に親しまれており、白米と合わせてよく食べられています。
GI値とは、食後に血糖値が上昇する速度を表す指標のことです。
ブドウ糖を摂取した場合のGI値が100であるのに対して納豆は30であり、食後に血糖値が急上昇するのを防げます。
食品成分データベースによると、糸引き納豆100gあたりのカロリーは184kcalです。
市販されている納豆1パックは40〜50gが多く、1食分のカロリーは約90kcalとなります。
納豆は食品のGI値が気になる人、1日の摂取カロリーを制限している人も取り入れられるでしょう。
ここからは、納豆が糖尿病の人や血糖値が気になる人に適している理由について解説します。
タンパク質は食後に血糖値が上昇するのを抑える働きがある
納豆に含まれているタンパク質は糖質の吸収を促し、血糖値が上昇するのを抑える働きがあります。
タンパク質によって糖質の吸収速度が遅くなり、血糖値の上昇がおだやかになるためです。
タンパク質の摂取は、筋肉の維持や増加にもつながります。
筋肉には血糖値を調整する働きがあるため、筋肉量が増えると血糖値が下がります。
さらにタンパク質に含まれるペプチドという成分は、血糖値の上昇を抑えるのに効果的です。
ペプチドはGLP-1というホルモンに作用し、インスリンの分泌を促進する働きがあります。
さらにGLP-1は、血糖値を上げるグルカゴンというホルモンの分泌を抑制します。
健康的な食習慣には、動物性と植物性のタンパク質をバランスよく摂取する必要があります。
動物性タンパク質に偏った食生活を送っていると、糖尿病や心臓病を発症するリスクが高まると考えられています。
肉や卵をよく食べる人は動物性タンパク質に偏っている可能性があるため、植物性タンパク質の摂取が効果的です。
植物性タンパク質は豆類や野菜、穀類に含まれていますが、中でも豆類に多く含まれています。
植物性タンパク質は、動物性タンパク質に比べてカロリーや脂質が少ないのも特徴です。
糖尿病の人は肥満や脂質異常症を併発している場合も多いため、植物性タンパク質を含む食品が役立つでしょう。
大豆イソフラボンには耐糖能異常を改善する働きが期待できる
納豆には大豆イソフラボンというポリフェノールが含まれており、耐糖能異常を改善する働きが期待できます。
血糖値を正常に保てない原因はインスリンの分泌量や作用不足であり、糖尿病を発症するリスクが高まります。
以下のいずれかにあてはまる場合、耐糖能異常と診断されます。
- 空腹時の血糖値が110〜125mg/dLである
- 75g経口ブドウ糖負荷試験で2時間後の血糖値が140〜199md/dLである
大豆イソフラボンはブドウ糖の取り込みを改善してインスリンの効きを良くすると考えられているため、糖尿病を発症するリスクを下げられます。
大豆イソフラボンには、コレステロール値や血圧を下げる働きも期待できます。
ある実験によると、大豆食品の摂取により悪玉コレステロールの数値が低下したという結果が出ました。
動脈硬化は糖尿病と密接な関係があり、さまざまな合併症を引き起こします。
大豆イソフラボンの血管を拡張させる作用は、血圧の低下にも効果的です。
参照元:大豆イソフラボンによる高血圧モデル動物の血圧の低下 – 農研機構
女性ホルモンに似た働きを持っているため、更年期の不調を抱える女性も積極的に摂取したい成分です。

イソフラボンはカテキン、アントシアニンと並び代表的なポリフェノールの1つです。
ポリフェノールが持つ様々な効果については、こちらの記事で詳しくまとめています。
糖質の吸収速度を遅らせる水溶性食物繊維が豊富に含まれている
納豆には糖質の吸収速度を遅らせる水溶性食物繊維が豊富に含まれており、血糖値の急上昇を予防するのに効果的です。
食物繊維には水溶性と不溶性の2種類があり、水溶性食物繊維は腸の中で糖質を包み込んでゆっくりと移動します。
糖質の消化吸収が遅くなると、食後に血糖値が上がる速度も遅くなります。
大豆食品には両方の食物繊維が含まれており、血糖値に良い影響を与える食品です。
研究によると、納豆は大豆よりも血糖値の上昇を抑える効果が大きいと報告されました。
効果に差が出る要因は明らかになっていませんが、水溶性食物繊維の含有量や粘性が関係していると考えられています。
食物繊維の摂取は、血糖値コントロールにも役立ちます。
糖尿病診療ガイドライン2024では、2型糖尿病患者に対する積極的な食物繊維の摂取が推奨されています。
参照元:食事療法 – 日本糖尿病学会
糖尿病の治療は、食事や運動など生活習慣の改善が重要です。
食物繊維には食べ過ぎを予防する効果もあり、健康的な食習慣につながります。
ナットウキナーゼには血栓の元になる成分を分解する働きがある


納豆に含まれるナットウキナーゼには血栓の元になる成分を分解する働きがあり、血栓ができるのを予防できます。
大豆を発酵させる際に納豆菌から生産され、血栓の元となるフィブリンという成分を分解する働きがあります。
糖尿病の人は血糖値の高い状態が続いて血管が損傷し、血栓症のリスクが高まります。
血管のつまる部位によって脳梗塞や心筋梗塞など、命に関わる疾患を引き起こします。
血液の流れを妨げる血栓がなくなると血流が改善され、動脈硬化の予防にも効果的です。
ナットウキナーゼの血液をさらさらにする作用は、血圧を下げる働きもあります。
糖尿病と高血圧は深く影響しているため、合併する割合が高くなります。
ナットウキナーゼの摂取により、合併症の予防や血流の改善などさまざまな効果が期待できるでしょう。
大豆食品の1つである納豆は脂肪肝の予防や改善に役立つ
脂肪肝には食習慣が大きく影響しており、大豆食品の1つである納豆は脂肪肝の予防や改善に役立ちます。
主な原因は飲酒や肥満であり、放置すると肝硬変などの肝臓疾患を引き起こします。
参照元:e-ヘルスネット – 厚生労働省
脂肪肝は、インスリン抵抗性や肝線維化につながる恐れもあります。
インスリン抵抗性があると血糖コントロールがうまくいかず、高血糖の状態が続いてしまいます。
脂肪肝がインスリン抵抗性を悪化させ、糖尿病が進行する恐れもあります。
症状が進行すると肝臓が硬くなり、肝機能の低下につながります。
日本食の中でも特に大豆食品や海藻類、魚介類には肝線維化を抑制する働きがあります。
糖尿病患者の中には、脂肪肝を併発している人も多いでしょう。
体重を数kg減らすだけでも改善が見込めるため、体重管理が大切です。
発酵食品には腸内環境を整えて慢性炎症を防ぐ働きがある
発酵食品の納豆には腸内環境を整え、慢性炎症を防ぐ働きがあります。
継続的な炎症反応はインスリンの分泌にも影響し、血糖値の上昇を招きます。
発酵食品には腸内細菌の多様性を高め、炎症を減らす作用があります。
腸内環境の改善により腸内フローラのバランスが整うと、血糖値の改善に効果的です。
腸内には多くの種類の細菌が存在し、種類ごとに腸内フローラと呼ばれる集合体を形成しています。
腸内フローラを構成している腸内細菌は、大きく分けて以下の3つです。
- 善玉菌
- 悪玉菌
- 日和見菌
これらの細菌のバランスは善玉菌2割、悪玉菌1割、日和見菌7割が理想といわれています。
腸内環境を健康に保つには、善玉菌を優位に保つのが大切です。
善玉菌が多い人はインスリンの感受性が高く、糖尿病を発症するリスクが下がるという研究結果も発表されました。
発酵食品や食物繊維は善玉菌を増やすのに役立ち、納豆菌には腸内の善玉菌を増やす効果があります。
なお納豆は糖尿病の人にも適した食品ですが、食べる際にはいくつか注意点もあります。
糖尿病の人や血糖値が気になる人が納豆を食べる時には注意点もある


糖尿病の人や血糖値が気になる人が納豆を食べる時の注意点は、以下の3つです。
- ワルファリンを服用している間は納豆を控える
- 納豆ばかりを多く食べ過ぎないようにする
- 白米の量が多くなりすぎないようにする
納豆は栄養価が高く、血糖値に対する良い効果が期待できます。
ただし同じ食品でも食べ方によって、血糖値が変わります。
血糖値を急激に上げないためには、以下の点を意識するのが大切です。
- 1日3食を規則正しく食べる
- 食事はよく噛んでゆっくり食べる
- 食物繊維、タンパク質、炭水化物の順番で食べる
これらを意識すると血糖値に良い影響を与え、血糖値コントロールが可能となります。
それでは、納豆を食べる時の注意点を1つずつ解説します。
納豆はワルファリン(商品名ワーファリン)の効用を弱める
納豆はワルファリン(商品名ワーファリン)の効用を弱めてしまうため、服用している人は避けたほうがよいでしょう。
ワルファリン(商品名ワーファリン)は血液をさらさらにし、血栓ができるのを防ぐ抗凝固剤です。
血液が固まる際にはビタミンKが必要となり、ワルファリン(商品名ワーファリン)にはビタミンKの働きを阻害する作用があります。
納豆にはビタミンKが多く含まれているため、薬の効きが弱くなってしまいます。
納豆を食べたい人や日常的に納豆を食べる習慣がある人は、薬を変更するのも1つの方法です。
血液をさらさらにする薬は、他にリバーロキサバン(商品名イグザレルト)やアピキサバン(商品名エリキュース)などがあります。
病院や薬局によって取り扱いのある薬が異なるため、医師や薬剤師に相談しましょう。
納豆の他にも緑藻類の一種であるクロレラや青汁はビタミンKが多く、ワルファリン(商品名ワーファリン)を服用している人は避けるべきです。
なお納豆の原料である大豆にはビタミンKが多く含まれておらず、食べても問題ありません。
納豆を多く食べても健康効果が倍増するわけではない


納豆を多く食べても健康効果が倍増するわけではないため、食べる量は1日1パックが目安です。
2パック食べたからといってすぐに症状が出るわけではありませんが、納豆の食べ過ぎは体に悪影響を及ぼします。
納豆菌は生命力が強く、増えすぎると腹痛や吐き気につながる恐れがあります。
本来は腸内環境を整える働きがありますが、お腹の調子が改善しない場合は一度納豆を控えてみましょう。
納豆にはプリン体が多く含まれており、食べ過ぎると痛風や高尿酸血症を発症するリスクが高まります。
さらに納豆には大豆イソフラボンの安全な一日摂取目安量のうち、約半分の量が含まれています。
大豆イソフラボンの一日摂取目安量の上限は70〜75mgですが、納豆1パックの含有量は36g程度です。
他に豆腐などの大豆食品を食べると、目安量を超える可能性があります。
参照元:大豆イソフラボンの一日摂取目安量の上限値 – 食品安全委員会
健康的な食習慣には特定の食品に偏らず、バランスの良い食事を心がけるのが大切です。
納豆といっしょに食べる白米は多く食べ過ぎない
白米には糖質が多く含まれているため、納豆といっしょに食べる際は多く食べ過ぎないのが大切です。
白米は高GI食品であり、食後の血糖値が急激に上昇します。
さらに白米の上に納豆を乗せて食べると、ごはんの熱で納豆の健康効果が薄れてしまう可能性があります。
炊きたてごはんは90度以上、保温した状態でも60度以上あります。
納豆と白米を同時に食べる際は別の器に入れる、またはごはんを冷ましてから乗せるとよいでしょう。
糖尿病の人は、納豆を白米の前に食べるのも効果的です。
納豆にはタンパク質や食物繊維が豊富に含まれており、炭水化物の前に食べると血糖値の上昇を抑えられます。
食物繊維を含む食品は満腹感が感じられ、炭水化物の量を減らすのに有効です。
納豆は食べ方によって健康効果を高められるため、続けて効果的な食べ方を紹介します。
納豆の健康効果を高めるために効果的な食べ方は3つある


納豆の健康効果を高めるために効果的な食べ方は、以下の3つです。
- 加熱調理をしない
- 継続して食べる
- 他の食材と組み合わせて食べる
納豆を食べ続けるのが難しい場合は、粉納豆を取り入れる方法もあります。
粉納豆は納豆をフリーズドライで粉末化した食品であり、納豆と同等の健康効果が期待できます。
量の調節が簡単で、常温での長期保存が可能です。
料理に入れて気軽に食べられるため、普段納豆を食べる習慣がない人にも向いています。
それでは、納豆の効果的な食べ方について1つずつ解説します。
納豆の効果を最大限に得るには加熱調理をせずに食べる
納豆に含まれるナットウキナーゼは熱に弱く、効果を最大限に得るには加熱調理をせずに食べるのが大切です。
納豆チャーハンや納豆汁などは、調理して熱を加えると効果が薄れる恐れがあります。
納豆は常温に戻すと、再発酵という現象が起こります。
再発酵が進むと糸引きが悪くなり、味や食感が落ちてしまいます。
麺類に納豆をトッピングする場合も熱が伝わるのを防ぐため、冷たい麺を選ぶようにします。
自分の悩みや生活に合ったタイミングで継続して食べる


納豆の健康効果を得るには、自分の悩みや生活に合ったタイミングで継続して食べるのが効果的です。
納豆の継続的な摂取により、腸内環境の改善につながります。
納豆は食べる時間帯によって、得られる効果が異なります。
朝に食べると、ダイエットや肥満予防に効果があります。
納豆にはタンパク質が豊富に含まれており、朝にタンパク質を摂取すると代謝が上がるためです。
炭水化物とタンパク質の組み合わせは体内時計のリセットに役立ち、代謝の向上につながります。
そのため朝食に納豆ごはんを食べると、ダイエット効果が期待できます。
ただし中には毎朝パンを食べていて、朝食に納豆を食べるのが難しい人もいるでしょう。
夜に納豆を食べると、ナットウキナーゼの血液をサラサラにする効果を最大限に引き出せます。
そのため、夕食に納豆を食べると血栓や高血圧の予防に有効です。
夜中から朝方にかけての時間帯は血流が滞り、血栓ができるリスクが高まります。
食後10〜12時間はナットウキナーゼが活発に働き、血栓や心筋梗塞の発作を予防できます。
人によって悩みや生活習慣が異なるため、自分に合ったタイミングで習慣にするのが大切です。
他の食材を組み合わせて食べるとより高い健康効果が得られる
納豆と他の食材を組み合わせて食べると相乗効果が生まれ、より高い健康効果が得られます。
納豆と組み合わせるのにおすすめの食材は、以下のとおりです。
- キムチ
- チーズ
- お酢
- ねぎやニラなどの薬味
キムチは乳酸菌を多く含む発酵食品で、納豆と相性の良い食品の1つです。
納豆菌と乳酸菌の働きにより善玉菌が活性化され、腸内環境の改善が期待できます。
乳酸菌は血糖値やコレステロール値を下げ、便秘を解消する働きがあります。
チーズもキムチと同様に発酵食品であり、免疫力の向上に効果的です。
お酢と納豆は、どちらも血糖値の上昇を抑える働きがあります。
納豆にお酢を加えると糸引きが弱くなる場合がありますが、糖尿病には有効な組み合わせです。
ねぎやニラなどの薬味には、納豆独特の臭いを緩和する効果があります。
どちらもビタミンB1の働きを助け、代謝や疲労回復を促します。
納豆は調理せずにそのまま食べられますが、食べ続けていると味に飽きてしまう人もいるでしょう。
他の食材との組み合わせにより味に変化が出るため、無理なく納豆を継続できます。



プロアントシアニジンという抗酸化成分には、糖の吸収を抑えたり、血糖値の上昇を抑制する効果が確認されています。
プロアントシアニジンを多く含む食材を意識するなども心がけましょう。
プロアントシアニジンを多く含む食品一覧
納豆にはさまざまな健康効果があり血糖値の上昇を抑えられる


納豆にはさまざまな健康効果があり、糖尿病の人も積極的に摂取したい食品です。
納豆に含まれるタンパク質や食物繊維には、血糖値が急激に上がるのを抑える効果があります。
他にも血栓や脂肪幹の予防、腸内環境の改善などに役立ちます。
糖尿病患者の中には他の病気を併発している人も多く、納豆の健康効果は合併症の予防や改善に効果的です。
ただしワルファリンの服用中に納豆を食べると、薬の作用が弱まってしまいます。
納豆ばかりを食べるのは避け、白米を多く食べ過ぎないのも大切です。
納豆は加熱調理をせず、他の食材と組み合わせると健康効果を高められます。
食事に継続して納豆を取り入れ、血糖値の安定を目指しましょう。