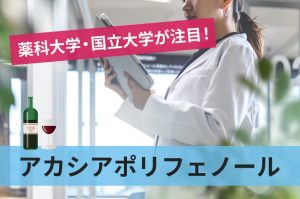夜寝ている時や運動している最中に、ふくらはぎがつる経験をした人も多いのではないでしょうか。
ふくらはぎがつる症状は誰にでも起こり得ますが、通常よりも頻繁に起こる場合は、糖尿病に罹患しているかもしれません。
今回は、糖尿病により頻繁にふくらはぎがつる原因を紹介します。
さらに、糖尿病とはどのような病気であるかや、糖尿病以外でふくらはぎがつる原因および予防方法についても解説します。
- ふくらはぎがつる原因として糖尿病の可能性がある
- 糖尿病は重篤な合併症状を引き起こす怖い病気
- 糖尿病以外では身体の冷えや過度な運動などもふくらはぎがつる原因になる
- 水分補給や身体の冷え防止がふくらはぎがつる症状の予防になる
- ふくらはぎがつった場合はストレッチや電解質を含む水分補給がよい
今回の記事を参考にして、糖尿病の早期発見に活かしてください。
ふくらはぎが頻繁につる場合は糖尿病を疑ってみよう

ふくらはぎが頻繁につる場合は、糖尿病に罹患している可能性があります。
ふくらはぎのつりと糖尿病の関係を、意外だと感じる人も多いのではないでしょうか。
糖尿病になると、血行の悪化や神経系における障害が起こり、ふくらはぎがつる要因になる場合が多いです。
糖尿病によるふくらはぎのつりの原因を、以下の3点を中心に解説します。
- 糖尿病によって末梢神経障害が引き起こされる
- 血行障害もふくらはぎのつりに影響する
- 高血糖を起因とした脱水症状も原因になる
糖尿病とふくらはぎのつりとの関係を理解して、糖尿病の早期発見に努めましょう。
糖尿病によって末梢神経障害が引き起こされる
糖尿病になると末梢神経障害が引き起こされて、身体の末端部分である足先にしびれや痛みが起こる原因となります。
収縮した筋肉を弛緩させる動きも適切になされないため、ふくらはぎのつりが頻発してしまうという仕組みです。
糖尿病が継続すると、末梢神経へのダメージが蓄積していき、さらに筋肉系統への指令が正しく行われなくなってしまいます。
血行障害もふくらはぎのつりに影響する
糖尿病が原因で起こる血行障害も、ふくらはぎがつる要因になります。
糖尿病になって血糖値の高い状態が継続すると、体内の血管の壁が厚くなって血流が悪くなります。
血流が悪くなると、十分な血液が末端の筋肉に届かなくなって、酸素や栄養素の不足により筋肉が正常に働かなくなるという仕組みです。
さらに、血行不良は筋肉の動作不良に加え、疲労の蓄積が解消されない原因にもつながります。
血行が悪くなると、足がつるケースが増えてしまう点も理解しておきましょう。
高血糖を起因とした脱水症状も原因になる

糖尿病により高血糖の状態が継続すると、脱水症状が引き起こされてふくらはぎのつりが起きるケースが増えます。
高血糖の状態が継続すると、尿による水分の排出量が増加します。
意識的に水分を摂取しないと、体内の水分が不足して脱水症状を引き起こします。
さらに、尿の排出量増加は水分不足に加えて、カリウムやマグネシウムなどのミネラル不足になるケースも多いです。
ミネラル不足は筋肉のけいれんの要因になる場合が多いため、ふくらはぎのつりにつながります。
糖尿病が疑われる場合は、脱水症状に陥らないようにこまめな水分補給を心がけましょう。
下肢で引き起こされる動脈閉塞性疾患も原因に
糖尿病が原因で、下肢に動脈閉塞性疾患が起こり、ふくらはぎのつりが頻発する場合があります。
動脈閉塞性疾患の代表例としては、心筋梗塞や脳梗塞などが該当します。
これらの重篤な症状は、糖尿病を起因とした動脈硬化が原因で引き起こされるケースが多いです。
ふくらはぎのつりが頻発する場合は、動脈閉塞性疾患に罹患している可能性についても考慮しましょう。
夜間のみでなく昼間の時間帯でも起こる場合が多い
糖尿病が原因で起こるふくらはぎのつりは、夜間のみでなく昼間の時間帯でも頻発するという特徴があります。
一般的に、ふくらはぎがつる症状は夜間の寝ている際に起こる場合が多いです。
夜間に時々起こるふくらはぎのつりは、筋肉疲労や水分不足といった一時的な要因で発生しているケースが多く見られます。
一方で、昼間の時間帯でふくらはぎのつりが頻発する場合は、何らかの病気が起因となっている可能性が高いです。
気になる症状がある場合は、糖尿病の可能性を含め専門医に相談してみるとよいでしょう。
ふくらはぎがつる原因となる糖尿病について詳しく理解しよう
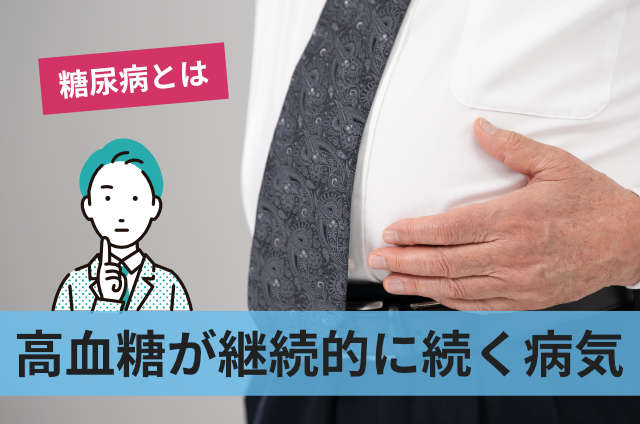
ふくらはぎのつりの原因となる糖尿病は、生活習慣病の1つであり、生活に多大な支障を来してしまう病気です。
重篤な合併症を引き起こす場合も多く、状況によっては命の危険に関わるケースもあります。
初期症状が現れないまま病状が進行する可能性もある病気のため、ふくらはぎのつりをきっかけに専門医に診断を受けてみるのもよいでしょう。
糖尿病について、以下の4点を中心にして説明します。
- インスリン異常により血糖値が下がらない状態
- 糖尿病は原因により4つに分類できる
- 糖尿病の症状は多岐にわたる
- 糖尿病は重篤な合併症につながるリスクがある
糖尿病についての理解を深め、早期発見に努めてください。
インスリン異常により血糖値が下がらない状態
糖尿病は、インスリンが強く影響する病気です。
インスリンは、すい臓のランゲルハンス島と呼ばれる場所で生成されます。
血液中から身体の各組織が糖質を吸収するために、インスリンが必要不可欠です。
食物などを吸収して生成された糖質は、血液によって全身を巡ります。
インスリンは細胞のドアを開けるような役割を持っており、血液中の糖質がスムーズに細胞に吸収されます。
インスリンが何らかの要因で十分な働きをしなくなると、血液中の糖質が各組織に行き届かず血液中に蓄積されてしまい、血糖値が下がりません。
インスリンの分泌量が減少したり、働きそのものが弱まったりすると、血糖値が下がらず糖尿病のリスクが高くなると理解しておきましょう。
糖尿病は原因により4つに分類できる
インスリンの働きが不足する原因によって、糖尿病は大きく以下の4つに分類できます。
- インスリンを体内で生成できない1型糖尿病
- 生活習慣病が主な原因である2型糖尿病
- 妊婦特有の妊娠糖尿病
- 遺伝子異常や薬物が影響するその他の糖尿病
糖尿病に罹患したといっても、どの分類に含まれるかによって対処や治療方法が異なります。
糖尿病を理解するうえで、4つの分類を把握して自分が罹患した原因が何であるかを把握するのは重要です。
以下で4つの分類の特徴をそれぞれ解説するので、糖尿病を理解する際の参考にしてください。
インスリンを体内で生成できない1型糖尿病
1型糖尿病と診断された場合は、生命を維持するために体外から人工的にインスリンを投与する必要があります。
すい臓のランゲルハンス島内の細胞が壊されるのが原因と考えられていますが、細胞が壊れる原因自体ははっきりとわかっていません。
発症する年齢にも法則性はなく、若年層にも広く症例があります。
1型糖尿病と、次に紹介する2型糖尿病とでは、対処の仕方や治療方法が大きく異なるため、明確に区別して理解しましょう。
生活習慣病が主な原因である2型糖尿病
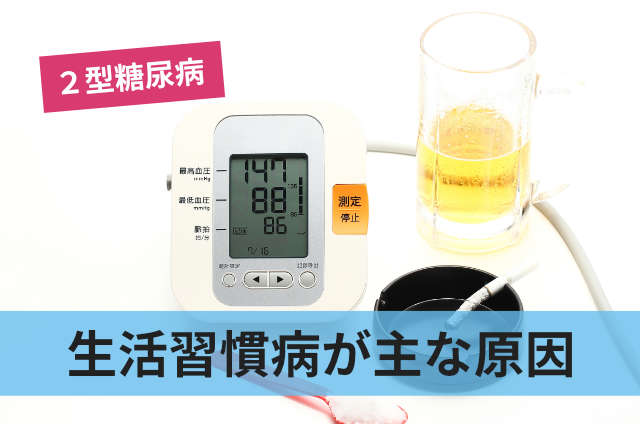
2型糖尿病とは、生活習慣の乱れや遺伝的な要因が影響して、インスリンの分泌や働きが低下して起こる糖尿病のことです。
2型糖尿病患者の多くは生活習慣の乱れから発症しているため、生活習慣病の代表例として考えられています。
2型糖尿病になる要因としては、食べ過ぎや運動不足による肥満、ストレスなどが挙げられます。
環境的な要因で発症するケースが多いため、2型糖尿病を予防するには基本的な生活習慣の見直しが必要不可欠です。
普段からバランスのよい食事を心がけて、適度な運動をしながら十分な睡眠時間を確保するといった基本的な生活リズムを保ち、2型糖尿病にならないように取り組みましょう。
妊婦特有の妊娠糖尿病
妊娠中は、胎盤で生成されるホルモンの影響で、インスリンの働きが弱くなってしまいます。
特に食後の血糖値が急激に上昇する症例が見られ、場合によっては母子ともに深刻な状態に陥ってしまう恐れもあります。
妊娠前から血糖値が高い人が妊娠すると、妊娠糖尿病と診断されるケースが多いです。
妊娠糖尿病と診断されると、急激に血糖値が上昇しないよう、食事を1日4〜6回に分けて摂取する場合もあります。
妊娠糖尿病と診断されても、出産を終えると血糖値が正常に戻るケースが多いですが、妊娠糖尿病を経験すると将来的に糖尿病になるリスクが高いと考えられています。
遺伝子異常や薬物が影響するその他の糖尿病
糖尿病は、遺伝子異常が影響して発症する場合もあります。
遺伝子異常によりインスリンの生成が難しかったり、インスリンが作用する過程で異常が見られる場合が多いです。
さらに、用いている治療薬の影響を受けて糖尿病を発症する事例があります。
薬物が原因の糖尿病は、投薬を中止すると症状が改善されるケースが多いです。
しかし、元々の病気を悪化させてしまうリスクが大きくなるため、主治医と相談しながら投薬量を調整したり治療方法を見直したりする必要があります。
糖尿病の症状は多岐にわたる
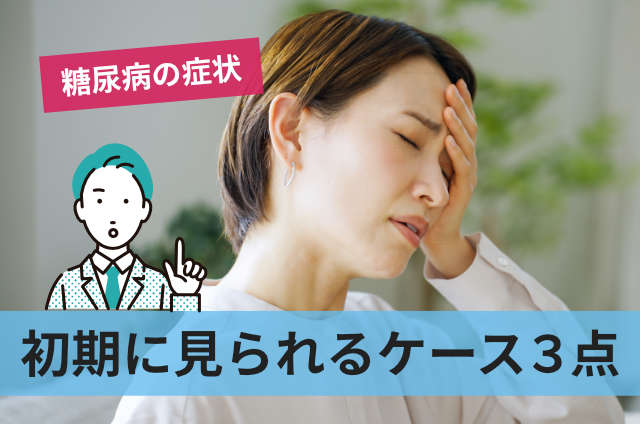
糖尿病に罹患した際の症状には、様々なものがあります。
一方で、自覚症状として認識されず、放置してしまうケースが多いのも事実です。
日常生活で普通に起こりうる違和感が、実は糖尿病の初期症状であったという事例も多く見られます。
少しの違和感であっても糖尿病の可能性を意識して、早期に対応できるようになっておくとよいでしょう。
糖尿病の症状のうち、初期に見られるケースが多い事例を以下に3点紹介します。
- 尿量が多くなりのどの渇きを感じる
- 常にだるさがあり疲労が抜けない
- 食事をしても空腹が収まらない
糖尿病の代表的な症状を理解して、専門医で早めの診断を受けるように努めてください。
尿量が多くなりのどの渇きを感じる
糖尿病になると、尿の量や回数が多くなったり、のどの渇きを頻繁に感じるようになったりします。
そのため体内の水分が不足するようになり、のどの渇きにつながるという仕組みです。
さらに、血液中の糖を排出するために尿量も増えます。
こまめに水分を摂取しないと、体内での代謝に追いつかず脱水症状に見舞われる恐れがあります。
普段よりも尿の量や回数が増えたり、汗をかいていないのに無性にのどが渇くと感じたりする際は、糖尿病を疑って専門医に相談してみましょう。
常にだるさがあり疲労が抜けない
常にだるさを感じ、疲労感が抜けない場合も、糖尿病に罹患している可能性があります。
糖尿病によるインスリン不足は、血中の糖質を体内に取り込めなくするため、エネルギー不足を引き起こす要因です。
しっかりと食事をしても栄養分が体内に吸収されず、活動に必要なエネルギーが不足してしまいます。
だるさや疲労は、日常生活において感じるケースが多い状態であるため、見過ごしてしまう人も多いでしょう。
普段よりもだるさが強く、疲労感がなかなか抜けないと感じる場合には、糖尿病の可能性を疑って早期の診断を受けてください。
食事をしても空腹が収まらない

食事をしても空腹が収まらない場合は、糖尿病に罹患しているかもしれません。
糖尿病になると体内のインスリンが働かなくなり、糖質からエネルギーを摂取できなくなってしまいます。
糖質からのエネルギー供給が得られなくなった場合、筋肉を消費してタンパク質をエネルギー源として活用する作用が起こります。
同時に脂肪をエネルギーに変える作用も起こるため、身体から筋肉と脂肪が減り、伴って体重が減少する仕組みです。
食事を食べても空腹が収まらず、体重が自然に減少している場合は、糖尿病の可能性を疑って専門医に相談するとよいでしょう。
糖尿病は重篤な合併症につながるリスクがある
糖尿病になると、のどの渇きや疲労感など様々な症状が出てきます。
さらに病状が進行すると、重篤な合併症を引き起こしてしまう可能性があります。
糖尿病の合併症の中には、失明や足の切断など甚大な問題を引き起こしてしまう場合もあるため、初期症状の段階で早期に治療を開始するのが大事です。
糖尿病を起因とした重篤な合併症のうち、代表的なものを以下に6例紹介します。
- 視力低下や失明につながる糖尿病網膜症
- 腎不全や尿毒症のリスクがある糖尿病腎症
- 足の壊疽につながる糖尿病神経障害
- 生命に危険がおよぶ脳梗塞
- 心臓の働きが低下する心筋梗塞
- 足の血管の動脈硬化による末梢動脈性疾患
糖尿病の合併症の怖さを理解して、早期発見および治療に努めましょう。
視力低下や失明につながる糖尿病網膜症
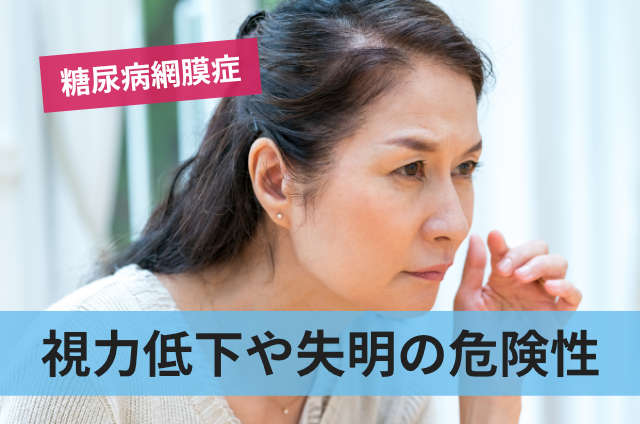
高血糖の影響により、ものを見る機能を持つ網膜に損傷が起こり発症します。
網膜は、光や色を感じ取る神経細胞が敷き詰められ、無数の血管が張り巡らされている組織です。
高血糖の状態が継続すると、網膜にある細い血管に損傷が起こり、詰まってしまいます。
血管の詰まりにより網膜に十分な酸素が行き届かなくなり、網膜剥離などの原因になります。
糖尿病網膜症は、失明原因のうち上位を占めている病気です。
初期異常が現れないケースが多いため、気が付いた時にはかなり症状が進んでいる場合もあります。
糖尿病の疑いがある場合は、治療に合わせて定期的に眼科を受診して眼底検査を受けるのがよいでしょう。
腎不全や尿毒症のリスクがある糖尿病腎症
糖尿病腎症は、糖尿病の三大合併症の1つで、腎臓の機能が低下して起こる病気です。
高血糖の状態が続き腎臓内の細い血管に損傷が起こると、腎臓のろ過機能が働かなくなり、老廃物を排泄できず体内に蓄積されてしまいます。
糖尿病腎症が進行すると、人工透析による治療が必要です。
糖尿病腎症の初期段階では、尿にたんぱく質が漏れ出してくるため、尿検査により病気の発見が可能です。
糖尿病の疑いがある場合は、定期的な尿検査を実施して、糖尿病腎症を併発していないか確認する必要があります。
足の壊疽につながる糖尿病神経障害
糖尿病神経障害は、糖尿病の三大合併症の1つで、糖尿病の合併症の中で最も多い病気です。
糖尿病による高血糖の状態が長期間続くと、感覚神経や運動神経および自律神経など、様々な神経系に障害が及びます。
神経系における障害が起因となり、しびれや痛みおよび冷感を覚えたり、筋力低下により歩行が困難になったりします。
さらに病状が進行すると、動脈硬化が悪化して足先への血液循環が悪くなる場合が多いです。
免疫機能が低下し細菌感染による足先での炎症が起こり、細胞組織が死んでしまう壊疽に陥るケースもあります。
足の壊疽が進行すると下肢切断を余儀なくされる場合もあるため、糖尿病が進行して足先の感覚が衰えたと感じる場合は、清潔を保ち炎症の発生を防ぐ必要があります。
生命に危険がおよぶ脳梗塞
脳梗塞は脳卒中の種類の1つで、脳の血管が詰まる危険な病気です。
急に手足が麻痺したり言葉を発せなくなったりして、場合によっては命に関わる重篤な状態に陥ります。
脳の血管が完全に詰まる前に血流が悪くなった際は、頭の重量感や物忘れなどの症状が現れます。
違和感を覚えた場合は、早急に専門医に相談するのがよいでしょう。
脳梗塞は、治療が間に合って一命を取りとめたとしても、後遺症が残るケースが多いのも特徴です。
手足の麻痺や言語障害といった後遺症が多く、その後の生活に支障を来してしまいます。
脳梗塞は命に関わる危険な病気であるため、前兆を察知したら早めに検査を受けて対策を講じるのが大切です。
心臓の働きが低下する心筋梗塞
心筋梗塞は、心臓の働きが低下して起こる病気です。
冠状動脈が詰まって、心臓を動かしている心筋に血液が届かなくなり心臓が壊死してしまう病気で、激しい痛みを伴います。
突然痛みを伴って発症する急性心筋梗塞がほとんどで、命に関わる重篤な状態になるケースが多いです。
心筋梗塞が起こる原因として、動脈硬化が挙げられます。
血管が柔軟性を失って硬くなってしまう現象で、血流が悪くなる要因と考えられています。
動脈硬化は、糖尿病の人が陥りやすい症状です。
血糖値の高い状態が継続していると、血管の内壁が厚くなり、血流の悪化を招きます。
糖尿病に罹患している人は、心筋梗塞を発症しないように生活習慣の改善を意識する必要があります。
足の血管の動脈硬化による末梢動脈性疾患
末梢動脈性疾患は、足の血管に動脈硬化が起こって発症する病気です。
末梢動脈性疾患になると、足にしびれや痛みが起こり、生活に不自由を来すようになります。
症状が進行すると、足に潰瘍ができたり、足が壊死したりする要因になってしまいます。
場合によっては、下肢の切断を余儀なくされる可能性がある怖い病気です。
末梢動脈性疾患も、他の合併症と同様早期の対応が重要になります。
足のしびれを感じる場合は、糖尿病を疑って早めに医師の診断を受けるのがよいでしょう。
初期症状が見られない場合も多いのが糖尿病の特徴であるため、少しの異変にも敏感になって対処する必要があります。
ふくらはぎのつりを予防する効果がある対策を知ろう

ふくらはぎがつると、しばらく強い痛みを伴います。
頻繁につる場合は、前述のとおり糖尿病に罹患している可能性もあるため、軽視できません。
ふくらはぎがつるのを予防するためには、以下のような対策を講じるとよいでしょう。
- 水分をこまめに補給する
- 身体を冷やさないように対策する
- 入浴時はじっくりと浴槽に浸かる
- ビタミンやミネラルを意識した食事を心がける
- 血糖値を適切に保つ
- 身体に合っている寝具を選ぶ
- 就寝前のストレッチを実施する
いずれも簡単に取り組める方法であるため、毎日の習慣にするなど積極的に実施してみてください。
水分をこまめに補給する
ふくらはぎのつりを予防するために、水分のこまめな補給は効果があります。
足のつりは、体内の水分量とミネラル量が影響していると考えられています。
汗をかいて水分やミネラルが失われると、ふくらはぎがつる可能性が高くなってしまうでしょう。
運動をして汗をかいた後や、就寝前にはしっかりと水分補給をすると足のつりの予防になります。
水のみでなく、スポーツドリンクといったミネラル成分を豊富に含んでいる飲料を選ぶのも適しています。
のどが渇いてから水分を摂取するのではなく、のどの渇きを感じる前にこまめに摂取するのが理想的です。
こまめな水分摂取は、足のつり予防以外にも様々な健康効果が期待できるため、ぜひ積極的に取り組んでみてください。
身体を冷やさないように対策する
身体を冷やさないように、十分な対策を取るのも、ふくらはぎがつる予防になります。
身体が冷えてしまうと、筋肉の収縮が促進されて足のつりを引き起こすリスクが上がります。
冬場の寒い時期に身体を冷やさないようにするのはもちろん、夏場でも対策が必要です。
室内で冷房を強くし過ぎると、身体を冷やしてしまう原因になります。
特に就寝時には、身体が冷えすぎないように空調温度を適切に保つ必要があります。
就寝中に汗をかいて身体の冷えを誘発しないよう、綿素材などの吸水性の高い服装で寝るのも効果的です。
身体の冷えへの対策を十分に取って、ふくらはぎのつりを予防しましょう。
入浴時はじっくりと浴槽に浸かる

入浴時はシャワーで済ませるのではなく、じっくりと浴槽に浸かるとふくらはぎがつる予防になります。
季節を問わず、浴槽にお湯を溜めてゆっくり温まる習慣を持つと効果的です。
血行が良くなると足のつりの予防につながるため、毎日の習慣にするとよいでしょう。
入浴後は、汗をかいて水分が失われている場合が多いため、水分摂取も心がけた方がよいです。
忙しくてなかなか時間が確保できない人も多いかもしれませんが、時間を工面して可能な限り浴槽につかる習慣を取り入れてみてください。
ビタミンやミネラルを意識した食事を心がける
普段の食生活において、ビタミンやミネラルを豊富に含んだ献立を意識すると、ふくらはぎがつる予防になります。
特に、筋肉の動きに強く関連しているマグネシウムやカルシウムを豊富に摂取すると効果的です。
さらに、疲労回復効果があるタウリンやビタミンB1、クエン酸といった成分を含んでいる食材を積極的に取り入れるとよいでしょう。
身体の冷えを予防するため、温かい献立を用意するのも効果的です。
特に夏場は食欲が出ないからといって、そうめんや冷麺といった冷たい食べ物を多く食べる人もいるかもしれません。
身体の冷えは筋肉を収縮させて足のつりを誘発してしまう恐れがあるため、冷たいものばかり選択するのは避けた方がよいです。
血糖値を適切に保つ
血糖値を適切に保つと、ふくらはぎのつりを予防できます。
すでに糖尿病と診断されている人は、治療に専念して血糖値が上がりすぎないようにしましょう。
糖尿病と診断された経験がない人でも、頻繁に足がつる場合は糖尿病に罹患している可能性もあります。
糖尿病は初期症状が出ないケースも多いため、気付いた時にはかなり症状が進行している場合も多いです。
ふくらはぎがつる回数が増えてきたと感じる場合は、早めに専門医に相談して糖尿病の検査を受けてみてください。
身体に合っている寝具を選ぶ
就寝中のふくらはぎのつりを予防するには、身体に合っている寝具を選ぶのも有効です。
身体の冷えを防止するための温かい寝具や、硬さと形状が合っているものを選ぶ必要があります。
特にマットレスは硬すぎず柔らかすぎず、身体に余分な負荷をかけないものを選ぶのが大切です。
ずっと同じ姿勢で横になっていると、血行が悪くなり足がつる要因になります。
寝返りを自然に打てるような、適切な硬さのマットレスを選んで利用しましょう。
自分に合っている寝具がわからない場合は、専門医や寝具専門店などに相談して決める方法もあります。
就寝前のストレッチを実施する
就寝前にストレッチを定期的に行うと、寝ている間に足がつる予防になります。
就寝中のふくらはぎのつりは、血行の悪化によって引き起こされるケースが多いです。
寝る前にストレッチを行い血行を改善しておくと、予防効果が期待できます。
ふくらはぎや太もも、足の裏を、軽く伸ばすストレッチを行うとよいでしょう。
腰からの神経症状によって足がつっている可能性もあるため、腰や骨盤周りの筋肉を伸ばす腰痛体操なども効果があります。
ふくらはぎがつる原因として、筋力や持久力の低下も挙げられるため、柔軟性のみでなく普段からウォーキングなどをして筋肉維持に努めるのも大切です。
ストレッチと適度な運動を継続して行うと、ふくらはぎがつる予防になり、質の高い睡眠にもつながります。
ふくらはぎがつってしまった時の対処方法について理解しよう

以上で紹介した対策を十分に取っていたとしても、ふくらはぎがつる可能性はあります。
ふくらはぎがつると、強い痛みを伴って足を動かすのが難しくなります。
ふくらはぎがつった時の対処では、痛みの箇所を揉む人が多いのではないでしょうか。
ふくらはぎがつってしまった時の正しい対処方法を以下に3つ紹介します。
- ふくらはぎの筋肉をストレッチで伸ばす
- 電解質を含む水分を補給する
- 痛みが強く治らない場合は市販薬の利用も検討する
ふくらはぎがつってしまった時にも慌てず対処できるように、あらかじめ正しい対処方法を理解しておきましょう。
ふくらはぎの筋肉をストレッチで伸ばす
ふくらはぎがつってしまった場合は、ふくらはぎの筋肉をゆっくりと伸ばして、血行をよくすると症状が改善します。
足がつって痛みが出た場合、しばらく我慢して痛みが落ち着いてからつった方の足をゆっくりと伸ばします。
ふくらはぎの筋肉を伸ばすには、床に座って足を前に伸ばし、上に向けたつま先を手でつかんで手前に引くと効果的です。
一気に強くストレッチをすると、かえって痛みが増してしまう場合もあります。
筋肉を伸ばす際は、慎重にゆっくりと取り組むのが基本です。
ふくらはぎがつってしまった場合は、激しい痛みに焦ってしまうかもしれませんが、落ち着いてゆったりとストレッチをして痛みを和らげていきましょう。
電解質を含む水分を補給する
ふくらはぎがつって痛みが治まった後も、油断していると再発する可能性があります。
再発を防止するためには、ミネラル成分などの電解質を含む水分を摂取すると効果的です。
体内で水分が不足すると、足のつりが起こる可能性が高くなります。
寝る前に水分補給をしておくと、足のつりの再発を防止できます。
失われた電解質を効率よく補えるため、ふくらはぎがつるリスクを軽減できます。
水分補給は、ふくらはぎがつった後のみでなく、普段から積極的に取り組んでおくと予防効果が得られます。
痛みが強く治らない場合は市販薬の利用も検討する
ふくらはぎがつった際に、痛みが強くなかなか収まらない場合は、市販薬を利用した症状の緩和が可能です。
ふくらはぎがつる頻度が多くなってきたと感じる場合は、あらかじめ市販薬を常備しておくといざという時すぐに使えます。
市販薬の利用に際しては、事前に専門医や薬剤師に相談しておくとよいです。
しかし、市販薬を過信して医療機関に相談に行かないのは適切な対応ではありません。
市販薬はあくまで一時的に痛みを緩和するものであると理解して、医療機関で糖尿病を含めた診断を受けるとよいでしょう。
糖尿病以外でもふくらはぎがつる要因がある

糖尿病以外にも、ふくらはぎが頻繁につる要因があります。
足がつる現象は、健康でも起こりうる症状です。
発生の頻度が多い場合は、糖尿病を含めその原因を確認し、身体の異常に対して早期に対応できるようにするとよいでしょう。
糖尿病以外のふくらはぎがつる要因のうち、主なものを以下に8件紹介します。
- 夜間における身体の冷えや脱水
- 過度な運動による筋肉への負荷
- 熱中症をきっかけとした電解質の減少
- 腎不全治療で透析を行っている最中
- 心不全による体内の水分バランスの乱れ
- 睡眠時無呼吸症候群による疲れと睡眠不足
- 甲状腺の機能異常を起因とした血流悪化
- 薬物性の神経系異常が原因になる場合も
ふくらはぎがつる頻度が多い場合に、原因を解明する参考にしてください。
夜間における身体の冷えや脱水
健康な人でも、夜間における体の冷えや脱水状態により、ふくらはぎがつるリスクが高くなります。
冬場の寒い時期に手足が冷えた状態で就寝すると、血行が悪化して足がつる場合が多いです。
夏場においても、就寝中にかいた汗が冷房などで冷えてしまうと、体温が奪われてしまい身体が冷えてしまいます。
汗をかいて水分が減少すると、体内の電解質のバランスが悪くなり足がつるリスクを高めてしまいます。
就寝前にはコップ1杯程度の水を飲む習慣を作るとともに、室内温度を適切に保って冷えを防ぎ、汗をかきすぎないように取り組みましょう。
過度な運動による筋肉への負荷
過度な運動により、足の筋肉に普段よりも強い負荷がかかった場合、ふくらはぎのつりが起こってしまう場合が多いです。
普段運動をしない人がいきなり運動をする場合はもちろん、普段から適度な運動をしている人でも急激に運動量を増やすと、筋肉に過度な負荷がかかってしまいます。
普段よりも激しい運動をする場合は、ウォーミングアップを行って筋肉に過度な負荷をかけないように心がける必要があります。
普段の運動量を考慮し、無理な運動をしないようにするのも、足のつりを起こさないために重要です。
運動をする際には、水分補給をしっかりと行うと、ふくらはぎのつりを予防する効果があります。
熱中症をきっかけとした電解質の減少
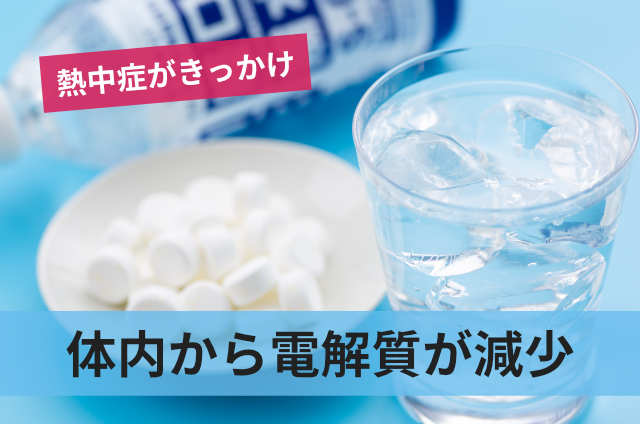
熱中症になった場合、体内から電解質が減少し、ふくらはぎがつる場合が多いです。
熱中症になって多くの汗をかくと、水分とともに電解質が体内から失われていきます。
電解質のバランスが悪くなると、足のつりが起こるリスクが高くなります。
のどが渇いてから水分を摂取するよりも、のどが渇く前に早めに水分摂取を心がけると熱中症予防につながります。
熱中症はふくらはぎのつりの原因のみでなく、命に関わる危険な状態になる場合もあるため、十分予防に努めましょう。
腎不全治療で透析を行っている最中
腎不全治療で透析治療を行っている最中は、ふくらはぎのつりが頻繁に起こります。
除水により体内の水分が失われて、足のつりが起こる場合が多いです。
体内の水分量低下による血圧の低下も、ふくらはぎのつりが起こる要因となります。
透析中に足がつった場合は、スタッフに伝えて対処してもらうとよいでしょう。
透析治療を行っていると、治療の途中以外でも足のつりが多く見られます。
毎日のストレッチを行って良好な血行を維持するなど、できる限りの対策を講じるのが大切です。
心不全による体内の水分バランスの乱れ
心不全になっている人は、体内の水分バランスが乱れて、ふくらはぎがつるケースが多くなります。
身体の血流が悪くなると、足の末端に十分な血液が行かなくなり、むくみやけいれんの原因になります。
高齢者になると体力が低下するのが当たり前と思い、初期症状に気付けない人も多くいます。
心不全は命に関わる場合も多いため、早期に治療を開始して対策を講じる必要があります。
睡眠時無呼吸症候群による疲れと睡眠不足

睡眠中に呼吸が何度も止まる睡眠時無呼吸症候群になると、ふくらはぎがつる回数が増えると考えられています。
睡眠時無呼吸症候群になると、良質な睡眠の確保が難しくなり、疲れと睡眠不足による筋けいれんが起こるリスクが増えます。
睡眠時無呼吸症候群は、肥満体型の人が陥る病気であると考える人も多いかもしれません。
しかし、痩せている人でも扁桃腺が大きかったり下あごが小さかったりすると、気道が狭くなって睡眠時無呼吸症候群になるケースも多いです。
睡眠時無呼吸症候群は自分で気付くのが難しい場合も多いため、家族からいびきの大きさを指摘されるようになった際は、検査を受けてみるとよいでしょう。
甲状腺の機能異常を起因とした血流悪化
甲状腺の機能異常を起因として、ふくらはぎのつる回数が増える場合もあります。
甲状腺に異常が起こり、ホルモンの分泌量が減少すると、血液の流れが悪化します。
血流不足により足の筋肉にけいれんが起こるリスクが増え、つりの原因になる場合が多いです。
さらに、血流悪化によって足の筋力が低下して、足がつる回数が増える側面もあります。
甲状腺異常は、気付かずに放置している人が多いのが現状です。
疲労感の増加やむくみなど、体調不良により起こる症状と似ているのが初期症状であるため、甲状腺異常と判断するのは難しいといえます。
ふくらはぎのつる回数が増えたと感じる場合には、糖尿病に加えて甲状腺異常についても調査を受けるとよいでしょう。
薬物性の神経系異常が原因になる場合も
薬物性の神経系異常が原因となり、ふくらはぎがつる場合もあります。
以下のような治療薬の服用が原因で、足の筋肉にけいれんが起こり、つる回数が増えると考えられています。
- 不整脈薬
- 利尿薬
- 脂質異常症
すでに患っている病気の治療や症状の緩和を目的として服用している薬であるため、足のつりの解消を目的に、服用を中止したり服用量を減らしたりするのは危険です。
病気の悪化を招いてしまう可能性があるため、必ず主治医に相談のうえで対応しましょう。
ふくらはぎがつる要因は糖尿病以外にも様々な場合が考えられるため、安易に判断せずあらゆる可能性を考慮して対応する必要があります。
ふくらはぎがつる要因としての糖尿病を理解しておこう

ふくらはぎがつる要因としては、糖尿病に罹患している可能性があります。
糖尿病の症状である血流悪化や神経障害および水分不足などが原因で、ふくらはぎが頻繁につっていると考えられます。
糖尿病は、疲労感の持続やのどの渇きおよび空腹感の継続といった症状が見られます。
さらに症状が進行すると、糖尿病網膜症や糖尿病腎症といった、重篤な合併症に発展するケースもあります。
ふくらはぎのつりを予防するためには、こまめに水分摂取する、身体を冷やさないようにするといった対策を講じると効果的です。
ふくらはぎがつってしまった場合は、ゆっくりと筋肉を伸ばしたり水分摂取を行ったりして状態の緩和を図ります。
ふくらはぎがつる要因としては、糖尿病以外にも様々なケースが考えられます。
つる回数が増えたと感じる場合は、糖尿病を含めさまざまな可能性を想定して、各種検査を受けてみてください。