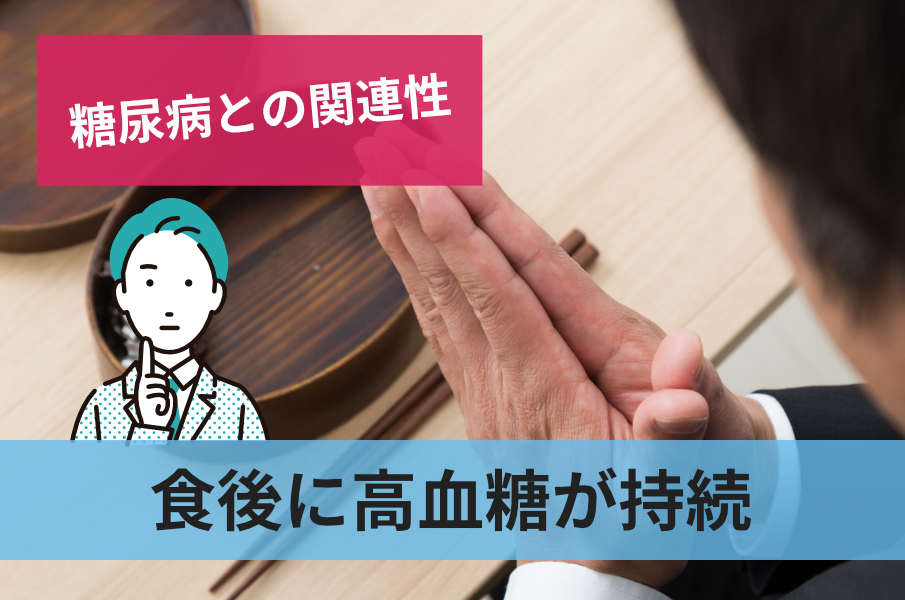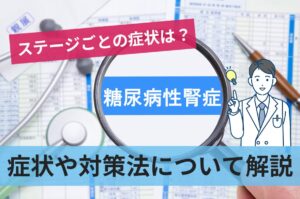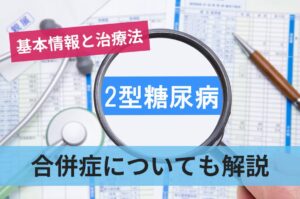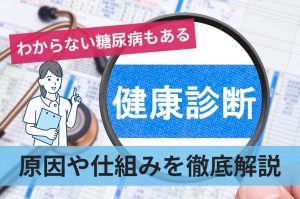食後の血糖値は健康的な人の場合、一旦上昇してから正常値に戻ります。
しかし、一部の人は食後の血糖値で高血糖が持続する場合があり、放置すると糖尿病の発症リスクが上がってしまいます。
この記事では、食後の血糖値について、糖尿病との関連性や高血糖を防ぐ対策などをまとめました。
- 血糖値が変動する仕組み
- 食後の血糖値で高血糖が持続する理由
- 食後の血糖値の上昇を抑える対策
糖尿病の検査で数値が高めだった人は、今後の運動や食事の方法を参考にしてください。
食事で糖分を摂取したときは血糖値が一時的に上昇してから元に戻る
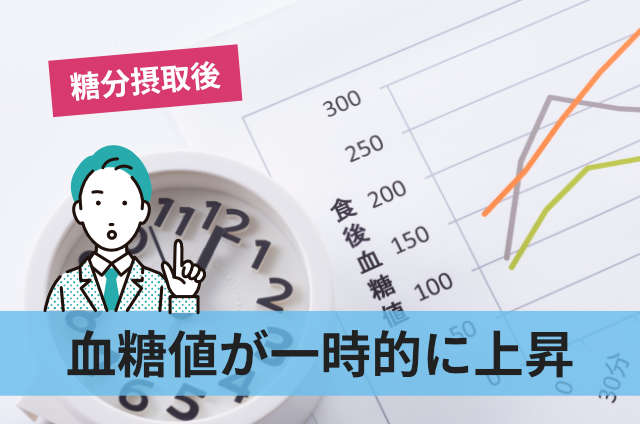
血糖値は血液に含まれるブドウ糖を示す数値であり、mg/dLの単位で表記されます。
しかし、インスリン分泌量の低下やインスリンに対する抵抗性が体内にできていた場合、血糖値は元の数値まで下げきれません。
血糖値が下がらない状態で再度糖分を摂取して血糖値が上昇すると、徐々に普段の血糖値は高くなっていきます。
血糖値が常に高血糖になってしまった場合、さまざまな不調や合併症を生じさせる糖尿病に移行する可能性があります。
糖尿病の検査では空腹時血糖値とヘモグロビンの糖分割合から判定する
高血糖から発症する糖尿病は、基本的に血液検査や尿検査から数値を見て、発症しているかを判断しています。
中でも血液検査では以下の数値から、糖尿病が進行する前の段階で発見できます。
- 空腹時血糖値:前日から10時間以上絶食して、採血した際の血糖値
- HbA1c(ヘモグロビンA1c):赤血球のヘモグロビンに含まれる糖分割合
採血時の数値の基準は、以下のとおりです。
| 正常値 | 正常高値 | 境界型 | 糖尿病型 | |
|---|---|---|---|---|
| 空腹時血糖値 | ~99mg/dL | 100~109mg/dL | 110~125mg/dL | 126mg/dL~ |
| HbA1c | ~5.5% | 5.6~5.9% | 6.0~6.4% | 6.5%~ |
空腹時血糖値は検査した時点の数値を見ていて、体調によっては数値のぶれが出てくる場合があります。
そのため、検査前の2ヶ月間でヘモグロビンの糖分割合が増えたときは、検査時に判定できます。
空腹時血糖値やHbA1c以外にも糖尿病、及び糖尿病の合併症の症状が見られる場合は、数値と合わせて糖尿病と診断されます。
食後の血糖値は体質や生活習慣の乱れから高い数値が継続する人もいる
糖尿病の検査は複数の数値を見て判断しますが、それでも完璧に異常を見つけられるわけではありません。
普段の血糖値は健康的な人と同じでも、食後の血糖値のみが正常値を大きく超えてしまう人もいます。
食後高血糖と呼ばれる状態であり、糖尿病の検査で発見するのが難しい点から隠れ糖尿病と言われる場合があります。
食後高血糖になってしまう原因は、以下のとおりです。
- 生まれつきの体質や糖尿病患者からの遺伝でインスリンの分泌が遅い
- 生活習慣の乱れでインスリンに対する抵抗性があり、血糖値を下げるのが遅い
インスリンの分泌はできているため、健康的な人よりも時間をかけて血糖値は正常値の範囲内に戻されます。
しかし、食後高血糖を放置すると徐々に普段の血糖値が上がって、糖尿病につながってしまいます。
糖尿病の検査におけるHbA1cや尿検査の結果から食後高血糖の疑いが出る
食後の血糖値は糖分を摂取した状態でなければ見られないため、糖尿病の検査で参照する空腹時血糖値では判定できません。
しかし、ほかの検査項目で異常が見られた場合、食後高血糖の疑いが出てきます。
- HbA1c:正常高値以上の数値の場合、検査前の2ヶ月間で血糖値が高い時期がある
- 尿検査:尿中に糖分量が多い場合、高血糖の可能性がある
上記に加えて空腹時血糖値の数値が高めの場合、食後高血糖で普段の血糖値が上がり始めている可能性もあります。
詳しい検査を勧めるか否かは病院や医師の判断によりますが、勧められたときはなるべく受診しましょう。
食後高血糖を早期に発見できた場合、糖尿病への移行を防げます。
食後の血糖値は経口ブドウ糖負荷試験で血糖値の変動から状態を把握する

食後の血糖値で正確な数値を見るには、通常の検査ではなく、経口ブドウ糖負荷試験による検査が必要です。
経口ブドウ糖負荷試験では、以下の流れで検査を行います。
- 採血する前に75gのブドウ糖を摂取する
- 摂取後から30分・60分・90分・120分に採血する
- 数回の採血で血糖値の上下を見て判定する
採血時の数値の基準は、以下のとおりです。
| 正常型 | 境界型 | 糖尿病型 | |
|---|---|---|---|
| 経口ブドウ糖負荷試験(OGTT) | ~139mg/dL | 140~199mg/dL | 200mg/dL~ |
インスリンが正常に機能している場合は、120分後の採血までに140mg/d未満の数値になります。
採血の途中で200mg/dLを超える大きな数値になる場合は、最終的に正常型の範囲に収まっても血糖値の変動としては異常です。
食後の血糖値を上げ過ぎないように運動や食事内容を改善する
食後高血糖と判明した場合、基本的には運動療法と食事療法により改善を目指していきます。
運動療法と食事療法は糖尿病治療に使われていて、主に以下の効果を取り入れるため、運動や食事の内容を変えていきます。
- 脂質制限や運動によるエネルギー消費で、インスリンの働きを弱める肥満を対策
- 運動によるホルモンの活性化で、インスリンの働きを高める
- 糖質制限や積極的な食物繊維の摂取で、血糖値の上昇を緩やかにする
運動や食事内容の改善は、通常の高血糖対策としても有効な手段です。
食後高血糖と判定されていない人も、健康を維持するために取り入れてみてください。
運動療法では自分ができる範囲で有酸素運動や筋肉トレーニングを継続させる
運動療法では毎日食後30分から2時間の間に、有酸素運動や筋肉トレーニングを行うのが推奨されています。
食事で摂取した栄養素は、当日に消費しなければ体内に貯蓄されて、血糖値の上昇や中性脂肪につながる可能性があります。
そのため、運動量や時間以上に、毎日継続して運動するのが重要です。
毎日の運動を前提にしたうえで、1日あたりの運動量は有酸素運動であるウォーキングを15分程度行うのが基準になります。
食後に15分以上の時間を取るのが難しい場合は、2〜5分程度の運動を複数回やるのも有効です。
細切れの運動でも、毎日継続している場合は、運動していない人よりも確実にエネルギー消費量は高まります。
食事療法では食物繊維の摂取量を増やしながら糖質や脂質が少ない食品を選ぶ

食事療法では食物繊維を優先的に摂取しながら、糖質や脂質の摂取量を調整していくのが推奨されています。
特に食物繊維は食事の最初に食べておいた場合、以下の効果が発揮されます。
- 血糖値の上昇を緩やかにする効果で、後から摂取した糖質で血糖値を上げ過ぎない
- 胃の中で膨れる性質から、後からほかの食品を食べ過ぎない
食べ過ぎの防止は糖質や脂質の過剰摂取の防止にもなるため、食物繊維は血糖値の上昇対策として有用な食材です。
主に野菜やキノコ類、海藻に多く含まれているため、副菜として毎食の一品に加えてみましょう。
糖質や脂質の調整については、以下のような食品の置き換えから摂取量を減らせます。
| 置き換え前の食品 | 置き換える食品 |
|---|---|
| 精白米(糖質) | 雑穀米 |
| 小麦粉パン(糖質) | 全粒粉パン |
| 脂身が多い肉(脂質) | 脂身が少ない部位の肉魚 |
身体に必要な栄養素であるため、一切摂取しないのではなく、適量を摂取できるように食品を選んでください。
運動や食事で改善が見込めない場合には薬物療法が検討される
運動や食事内容を改善しても、体質や糖尿病の進行度から思うように血糖値を下げられない人もいます。
数ヶ月間の実施で改善が見込めない場合は、薬物療法による血糖値のコントロールが候補にあがってきます。
薬物療法ではインスリン分泌促進薬や糖分の分解を抑制させる薬を服用しますが、食事や運動による改善を止めるわけではありません。
運動や食事でも引き続き血糖値を上げ過ぎないようにして、薬の効果を補助的に使っていきます。
血糖値に関連する薬には副作用があり、効果が効き過ぎると低血糖を引き起こす人もいます。
薬を処方されたときは、医師の指示に従って適切な量や時間帯の摂取を心がけましょう。
食後の血糖値が高い人も食事や運動で対策して糖尿病を防げる
食後の血糖値は体質や生活習慣の乱れから、高血糖が持続してしまう人がいます。
時間をかけた場合は正常値に戻せますが、放置すると普段の血糖値に影響が出て糖尿病につながる可能性も高い状態です。
糖尿病の検査で食後高血糖の疑いが出て、経口ブドウ糖負荷試験を勧められたときは、検査を受けて早めに症状を判定してもらいましょう。
食後高血糖の状態でも、毎日の有酸素運動や食物繊維を多く摂取する食事から、血糖値の上昇を抑えられます。
食後の血糖値が問題ない人も、食事や運動の改善から血糖値を正常に保って健康的に過ごせるため、実践してみてください。