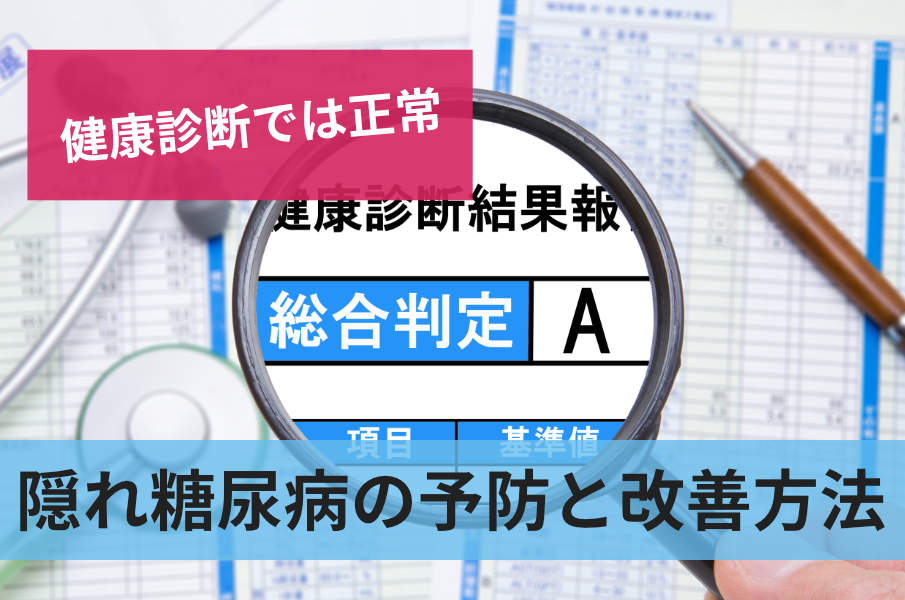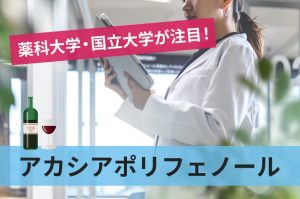健康診断を受けて、空腹時血糖値やヘモグロビンA1cが正常で安心していませんか。
通常の健康診断では、空腹時の血糖値やヘモグロビン1cを測定する場合がほとんどです。
しかし近年、空腹時血糖値やヘモグロビンA1cが正常でも食後2時間後の血糖値が高い隠れ糖尿病が問題視されています。
食後2時間後の血糖値の改善には、空腹時血糖値の改善と同様の方法が推奨されています。
今回は、隠れ糖尿病を改善するための方法についてまとめました。
- 糖尿病という病気について
- 糖尿病の合併症
- 糖尿病の診断基準
- 血糖値変動のメカニズム
- 血糖値改善のための運動療法
- 血糖値改善のための食事療法
この記事を読み、糖尿病および隠れ糖尿病の予防や改善方法への理解を深めましょう。
糖尿病は血中の糖が増えてしまう病気

糖尿病とは、インスリンが十分に機能しないために、血中の糖が通常よりも増えてしまう病気のことです。
日本生活習慣病予防協会による糖尿病に関する報告を、以下にまとめました。
- 日本では、糖尿病患者は年々増加しており、治療を受けている患者数は2020年時点で579万人に及ぶ。
- 糖尿病による年間死亡者数は、約1万6000人いる。
- 糖尿病が強く疑われる者の割合は、男性16.8%、女性8.9%である。
- 糖尿病の年間医療費は、約1兆2000億円かかっている。
参照元:日本生活習慣病予防協会「糖尿病」
このように、糖尿病は身近な病気であり、社会的な問題にもなっています。
糖尿病は遺伝的要因と生活習慣要因により発症する
糖尿病の原因は、主に遺伝的要因と生活習慣要因の2つです。
遺伝的要因は、生まれつきインスリン分泌が少ない状態で、1型糖尿病と呼ばれています。
家族に糖尿病患者がいる場合には、糖尿病になる確率が高まるという報告もあります。
生活習慣要因の例は、以下のとおりです。
- 過食
- 運動不足
- 高カロリー食の摂取
- 高脂肪食の摂取
- アルコールの過剰摂取
このような生活習慣が原因で発症する糖尿病を、2型糖尿病と呼びます。
日本の2型糖尿病患者は、糖尿病患者全体の95%を占めています。
糖尿病のほとんどが生活習慣の乱れが原因であるため、予防が可能です。
糖尿病は様々な病気を合併する危険がある
糖尿病になり、高血糖状態が持続すると、血管や神経へのストレスが増加します。
この高血糖の持続が、合併症を引き起こします。
他にも、糖尿病であると脳血管疾患や心臓疾患のリスクも高まります。
以下は、糖尿病患者で合併症を罹患している人の割合です。
- 糖尿病網膜症13.1%
- 糖尿病腎症15.2%
- 糖尿病神経障害15.6%
引用元:糖尿病実態調査報告
合併症は、ゆっくりと進行し、失明や切断などの重篤な障害へ繋がる可能性もあります。
糖尿病の診断には4つの数値が用いられる
糖尿病の診断に用いる指標は、以下のとおりです。
- 空腹時血糖値
- 食後2時間血糖値
- 随時血糖値
- ヘモグロビンA1c(HbA1c)
それぞれの基準値を、表に示します。
| 正常値 | 正常高値 | 境界型 | 糖尿病型 | |
|---|---|---|---|---|
| 空腹時血糖値 | ~99 | ~109 | ~125 | 126~ |
| 食後2時間血糖値 | 〜139 | 〜199 | 200〜 | |
| 随時血糖値 | 200〜 | |||
| HbA1c | ~5.5 | ~5.9 | ~6.4 | 6.5~ |
空腹時血糖値や食後2時間血糖値、随時血糖値のいずれかが糖尿病型であると同時に、ヘモグロビンA1cが6.5%以上であると糖尿病と診断されます。
この表を参考に健康診断の結果をみて、それぞれの数値がどの状態なのか確認しましょう。
血糖値とは血中のブドウ糖の濃度のこと
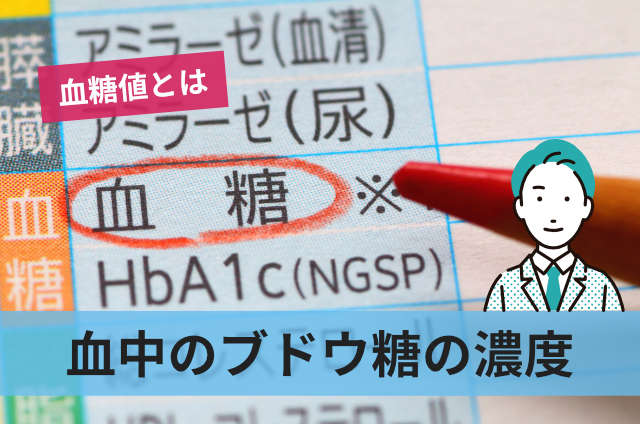
ここまでで、糖尿病には血糖値が深く関わっているとわかりました。
血糖コントロールが正常であれば、血糖値は一定の数値で維持されます。
しかし、食事や運動など日常生活で、血糖値は一時的に変動しています。
血糖値変動のメカニズムについて、確認していきましょう。
血糖値は誰しも上昇と下降を繰り返している
血糖値は、誰しも食事や運動などの日常生活の中で、上昇と下降を繰り返しています。
食事を摂取すると、血中のブドウ糖濃度が上昇し、血糖値も上昇します。
特に炭水化物には糖質が多く含まれているため、米やパンなどは血糖値を上昇させる食品です。
そこで、すい臓から分泌されるインスリンというホルモンが、血糖値の調整をします。
健康な人は血糖値が上昇すると、インスリンの分泌により、血糖値が下降します。
空腹時血糖値が正常でも食後2時間後の血糖値に注意する
前述したとおり、食後の血糖値はインスリンの効果によって、一度上昇しても正常値まで下降します。
正常値へ下降するまでにかかる時間は、およそ2時間とされています。
そのため、糖尿病の診断にも食後2時間後の血糖値を測定しなければなりません。
空腹時血糖値が正常範囲内であると、食後2時間後の血糖値を測定しない場合があります。
このような、食後血糖値だけが高値である状態を隠れ糖尿病と呼びます。
隠れ糖尿病は、気づかないうちに糖尿病が進行してしまうため、動脈硬化による合併症に注意が必要です。
隠れ糖尿病を早期に発見するためには、空腹時血糖値に加えて食後2時間後の血糖値も同時に測定する必要があります。
運動療法と食事療法の組み合わせで血糖値を改善する

糖尿病、隠れ糖尿病はどちらも血糖値を改善しなければなりません。
糖尿病ガイドラインで、血糖値の改善に推奨される方法は、運動療法と食事療法です。
運動と食事の組み合わせで血糖値を改善していきましょう。
血糖値の改善に効果的な運動は有酸素運動とレジスタンストレーニングである
血糖値改善のために推奨される運動療法として、有酸素運動やレジスタンストレーニングが挙げられます。
代表的な有酸素運動を、以下に示します。
- ウォーキング
- ジョギング
- ランニング
- サイクリング
- 水泳
- エアロビクスダンスエクササイズ
有酸素運動は週に3回以上、中等度の強度で実施し、運動をしない日が2日以上連続しない方法が推奨されています。
さらに、実施する運動強度が高いほど、血糖値の改善効果が期待できます。
レジスタンストレーニングは、ダンベルなどの器具を使用する方法と、スクワットや腕立て伏せなどの自分の体重(自重)を使用する2つの方法があります。
血糖値の改善に有効的なレジスタンストレーニングの具体的な方法は、以下のとおりです。
- 連続しない日程で週に2から3回行う。
- 上半身、下半身の筋肉を満遍なく含んだ5種類以上の運動を行う。
- 10回から15回繰り返せる負荷量を目安に始める。
- 最終的には、8回から12回で限界に達する負荷量で、1から3セット行う。
- 特に下半身の筋肉は全身の70%を占めているため、時間のない人には有効的である。
器具を使用する場合には、購入またはジムなどに通う必要があるため、費用をかけたくない人には注意が必要です。
運動習慣のあまりない人は、低負荷の運動から生活に取り入れて長期間継続していきましょう。
血糖値以外にも、運動療法によって下記の症状の改善が期待できます。
- 肥満
- 内臓脂肪の蓄積
- 脂質異常症
- 高血圧症
- 慢性炎症
- QOL(クオリティ・オブ・ライフ)
- うつ症状
- 認知機能障害
参照元:糖尿病ガイドライン 運動療法
血糖値は食後1時間経過時点でピークを迎えるため、血糖値が上昇し始める食後30分経過時点に有酸素運動を開始すると、血糖値上昇を抑制できます。
以上のように、運動には糖尿病の予防や改善以外にも様々な効果が期待できます。
自分のペースで、有酸素運動やレジスタンストレーニングを生活に取り入れてみてください。
血糖値の改善に推奨される3つの食事療法

血糖値改善のために推奨される食事療法は、主に3つあります。
1つ目に、過食や高カロリーな食事を制限する点が挙げられます。
特に2型糖尿病は体重の増加や肥満が原因であるため、エネルギーの制限は効果的です。
エネルギー摂取量を制限し、体重を5%以上減らすと、血糖コントロールが改善したという研究報告もあります。
自分の身長と体重から導き出される推奨エネルギー摂取量を参考にして、1日の摂取エネルギー量を減らすことが大切です。
2つ目は、炭水化物を制限した食事を心がけます。
炭水化物を制限すると、身体は体内の脂肪をエネルギー源とするため、肥満の改善に効果があります。
さらに、低炭水化物食を6ヶ月摂取すると、中性脂肪が目立って減少したと報告されています。
ただし炭水化物の制限に関して、短期的な血糖コントロールの改善はわかっていますが、長期的な効果についてはまだ報告されていません。
3つ目は、食物繊維の積極的な摂取です。
食物繊維には糖の吸収速度を遅くし、血糖値の急上昇を緩和する効果があります。
水溶性食物繊維の1日あたりの推奨摂取量は、7.6gから8.3gです。
参照元:糖尿病ガイドライン 食事療法
水溶性食物繊維を多く含む食品を、下記にまとめました。
- ライ麦粉
- オートミール
- 切り干し大根
- ごぼう
- 干しいちじく
- 干しプルーン
- インゲン豆
参照元:食品に含まれる食物繊維量一覧
食事メニューに、水溶性食物繊維を多く含む食材を取り入れてみてください。
食後高血糖を予防するための3つの注意点
前述したエネルギー摂取量の制限や食事メニューの変更を行っても、食後高血糖による隠れ糖尿病の危険性はあります。
食後高血糖を抑えるために、次の点に注意しましょう。
- 主食の前に野菜やたんぱく質を食べる。
- 食事は、ゆっくり食べる。
- 食事回数は1日3回として、欠食しない。
野菜に含まれる食物繊維が、食物の消化や吸収を緩やかにするため、食後血糖値の急上昇を防げます。
さらに、欠食せずに食事のリズムが整うと、食後の血糖値上昇も緩やかになります。
食事と血糖値は、密接に関わっており、糖尿病の予防や治療には食生活の改善は必要不可欠です。
自分の血糖コントロールを確認して糖尿病を予防しよう
近年、空腹時血糖値やHbA1cが正常な人でも食後2時間後の血糖値が高い隠れ糖尿病が問題視されています。
隠れ糖尿病は、気づかないうちに糖尿病が進行し、重篤な合併症に繋がる危険があります。
そのため、家族に糖尿病患者がいる場合や生活習慣の乱れが気になる人は、食後2時間後の血糖値も測定してみてください。
自分の血糖値の状態を知り、血糖値の改善に有効的な運動療法と食事療法を取り入れていきましょう。