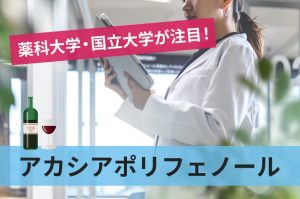大豆を原料とする豆乳は豊富なタンパク質や低カロリーが魅力であり、健康や美容の強い味方として人気の高い食品です。
近年では肉の代替食品として大豆ミートが注目され、大豆製品のダイエット効果にも期待が高まっています。
豆乳には血糖値を改善する働きがあり、糖尿病の発症リスクを下げる効果があるため、毎日の食事に取り入れて血糖値の改善に取り組みましょう。
この記事では、豆乳と血糖値の関係について詳しく解説します。
- 豆乳の健康効果と種類
- 豆乳が血糖値に与える影響
- 豆乳以外で血糖値を下げる方法
血糖値を下げる食事や運動の方法についても解説しているため、ぜひ参考にしてください。
豆乳は大豆からつくられる栄養豊富な飲料

豆乳は豆腐を作る過程で抽出される液体で、大豆を原料とします。
どれも栄養効果が高く、健康的な食材として人気があります。
豆乳は古くから存在していたものの、一般的に知られるようになったのは、市場に流通が始まった1970年代頃からです。
豆乳には独特の豆の臭いがあるため好みが分かれますが、近年は製造技術の向上によって臭いが気にならないものが増えています。
健康志向の高まりから、牛乳の代替品としての需要も上昇傾向です。
以下では、豆乳の栄養効果と種類について解説します。
豆乳に含まれる栄養素にはさまざまな健康効果が期待できる
畑の肉とも呼ばれる大豆を原料とする豆乳には、さまざまな栄養素が豊富に含まれています。
大豆に含まれる栄養素
| 植物性タンパク質 | 大豆に含まれる植物性タンパク質は、動物性に比べて低カロリーであり、吸収のスピードが遅いため満腹感を得られる。 筋肉の成長を助け、健康的な体づくりに役立つ。 タンパク質には基礎代謝を活発にする機能や、コレステロールを下げて全身の血流を改善する効果がある。 |
|---|---|
| 大豆イソフラボン | 女性ホルモンの一つであるエストロゲンと似た構造をもつ、ポリフェノールの一種。 加齢と共に減少するエストロゲンの代わりとなって、骨の健康を維持する効果が期待できる。 乳がんや前立腺がんの予防、更年期障害の改善や骨粗鬆症の予防にも効果がある。 |
| サポニン | マメ科の植物に多く含まれており、苦味や渋みの元となる成分。 肝臓機能や免疫力の向上、抗酸化作用があり、肥満の予防にも効果的。 |
| レシチン | リン脂質の一種であり、脳神経や神経組織を構成する細胞膜の主な成分。 アルツハイマー型認知症や動脈硬化の予防、肝機能を高める効果がある。 余分なコレステロールを血液中に排出させる機能があるため、血流が改善し、美肌効果にも期待ができる。 |
| カリウム | ミネラルの一種。 カリウムには余分なナトリウムを体外に排出して調整する機能があり、血圧を安定させる。 |
| マグネシウム | 必須ミネラルの一つで、骨や歯を形成する。 心臓や血管の働きを助け、筋肉の収縮や神経機能の維持にも不可欠。 |
| オリゴ糖 | 糖の一種。 腸内環境を改善する乳酸菌やビフィズス菌のエサになるため、免疫力の向上や便通をよくする働きがある。 |
豆乳の種類は主に3つで好みに合わせて飲み方が選べる

豆乳には主に3つの種類があり、大豆成分の割合によって以下に分類されています。
- 無調整豆乳:豆乳に水のみを加えたもの。大豆固形分8%以上で大豆タンパク質換算3.5%以上。
- 調製豆乳:豆乳に砂糖や塩、香料などを加えたもの。大豆固形分6%以上で大豆タンパク質換算2.8%以上。
- 豆乳飲料:調整豆乳に果汁やコーヒーなどを加えたもの。果汁入りは大豆固形分2%以上で大豆タンパク質換算0.9%以上、その他は大豆固形分4%以上で大豆タンパク質換算1.7%以上。
無調整豆乳は大豆と水のみを使用しているため、大豆独特の香りを強く感じます。
砂糖が不使用であるため、糖質を気にせずに飲めるのがメリットですが、強い大豆の香りに飲みづらさを感じる人も少なくありません。
無調整豆乳が苦手な場合は、調整豆乳や豆乳飲料を利用しましょう。
調整豆乳は、豆乳の豆の臭いが気にならないように甘さが加えられています。
豆乳飲料は果物やコーヒー、チョコレートなどのフレーバーが加えられているため、さらに飲みやすくなっています。
血糖値を下げるためには、糖質の入っていない無調整豆乳が効果的です。
豆乳の栄養素には血糖値を下げる効果がある
豆乳に含まれる栄養素には血糖値を下げる効果をもつものがあり、糖尿病の予防や改善に有効です。
糖尿病はインスリン機能の低下によって、慢性的に血糖値を下げられなくなります。
原因は遺伝や肥満、過度な飲酒や喫煙などがあげられ、生活習慣病とも呼ばれています。
栄養豊富な豆乳を毎日の食事に上手に取り入れ、血糖コントロールを行いましょう。
以下では、豆乳が血糖値に与える影響について解説します。
大豆イソフラボンがインスリンの働きを促進する
豆乳の栄養素である大豆イソフラボンには、インスリンの働きを促進し血糖値を下げる効果があります。
膵臓のランゲルハンス島から分泌されるインスリンは、人の体で血糖値を下げられる唯一のホルモンです。
さらに余分なブドウ糖はグリコーゲンとして肝臓に貯蔵されたり、中性脂肪に合成されたりして血糖値を下げます。
豆乳にはこのインスリンの働きを高める作用があるため、高血糖の予防に効果的です。
植物性タンパク質が血糖値の上昇を緩やかにする

豆乳の植物性タンパク質は肉や魚、牛乳などの動物性タンパク質に比べて、体内における消化吸収のスピードが遅いのが特徴です。
そのため、食事の前に豆乳を飲むと食後の血糖値の上昇が穏やかになります。
血糖値は食事から摂取する炭水化物などの糖質によって上昇し、インスリンの分泌によって正常値に戻ります。
通常、食後の血糖値が正常値に戻るまでにかかる時間は2時間程です。
しかし、糖質の多い食事や脂っこい食事によって食後の血糖値の急上昇が繰り返されると、インスリンがうまく機能せず正常値に戻るまでに時間がかかります。
食事の30分前に豆乳を飲むと血糖値の上昇が穏やかになり、食後高血糖の急上昇の予防に効果的です。
食欲を抑える効果で肥満を予防する
植物性タンパク質には、食欲を抑え肥満を予防する効果があります。
植物性タンパク質は消化吸収のスピードが遅く、満腹感を感じる効果があるため、食事の量が抑えられ食べ過ぎの予防が可能です。
肥満は糖尿病の原因であり、内臓脂肪が増加すると膵臓が疲弊しインスリンの分泌機能が低下します。
暴飲暴食などの過食も、血糖値が下げられなくなる要因の一つです。
豆乳の効果によって暴飲暴食を防ぎ、食事の量をコントロールできるため、食後高血糖の予防になります。
食事の前にコップ1杯の豆乳を飲んで、食べ過ぎを予防しましょう。
血糖値を管理するためには生活習慣の改善も大切
血糖値を管理するためには、食事や運動などの生活習慣の改善が大切です。
生活習慣病とも呼ばれる糖尿病の発症には、日常の生活が密接に関わっています。
血糖値はストレスによっても上昇するため、ストレス解消のための暴飲暴食や喫煙なども糖尿病の発症リスクを高めます。
インスリンの分泌は加齢に伴って減少するため、糖尿病は中高年で発症率が高くなる病気です。
特に働き盛りの3、40代で発症するリスクが上昇するため、早めに生活習慣の改善に取り組みましょう。
以下では、血糖値を下げるための生活習慣の改善方法と、豆乳以外で血糖値を下げる食品について解説します。
血糖値の管理には食事による血糖コントロールが基本
安定した血糖値を維持するためには、食事による血糖コントロールが基本です。
炭水化物や糖分の多いお菓子などの甘い食べ物を大量に食べると、一気に血糖値が上昇し食後高血糖を起こします。
1日1食などの不規則な食習慣も、空腹状態から食事を摂るため急激な血糖値の上昇を招く原因です。
血糖値は食事によって上昇するため、食事の摂り方に工夫をすると食後の血糖値の急上昇が予防できます。
以下は、血糖値を急上昇させない食事の摂り方のポイントです。
- 糖質や脂質の多い食事を避ける
- ゆっくりとよく噛んで食べる
- 1日3食を毎日同じ時間に食べる
- 野菜やきのこなどの食物繊維の豊富なものから食べる
- 栄養バランスの良い食事を摂る
- 過度な飲酒を避ける
運動には血糖値を下げる効果がある

運動には食事によって上がった血糖値を下げる効果があるため、血糖値の管理に重要な役割をもちます。
運動をすると、体内のブドウ糖をエネルギーとして消費し血糖値が下がります。
さらに、運動にはインスリンの効きを高める効果もあるため、生活のなかに少しでも運動を取り入れるようにすると効果的です。
血糖値を下げる運動のポイントは、以下の通りです。
- ウォーキングなどの有酸素運動を週3回以上行う
- 下半身の強化を中心として筋力トレーニングを行う
- 有酸素運動と並行して筋力トレーニングを行う
糖尿病の人は下半身の筋肉量の低下がみられるため、足を中心として下半身の筋力をつけるトレーニングを行いましょう。
血糖コントロールに役立つ豆乳以外の食品もある
豆乳以外で血糖値を下げるために効果的な食品は、食物繊維を多く含む食品です。
食物繊維には、食後の血糖値の急上昇を予防する効果があります。
食物繊維が豊富な食品には噛みごたえのある食品が多く、よく噛んでゆっくりと食事ができるため、食べ過ぎの予防にも効果的です。
血糖値の上昇を抑えるためには食物繊維の豊富な食品から先に食べ始めると、その後に食べる糖質の吸収を緩やかにします。
食物繊維の豊富な食品
| 野菜 | 春菊、あしたば、カボチャ |
|---|---|
| 芋類 | さつまいも、里いも |
| 果物 | キウイ、みかん、もも、干しぶどう |
| 海藻類 | わかめ、昆布、寒天、ひじき、のり、もずく |
| 豆類 | あずき |
| その他 | こんにゃく、納豆、大麦、オーツ麦 |
豆乳の豊富な栄養素が血糖値を下げ糖尿病を予防する
豆乳は大豆を原料とする飲料であり、大豆イソフラボンや植物性タンパク質など豊富な栄養素には血糖値を下げる効果があります。
豆乳は肉や魚、牛乳などの動物性タンパク質に比べて低カロリーであるため、ダイエットにも効果的です。
大豆イソフラボンにはインスリンの機能を促進し、血糖値を下げる効果があります。
植物性タンパク質は動物性タンパク質と比較して消化吸収が遅く、血糖値を穏やかに上昇させるため、食後高血糖の予防が可能です。
食事の30分前に豆乳を飲むと、その後の食事による血糖値の急上昇を防ぐ効果があります。
大豆には食欲を抑える効果があるため、糖尿病の発症原因の一つである肥満の予防にも効果的です。
豆乳の効果をより高めるためには、生活習慣の改善に取り組む必要があります。
安定した血糖値の管理には、食事と運動による血糖コントロールが大切です。
食事では血糖値を上げないように食べ方を工夫をすると、食後高血糖の予防ができます。
運動では有酸素運動と筋力トレーニングの両方を取り入れると、血糖値を下げる効果が得られます。
豆乳以外で血糖値を下げる効果がある食品は、食物繊維を多く含む食品です。
特に水溶性食物繊維を多く含む食品は胃腸で消化吸収されるスピードが遅く、糖質をゆっくり吸収するため血糖値の急上昇が防げます。
毎日の食生活に豆乳を利用しながら生活習慣の改善に取り組み、血糖値をコントロールしましょう。