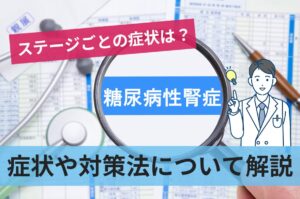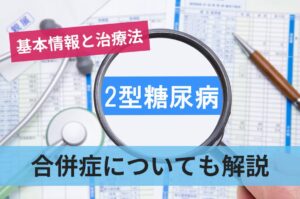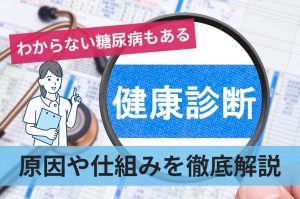さつまいもは糖質が多く、糖尿病や血糖値が気になる人の中には避けている人もいるでしょう。
しかし、さつまいもには体に良い成分が多く含まれており、血糖値コントロールにも役立ちます。
今回はさつまいもに含まれている栄養素と効果、血糖値を上げない食べ方についてまとめました。
- さつまいもは糖尿病患者に適した食品
- さつまいもに含まれている栄養素と効果
- 血糖値を上げないさつまいもの食べ方
さつまいもが血糖値に与える影響が気になる人や食べ方を知りたい人は、ぜひ参考にしてください。
さつまいもは糖尿病や血糖値が気になる人に適した食品である

さつまいもには糖質が多く含まれていますが、適量であれば糖尿病や血糖値が気になる人に適した食品です。
血糖値が急上昇するのを防ぎ、体内のコレステロールやナトリウムを排出する効果が期待できます。
血糖値の上昇速度を示す指標として、参考になるのがGI値です。
食品は、GI値によって以下のように分類されます。
| GI値 | 分類 |
|---|---|
| 55以下 | 低GI食品 |
| 56以上69以下 | 中GI食品 |
| 70以上 | 高GI食品 |
ブドウ糖を摂取した場合のGI値を100とし、GI値が高い食品ほど血糖値が急激に上昇します。
食後の血糖値がおだやかに上がるため、血糖値コントロールに役立ちます。
さらにさつまいもには、コレステロール値や血圧を下げる効果もあります。
糖尿病は生活習慣病の一種であり、糖尿病患者のうち95%以上は2型糖尿病です。
発症には遺伝的な要因のほかに、食べ過ぎや運動不足などの生活習慣が関係しています。
高血圧や脂質異常症なども生活習慣の要因が大きく、互いに関連し合っています。
そのため、糖尿病患者は他の生活習慣病を合併している人が多いのが現状です。
複数の生活習慣病は動脈硬化を進行させ、命に関わる病気を引き起こす恐れがあります。
さつまいもが持つ効能は糖尿病に良い影響を与え、生活習慣病の合併を予防するのに効果的です。
これらの健康効果は、さつまいもに含まれている成分が関係しています。
さつまいもには糖尿病に良い影響を与える成分が含まれている
さつまいもには、糖尿病に良い影響を与える以下の成分が含まれています。
- 食物繊維
- ヤラピン
- ビタミンB群
- カリウム
さつまいもは栄養素が豊富に含まれており、準完全食に分類されています。
厚生労働省が定める日本人の食事摂取基準に基づき、健康を維持するのに必要な栄養素を全て含む食品を完全食といいます。
単品ではたんぱく質や脂質が不足するため、別の食材で補うと栄養バランスが整います。
さつまいもには糖尿病患者が積極的に摂取したい成分が多く含まれており、さまざまな健康効果が期待できるでしょう。
ここでは、さつまいもの成分がもたらす健康効果について解説します。
血糖値の急上昇を防いで便通を促す食物繊維が豊富に含まれている

さつまいもには血糖値の急上昇を防ぐ水溶性食物繊維と、便通を促す不溶性食物繊維が豊富に含まれています。
食物繊維には2種類あり、それぞれの特徴と働きは以下のとおりです。
| 種類 | 特徴 | 働き |
|---|---|---|
| 水溶性食物繊維 | 水に溶けてゼリー状になる | ・血糖値の上昇を抑える ・ナトリウムやコレステロールを排出する ・便をやわらかくする |
| 不溶性食物繊維 | 水にほとんど溶けない | ・便の量を増やす ・便をやわらかくする |
水溶性食物繊維は糖質を包み込んでゆっくりと移動し、糖質の吸収速度を遅らせる働きがあります。
血糖値の急上昇を抑えられるため、血糖値コントロールに効果的です。
糖尿病の治療において血糖値コントロールは合併症を防ぎ、健康な人と変わらない生活を維持するのに役立ちます。
ナトリウムやコレステロールを排出する働きもあり、血圧やコレステロール値を下げる効果が期待できるでしょう。
糖尿病患者は、健康な人よりも高血圧や脂質異常症のリスクが高まります。
生活習慣病の合併は命に関わる病気につながるため、水溶性食物繊維の働きが役に立ちます。
一方、不溶性食物繊維は便通を促進し、便秘の予防や解消に有効です。
便秘により代謝が悪くなり、体重の増加や肥満につながる恐れがあります。
糖尿病の治療は食事と運動が基本となり、体重や摂取カロリーのコントロールが必要です。
食物繊維を多く含む食品は食べ応えが感じられ、食べ過ぎも予防できます。
腸内環境を整えるためには、両方の食物繊維をバランス良く摂取するのが大切です。
水溶性食物繊維と不溶性食物繊維はどちらも整腸作用があり、それぞれ働きが異なります。
さつまいもには、食物繊維以外にも整腸作用のある成分が含まれています。
さつまいも特有の成分であるヤラピンには整腸作用がある
さつまいも特有の成分であるヤラピンには整腸作用があり、便秘の予防や解消に効果があります。
ヤラピンはさつまいもの樹脂成分で、皮に近い部分からにじみ出る白い液体の中に含まれています。
一般的にヒルガオ科の植物が持つ成分ですが、食品の中で含まれているのはさつまいものみです。
ヤラピンは腸のぜん動運動を活発にし、便をやわらかくして排便を促す働きがあります。
ポリフェノールと結合すると黒ずむ性質があり、さつまいもの皮に見られる黒い部分はヤラピンがにじみ出て変色したものです。
皮の表面に傷があると、変色が起こる可能性が高くなります。
加熱しても作用が失われないため、調理方法を選びません。
ただし皮付近に多く含まれているため、効率的に摂取するにはさつまいもを皮ごと食べるのがおすすめです。
食物繊維とヤラピンの相乗効果により、強い整腸作用が期待できるでしょう。
ビタミンB群には糖質のエネルギー代謝を助ける働きがある
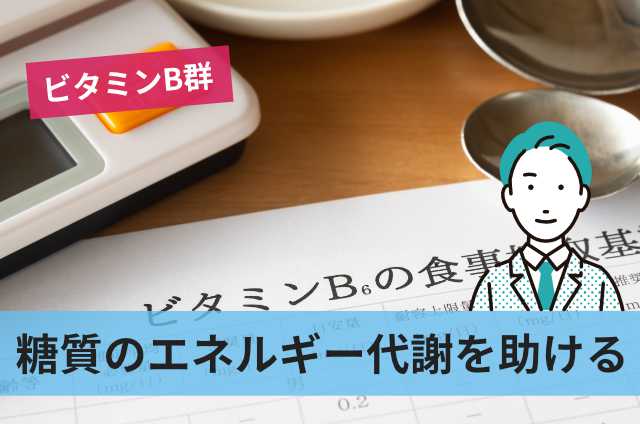
ビタミンB群は糖質やたんぱく質がエネルギーに変わる際に必要な栄養素で、糖質のエネルギー代謝を助ける働きがあります。
ビタミンB群は、以下の水溶性ビタミンの総称を表します。
- ビタミンB1
- ビタミンB2
- ビタミンB6
- ビタミンB12
- ナイアシン
- パントテン酸
- 葉酸
- ビオチン
さつまいもにはこれらのビタミンのうち、ビタミンB12以外が含まれています。
ビタミンB群はお互いに助け合いながら力を発揮するため、さつまいもはビタミンB群を効率的に摂取できる食品です。
ビタミンB1は、糖質をエネルギーに変える働きがあります。
ビタミンB2は脂質の代謝に大きく関わり、脂肪の燃焼を促進します。
ほかにも肌や髪の毛、粘膜を健康に保つ役割を果たしています。
特にダイエット中の人や脂っこい食事をよく食べる人は、積極的に摂取したいビタミンです。
ビタミンB6はたんぱく質の分解を助け、アミノ酸の代謝を促す働きをします。
代謝がうまく行われないと血糖値が上がる原因となるため、ビタミンB群は糖尿病患者にとって重要な役割を果たします。
水溶性ビタミンは、数時間で使い切れなかった分が汗や尿と一緒に排出されます。
体内に蓄積されないため、継続的な摂取が必要です。
カリウムは体内の余分なナトリウムを排出して血圧を下げる
さつまいもに含まれているカリウムには体内の余分なナトリウムを排出し、血圧を下げる働きがあります。
筋肉の収縮や神経の情報伝達にも関わり、体液のphバランスを保つ役割も果たします。
phとは水素イオン濃度指数のことで、体液はすべて弱アルカリ性に保たれています。
参照元:e-ヘルスネット – 厚生労働省
さつまいもには、100gあたり480mgのカリウムが含まれています。
参照元:日本食品標準成分表
ナトリウムは主に食塩として摂取され、摂り過ぎると高血圧やがんになるリスクが高まります。
平均的な1日あたりのナトリウム摂取量は男性が11g程度、女性が9g程度であり、摂取量を減らす必要があります。
参照元:e-ヘルスネット – 厚生労働省
糖尿病と高血圧が合併すると動脈硬化が進行し、糖尿病性腎症の悪化につながります。
糖尿病性腎症は、糖尿病の三大合併症の1つです。
発症すると腎臓の機能が低下し、進行すると透析が必要となります。
カリウムの働きにより尿から余分な塩分が排出され、高血圧や糖尿病の合併症を予防する効果があります。
さつまいもには糖尿病に良い影響を与える成分が含まれていますが、血糖値を上げないためには食べ方の工夫が必要です。
血糖値の急上昇を防いでさつまいもを食べるには4つのポイントがある

血糖値の急上昇を防いでさつまいもを食べるポイントは、以下の4つです。
- 皮をむかずに食べる
- 冷やして食べる
- 蒸すまたは茹でて調理する
- 食べる量を調節する
糖質は血糖値を上げる原因となり、さつまいもに含まれる糖質量は品種によって異なります。
数多い品種の中でも糖質が比較的少ないのは、鳴門金時です。
鳴門金時は栗のようなホクホクした食感と上品な甘さが特徴で、主に徳島県で栽培されています。
最近は品種改良が進み、糖度が高い新しい品種も増えています。
血糖値の上昇を抑えるには、さつまいもの品種にも気を配りましょう。
さつまいもの糖質量は食べ方や調理方法に大きく影響を受けるため、ここからは食べる時のポイントを解説します。
皮をむかずに食べた方が食物繊維を多く摂取できる
さつまいもの食物繊維は皮に多く含まれており、皮をむかずに食べた方がより多く摂取できます。
生のさつまいもに含まれる食物繊維の量を皮付きと皮なしで比較すると、以下のとおりです。
| さつまいもの状態 | 100gあたりの食物繊維の量 |
|---|---|
| 皮付き | 2.8g |
| 皮なし | 2.2g |
上記のとおり食物繊維は血糖値の上昇を抑え、腸内環境を整えます。
さらにさつまいもの皮には、クロロゲン酸やアントシアニンなどの成分が含まれています。
さつまいものアクにあたる成分であり、以下のような効能があります。
- 抗酸化作用がある
- 糖質の吸収を遅らせる
- 脂肪の蓄積を予防する
- メラニンの生成を防ぐ
抗酸化作用により体内の活性酸素を除去し、生活習慣病を予防できます。
糖質の吸収や脂肪の蓄積にも働きかけるため、糖尿病や肥満に良い影響を与えます。
植物に含まれる天然色素であり、さつまいもの皮はアントシアニンによって赤紫色をしています。
アントシアニンの効能は、以下のとおりです。
- 視覚機能の改善や眼精疲労の軽減
- 抗酸化作用がある
- 内臓脂肪の蓄積を抑える
- 花粉症を予防する
アントシアニンはロドプシンの再合成を促し、目の機能を改善させる働きがあります。
ロドプシンの再合成が遅れると、疲れ目や視界がぼやける原因となります。
抗酸化作用や内臓脂肪の蓄積を抑える作用は、糖尿病の合併症予防に効果的です。
他にも花粉症の原因となるヒスタミンを減少させ、発症を予防する効能もあります。
さつまいもに含まれるポリフェノールは約8割が皮の近くに集中しているため、皮をむかずに食べると無駄なく摂取できます。
冷やして食べるとでんぷんの質が変化して血糖値の上昇を抑えられる

さつまいもを冷やすとでんぷんがレジスタントスターチという成分に変化し、血糖値の上昇を抑えられます。
難消化性でんぷんとも呼ばれ、食物繊維と似た働きをします。
消化吸収に時間がかかるため、インスリンが過剰に分泌されるのを防ぎます。
さらにレジスタントスターチは、食物繊維の中でも善玉菌のえさとなる発酵性食物繊維です。
発酵性食物繊維の摂取により短鎖脂肪酸が生成され、以下の効果が期待できます。
- 腸内環境の改善
- 悪玉菌の増殖を抑える
- 腸管の免疫機能を高める
- 腸のぜん動運動を促す
短鎖脂肪酸は腸の免疫機能を活性化させて炎症を抑え、腸内環境を改善します。
悪玉菌はアルカリ性を好み、酸性の環境では増殖できないという特徴があります。
短鎖脂肪酸により腸内が酸性に傾いて弱酸性に保たれ、悪玉菌の増殖を抑えるのに有効です。
腸のぜん動運動が活発化すると、便秘の解消に効果があります。
蒸すまたは茹でる調理方法は糖質が増えるのを抑えられる
さつまいもは調理方法によって糖度が異なり、蒸すまたは茹でる調理方法は糖質が増えるのを抑えられます。
蒸し芋やふかし芋は、さつまいもの水分量があまり減少しないためです。
焼いたり揚げたりすると水分が蒸発して成分が凝縮され、糖質の量が多くなります。
時間をかけてさつまいもを加熱すると、糖化という現象が起こります。
糖化により糖質の量が増えるため、血糖値の急激な上昇を招く恐れがあります。
さらに甘い味付けや天ぷらの衣は、糖質やカロリーが増える原因の1つです。
大学芋やスイートポテト、さつまいもの天ぷらなどの献立には糖質や脂質が多く含まれています。
さつまいもを食べる時は調理方法に気を配り、味付けは糖質が多くならないようにしましょう。
量を調節して炭水化物が多い食品を重ねて食べるのは避ける

糖尿病患者がさつまいもを食べる際は量を調節し、炭水化物が多い食品を重ねて食べるのは避けるべきです。
さつまいもと炭水化物が多い食品を重ねて食べると、糖質が多くなってしまう恐れがあります。
糖尿病患者の献立を考える際は、食品交換表が役に立ちます。
80kcalを1単位とし、1日に食べる量の目安がわかります。
食品交換表における6つのグループは、以下のとおりです。
| 分類 | 食品の具体例 |
|---|---|
| 表1 | ごはん、うどん、さつまいも、じゃがいもなど |
| 表2 | みかんやりんご、バナナなどの果物 |
| 表3 | 卵、豆腐、魚介、肉類など |
| 表4 | 牛乳やヨーグルトなど、チーズを除く乳製品 |
| 表5 | マヨネーズ、バター、植物油、ピーナッツなど |
| 表6 | 野菜やきのこ、海藻類など |
表1は穀物やいも類、炭水化物が多い野菜が分類され、さつまいもも含まれます。
さつまいもとごはんなどの主食は同じ表1に分類されるため、食べる時は主食を少し減らすように心がけるのが大切です。
栄養素が豊富なさつまいもは糖尿病患者にも適した食品である
準完全食のさつまいもは体に良い栄養素が豊富に含まれており、糖尿病患者にも適した食品です。
水溶性食物繊維により、血糖値の急上昇を抑えられます。
さつまいも特有の成分であるヤラピンや不溶性食物繊維には、整腸作用が期待できます。
代謝を助けるビタミンB群やナトリウムを排出するカリウムも含まれており、糖尿病の合併症予防に効果的です。
ただし、さつまいもには糖質が多く含まれているため、食べ方にはいくつかポイントがあります。
食物繊維を多く摂取するには、皮をむかずに食べるのが最適です。
料理する際は蒸すまたは茹でる方法で調理し、加熱した後に冷やすと糖質の量を減らせます。
糖質が多くなりすぎないように量を調節し、炭水化物が多い食品と重ねて食べないのも大切です。
今回の記事を参考に、栄養素が豊富なさつまいもを食事に取り入れましょう。