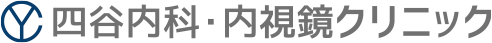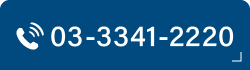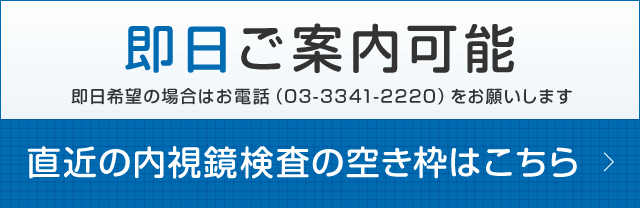脂質異常症について
血液中の脂質が一定基準値よりも多い状態を、脂質異常症と言います。コレステロールや中性脂肪など余分な脂質が多くなると、動脈硬化を引き起こしやすくなります。このため、脂質異常症のある方は、脳卒中や心筋梗塞の発症リスクが高いとされています。脂質異常症は、生活習慣の乱れが原因となることが多いために、生活習慣病と言われています。特に、現代社会では脂質異常症が増加傾向にあり、心血管疾患の主要な原因となっています。脂質異常症は、糖尿病や高血圧とともに心血管疾患の発症リスクを大きく引き上げるため、早期の発見と適切な管理が必要です。
また、脂質異常症は、自覚症状がほとんどないため、なかなか気付くことができず、ある日突然心筋梗塞などの発作を起こすことがあります。このような事態を防ぐためにも、健康診断で脂質異常症の疑いを指摘されたら、早めに当院までご相談ください。
脂質異常症の原因
肥満や運動不足、喫煙が、脂質異常症の発症原因とされています。また、高脂肪や高カロリーの食事、ビタミン・ミネラル・食物繊維の不足、過度の飲酒なども原因となります。特に、動物性脂肪の過剰摂取は発症リスクを高めます。さらに、アルコールや油分・糖分の摂りすぎも大きな原因となります。
脂質異常症を放置する危険性
脂質異常症は、血液中の脂質が異常な状態となります。通常はコレステロールや中性脂肪(トリグリセリド)の量が異常に増加または減少していることによって引き起こされます。コレステロールや中性脂肪の異常により、動脈硬化が進行し、最終的には心血管疾患(心筋梗塞や脳卒中など)のリスクが高まります。脂質異常症は、通常、自覚症状がほとんどないため、定期的な健康診断で血液検査を行い、血中脂質のバランスをチェックすることが重要となります。
脂質異常症がもたらす動脈硬化のメカニズム
脂質異常症が発症し、血液中の脂質バランスが崩れると、血管にダメージを与え、動脈硬化を進行させる要因となります。動脈硬化が進むと、血管が硬くなり、血流が悪化し、最終的には血栓が形成されやすくなり、心筋梗塞や脳卒中などの重篤な病気を引き起こす危険性が高まります。そのため、脂質異常症は単なる「血液の問題」ではなく、命に関わる病気となります。
脂質異常症の診断基準(空腹時採血による数値)
2006年までの診断基準値「総コレステロール値(220mg/dl以上)」に加えて、「悪玉コレステロール(LDL)が多い場合」「善玉コレステロール(HDL)が少ない場合」「中性脂肪が多い場合」の3種類を明確な診断基準として、いずれも脂質異常症とされます。
※この表は横にスクロールできます。
| 管理区分 | LDL-C | TG | HDL-C |
|---|---|---|---|
| 低リスク | <160 mg/dl |
<150 mg/dl(空腹時) <175 mg/dl(随時) |
≦40 |
| 中リスク | <140 mg/dl | ||
| 高リスク | <120 mg/dl <100 mg/dl* |
||
| 冠動脈疾患または アテローム 血栓性脳梗塞の既往 |
<100 mg/dl <70 mg/dl** |
*糖尿病におけるPAD・細小血管症合併時、または喫煙ありの場合
**急性冠症候群・家族性高コレステロール血症・糖尿病・冠動脈疾患またはアテローム血栓性脳梗塞のいずれかを合併する場合
脂質異常症の診断基準値
総コレステロール(TC)220 mg/dL 以上で脂質異常症の疑い、
基準値を超えた場合は、動脈硬化や心血管疾患のリスクが高まります。
悪玉コレステロール(LDL)
低リスク(160mg/dLより大きい)・中リスク(140mg/dLより大きい)・高リスク(120mg/dLより大きい)の場合には、脂質異常症の疑いがあります。LDLコレステロールは、動脈硬化を進行させる原因となるため、基準値を超えた場合は心筋梗塞や脳卒中などのリスクも高まります。
善玉コレステロール(HDL)
40 mg/dL 以下で脂質異常症の疑いがあるといわれています。善玉コレステロールが少ないと、心血管疾患のリスクが増加します。善玉コレステロール(HDL)は、血管内で余分なコレステロールを回収する役割があるために、善玉コレステロールが低いと動脈硬化のリスクが高まります。
中性脂肪(TG, トリグリセリド)
150 mg/dLより大きい(空腹時採血)、175 mg/dLより大きい(随時採血)場合には、脂質異常症の疑いがあると言われています。中性脂肪が高いと、動脈硬化や心疾患、糖尿病などのリスクが増加します。
脂質異常症の種類に基づく分類
①高LDLコレステロール血症(高LDL型)
高LDLコレステロール血症は、血中の悪玉コレステロール(LDL)の値が基準値を超えて高くなる状態を指します。LDLは、細胞に必要なコレステロールを運ぶ役割を担っていますが、過剰に増加すると血管壁に沈着し、動脈硬化を引き起こします。これにより、心筋梗塞や脳卒中などの心血管疾患のリスクが高まります。高LDLコレステロール血症の主な原因としては、遺伝的な要因(家族性高コレステロール血症)や不適切な食生活(高脂肪、高コレステロール食品の過剰摂取)、運動不足、肥満、高血圧、糖尿病などが挙げられます。特に高脂肪食や飽和脂肪酸の摂取がLDLコレステロール値を上昇させます。
基準値
低リスク(160mg/dLより大きい)・中リスク(140mg/dLより大きい)・高リスク(120mg/dLより大きい)場合には、脂質異常症と診断されます。理想的なLDL値は100 mg/dL未満とされていますが、心血管疾患のリスクが高い患者には、さらに厳しい目標(70 mg/dL未満)が推奨されることもあります。高LDLコレステロールは動脈硬化を進行させ、冠動脈疾患(心筋梗塞)や脳血管疾患(脳卒中)などのリスク因子となります。特に、家族性高コレステロール血症のように遺伝的にLDLが高い人では、リスクが著しく高くなります。
②低HDLコレステロール血症(低HDL型)
低HDLコレステロール血症は、血中の善玉コレステロール(HDL)の値が低い状態です。HDLコレステロールは、血管内に蓄積された余分なコレステロールを肝臓に運び、体外へ排出する役割があります。HDLが不足すると、余分なコレステロールが血管に蓄積され、動脈硬化を引き起こし、心血管疾患のリスクが高まります。低HDLコレステロール血症の主な原因は、遺伝的要因、肥満(特に内臓脂肪型)、運動不足、喫煙、アルコール過剰摂取などと言われています。また、糖尿病や高血圧もHDLを低下させる要因となります。
基準値
HDLコレステロールが40 mg/dL以下で脂質異常症と診断されます。HDLは「コレステロールの掃除屋」として血管内でコレステロールを回収して肝臓に運ぶため、HDLが低いと動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳卒中などのリスクが高まります。
③高トリグリセリド血症(高TG型)
高トリグリセリド血症は、血中の中性脂肪(トリグリセリド)の値が高い状態です。トリグリセリドは、食物から摂取した脂肪が体内で運ばれる形態で、過剰に蓄積されると、動脈硬化や膵炎のリスクが増加します。また、高トリグリセリドはインスリン抵抗性を引き起こし、糖尿病や脂肪肝の原因にもなります。食事(高カロリー、過剰な糖質、アルコール)、肥満、糖尿病、代謝症候群が高トリグリセリド血症の主要な原因となります。特に、過剰な糖質(精製糖や高GI食品)の摂取はトリグリセリド値を上昇させます。
基準値
トリグリセリド(中性脂肪)の値が150 mg/dL(空腹時)、175 mg/dL(随時)より大きいと脂質異常症であると診断されます。高トリグリセリドは、動脈硬化を進行させるだけでなく、急性膵炎を引き起こすことがあり、糖尿病や脂肪肝のリスクも高まります。また、高トリグリセリドは低HDLの状態を伴うことが多く、心血管疾患のリスクをさらに増加させます。
④混合型高脂血症
混合型高脂血症は、LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪(トリグリセリド)のすべてに異常が見られる状態を指します。混合型高脂血症は、異常な脂質が複数重なっているため、心血管疾患のリスクが非常に高くなります。混合型高脂血症は、遺伝的要因(遺伝性脂質異常)、不適切な食生活(高脂肪・高糖質食)、肥満、糖尿病、高血圧、運動不足などが複合的に影響することで発症すると言われています。
基準値
低リスク(160mg/dLより大きい)・中リスク(140mg/dLより大きい)・高リスク(120mg/dLより大きい)、HDLが40 mg/dL以下、150 mg/dL(空腹時)、175 mg/dL(随時)より大きい場合に混合型高脂血症と診断されます。混合型高脂血症では、LDLとトリグリセリドの両方が高く、HDLが低いため、動脈硬化が進行しやすく、心筋梗塞や脳卒中、糖尿病、脂肪肝などのリスクが高まります。
脂質異常症は、コレステロールや中性脂肪が異常なレベルで血液中に存在することから、動脈硬化を引き起こし、心血管疾患や糖尿病、脂肪肝など多くの合併症を引き起こします。そのため、早期診断と適切な治療、生活習慣の改善が重要となります。
脂質異常症の種類
高LDLコレステロール血症
血液中の悪玉コレステロール(LDL)が多すぎる状態を、高LDLコレステロール血症と言います。最も多く見られるタイプで、脂質異常症の有無を判断する重要な指標となるのがLDLコレステロールです。
低HDLコレステロール血症
血液中の善玉コレステロール(HDL)が低すぎる状態を、低HDLコレステロール血症と言います。HDLコレステロールが少ないと、血中のコレステロールが吸収できずに溜まってしまい、動脈硬化を進めてしまいます。
高トリグリセライド(中性脂肪)血症
血液中の中性脂肪が多すぎる状態を、高トリグリセライド(中性脂肪)血症と言います。脂質異常症では、中性脂肪とLDLコレステロールいずれも多い混合型も多く、中性脂肪が多いとLDLコレステロールも多くなりやすいことが分かっています。
脂質異常症のリスク要因
脂質異常症の原因は、遺伝的要因と環境的要因が複雑に絡み合っており、個人の生活習慣や食習慣が大きく影響します。生活習慣病の一部として、脂質異常症は予防することが可能であり、早期発見と適切な治療が求められている病気です。
リスク要因
1. 遺伝的要因
遺伝的な要因が脂質異常症に与える影響は大きく、特に家族に高コレステロール血症や動脈硬化、心血管疾患を患っている人が多い場合、脂質異常症を発症するリスクが高くなります。例えば、家族性高コレステロール血症などの遺伝性疾患は、遺伝子の変異により、LDLコレステロールの取り込みが正常に行われず、血中のコレステロールが高くなります。このような場合、食事療法や運動療法だけでは十分に対処できないことも多く、医師による早期の診断と専門的な治療が必要です。
2. 食事と生活習慣
脂質異常症は、食生活や生活習慣によって悪化することが多いです。特に、過剰なカロリー摂取や不適切な食事は、血中脂質の異常を引き起こす主な原因となります。特に、高カロリー・高脂肪・高糖質の食事は、LDLコレステロールの増加を促し、中性脂肪を増加させる要因となります。また、食物繊維が不足している食事は、血中脂質のバランスを崩しやすく、動脈硬化を進行させます。また運動不足やストレス、喫煙、過度の飲酒も、脂質異常症の進行を早める要因と考えられています。
3. 肥満と体重管理
肥満は脂質異常症の大きなリスク因子であり、特に内臓脂肪型肥満がある人は、血中の中性脂肪やLDLコレステロールが高くなる傾向にあります。肥満が進行すると、インスリン抵抗性が高まり、糖尿病や脂質異常症を引き起こす可能性が高まります。適正な体重を維持することが、脂質異常症の予防や改善には不可欠です。定期的な運動とバランスの取れた食事を行うことが体重管理の基本となります。
脂質異常症の診断方法
脂質異常症は、血液検査を通じて診断されます。診断に使用される主要な検査項目は以下となります。
総コレステロール
血液中のコレステロール全体の量を測定します。総コレステロールが高いと、LDLコレステロールや中性脂肪が高い可能性があり、心血管疾患のリスクが増加してしまいます。
LDLコレステロール(悪玉コレステロール)
LDLコレステロールの値が高いと、動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高くなります。LDLコレステロールの目標値は100mg/dL未満となります。
HDLコレステロール(善玉コレステロール)
HDLコレステロールが低いと、血管にコレステロールが蓄積されやすくなり、動脈硬化が進みます。HDLコレステロールの目標値は40mg/dL以上となります。
トリグリセリド(中性脂肪)
高いトリグリセリドの値は、心血管疾患のリスクを増加させます。トリグリセリド(中性脂肪)の理想的な値は150mg/dL未満と言われています。
これらの検査項目を基に、脂質異常症の診断が行われ、必要に応じて治療が進められます。
脂質異常症の治療・予防
食事療法

暴飲暴食を控えてください。また、脂肪分や糖分の多い食事を控えて、栄養バランスに気を付けて適量を召し上がってください。肉類などの動物性脂肪を控えて、タンパク質は魚介類や豆類などで摂ってください。また、ゆっくりと食べることで満腹感を得られ、腹八分で済ませることができます。特に、飽和脂肪酸やトランス脂肪酸を減らし、野菜や果物を豊富に摂取することが重要です。オメガ-3脂肪酸を含む魚(サバ、サーモンなど)やナッツ類を積極的に食べることで、LDLコレステロールの低下が期待できます。また、食物繊維が豊富な食品(全粒穀物、豆類など)を摂ることも効果的となります。
運動療法
ウォーキングなど軽い有酸素運動を継続して行います。階段を使うなど日常での工夫も有効です。できれば、毎日適度に身体を動かすことをお勧めします。定期的な有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、サイクリングなど)は、血中脂質の改善に非常に効果的となります。運動をすることで、HDLコレステロールを増やし、LDLコレステロールとトリグリセリドを減少させることができます。ただし、心疾患や整形外科疾患などがある場合は、医師と相談しながら行ってください。
薬物療法
食事や運動などの生活習慣を改善しても効果が得られない場合は、薬物療法を行います。患者様の体質やライフスタイルなどに応じて処方しております。薬物療法で心配なことや不安なことがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。