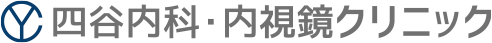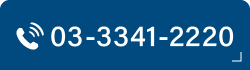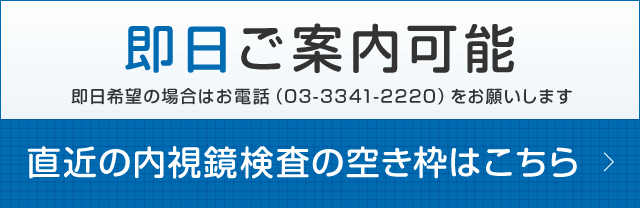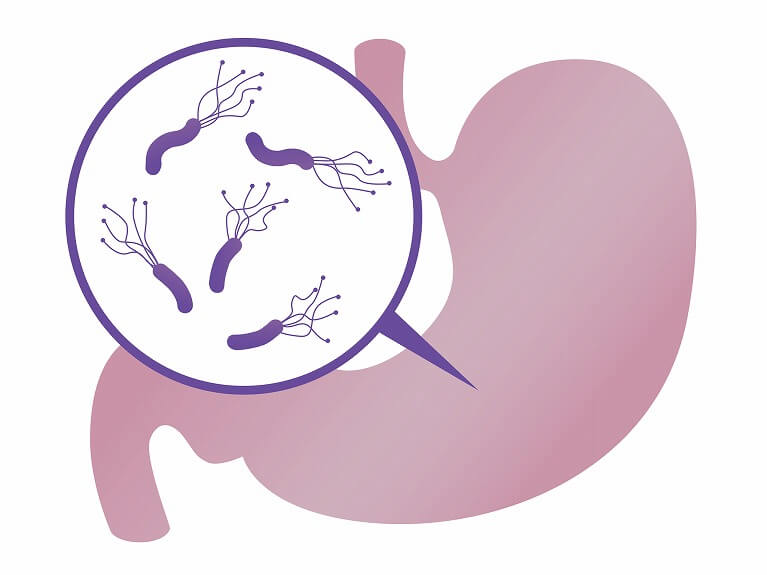 ピロリ菌(Helicobacter pylori)は、胃の粘膜に生息する細菌で、胃潰瘍や胃がんの原因となることが知られています。この菌の除菌は、健康リスクを大幅に減少させるだけでなく、胃腸の健康を維持するためにも非常に重要です。また命にかかわるような疾患を引き起こしてしまう可能性もありますので、おかしいなと思ったらすぐに当院へご相談ください。
ピロリ菌(Helicobacter pylori)は、胃の粘膜に生息する細菌で、胃潰瘍や胃がんの原因となることが知られています。この菌の除菌は、健康リスクを大幅に減少させるだけでなく、胃腸の健康を維持するためにも非常に重要です。また命にかかわるような疾患を引き起こしてしまう可能性もありますので、おかしいなと思ったらすぐに当院へご相談ください。
ピロリ菌の除菌とは
ピロリ菌がいると診断された場合、除菌治療を受ける必要があります。除菌を行うことで、胃や十二指腸潰瘍の再発リスクを70〜90%低減し、胃がんの発症率を約3分の1に抑えることができます。特に若い年齢で治療を開始すると、効果が高まることが分かっています。ただし、リスクが完全にゼロになるわけではありません。一度除菌が成功すれば、大人になってから再感染する可能性はほとんどありません。医師と相談しながら適切に進めることが大切です。
こんな症状は
ピロリ菌に感染しているかも
ピロリ菌に感染すると、胃炎をはじめとしたさまざまな疾患を引き起こし、以下のような症状が現れることがあります。自分の症状を確認し、早めの対応を検討しましょう。
①みぞおち付近の痛み
 空腹時にみぞおちのあたりが強く痛むことがあります。
空腹時にみぞおちのあたりが強く痛むことがあります。
②胃がんに関連する症状
胃がんが進行すると、次のような症状が現れる可能性があります。
- お腹の痛み
- すぐに満腹になる
- 原因不明の嘔吐
- 体重減少
- 貧血
③胸やけや胃の不快感
 胸やけが続く、胃の痛みが慢性的に続く場合は要注意です。
胸やけが続く、胃の痛みが慢性的に続く場合は要注意です。
④食欲不振
食欲が低下し、食べ物を受け付けなくなることがあります。
ピロリ菌が引き起こす可能性
がある疾患
ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)は、胃や十二指腸に感染し、さまざまな疾患を引き起こす可能性があります。非常に危険な疾患もありますので、ピロリ菌を放置することは非常に危険です。
萎縮性胃炎
ピロリ菌感染による慢性的な炎症が原因で、胃粘膜が萎縮し、胃酸分泌が低下する状態。
- 症状:胃もたれ、胃の不快感、食欲低下など。
- リスク: 胃がんの発生リスクが高まる。
胃、十二指腸潰瘍
胃粘膜がピロリ菌の影響で損傷を受け、胃酸によって粘膜がさらに侵食されている状態。
- 症状: 空腹時の胃痛、吐き気、胸焼け、吐血、黒色便など。
- 特徴: ピロリ菌除菌後、再発リスクが大幅に低減する。
胃がん
ピロリ菌感染が長期間続くことで、胃粘膜の炎症や萎縮が進み、がん細胞が発生する可能性が高まる。
- 予防:除菌治療によって胃がん発症リスクを約3分の1に低下させることが可能。
胃MALTリンパ腫
胃粘膜に存在するリンパ組織がピロリ菌感染によって炎症を起こし、がん化することがある。
- 治療:初期段階でピロリ菌を除菌することで改善が期待できる。
特発性血小板減少性紫斑病(ITP)
ピロリ菌感染が免疫系に影響を与え、血小板が減少する疾患。
- 症状:紫斑(皮下出血)、鼻血、歯茎からの出血など。
- 治療:ピロリ菌除菌により血小板数が改善するケースがある。
機能性ディスペプシア(FD)
胃や十二指腸に目立った病変がないにもかかわらず、慢性的な胃の不快感や消化不良が続く状態。
- 症状:胃の痛み、胃もたれ、早期満腹感など。
- 治療:ピロリ菌除菌により症状が改善する場合がある。
十二指腸炎
ピロリ菌感染が原因で、十二指腸の粘膜に炎症が起こる。
- 症状:空腹時の腹痛や吐き気。
- リスク:放置すると潰瘍へ進行する可能性がある。
除菌治療の流れ
 ピロリ菌の除菌には、抗生物質2種類と胃酸抑制薬を1週間服用します。その後、2ヶ月後に除菌が成功したかどうか尿素呼気検査にて判定を行います。除菌が不成功の場合、別の抗生物質を用いて再治療を行います。一度除菌が成功すれば再感染の可能性は低くなり、繰り返し検査を行う必要は一般的にありません。ただし、胃がんの原因の多くがピロリ菌感染による胃炎や萎縮性胃炎であるため、除菌後も定期的な内視鏡検査が推奨されます。
ピロリ菌の除菌には、抗生物質2種類と胃酸抑制薬を1週間服用します。その後、2ヶ月後に除菌が成功したかどうか尿素呼気検査にて判定を行います。除菌が不成功の場合、別の抗生物質を用いて再治療を行います。一度除菌が成功すれば再感染の可能性は低くなり、繰り返し検査を行う必要は一般的にありません。ただし、胃がんの原因の多くがピロリ菌感染による胃炎や萎縮性胃炎であるため、除菌後も定期的な内視鏡検査が推奨されます。
ピロリ菌の感染経路
ピロリ菌は、主に以下のルートで感染します。
食物や水
汚染された飲食物を摂取することで感染します。
人から人への感染
特に家族内感染が多いです。
感染の広がりやすい環境要因
衛生状態の悪い地域や、共有食器の使用が一般的な家庭では感染リスクが高まります。
ピロリ菌の検査方法
ピロリ菌を検出するための検査は、大きく分けて以下の2種類に分類されます。
【内視鏡を用いた方法】
【内視鏡を用いない方法】
それぞれの特徴を考慮し、適切な検査方法を選択します。
内視鏡を用いた検査方法
内視鏡を使用する検査では、胃粘膜や組織を採取し診断を行います。この方法は「点診断」と呼ばれ、特定の部位を詳細に調べることが可能です。ただし、稀に偽陰性となる場合もあります。
培養法
胃粘膜を採取し、ピロリ菌が成長できる環境下で約5~7日間培養します。培養後にピロリ菌の有無を判定します。
迅速ウレアーゼ試験
ピロリ菌が持つウレアーゼ酵素の活動を利用して診断します。採取した粘膜を反応液に入れ、液の色の変化で菌の存在を判定します。
組織鏡検法
胃粘膜の組織を特殊な染色で処理し、顕微鏡を用いてピロリ菌を確認する診断方法です。
内視鏡を用いない検査方法
内視鏡を使用しない検査は、身体への負担が少ないのが大きなメリットです。また、胃全体を対象に診断することから「面診断」として分類されます。
尿素呼気試験
ピロリ菌が持つウレアーゼ酵素の活動を利用し、呼気中の二酸化炭素濃度を測定する検査です。
手順:検査薬(13C-尿素)を服用し、服用前後の呼気を採取します。ピロリ菌が存在すると尿素が分解され、呼気中に多量の13CO2が検出されます。感染がない場合、13CO2はほとんど検出されません。
特徴:高精度で簡単に実施可能なため、主流の検査方法とされています。
便中抗原検査
ピロリ菌が胃内に存在する場合、便に菌抗原が排出される特性を利用した検査です。
特徴:偽陽性や偽陰性の可能性が低く、菌の存在を直接確認できます。菌が排出されるタイミングを検出するため、タイムラグが少ないのも特徴です。
ピロリ菌の検査方法は、症状や患者様の負担を考慮し、内視鏡を用いる「点診断」または内視鏡を使用しない「面診断」のいずれかを選択します。非侵襲的な検査は身体的な負担が少なく、初期診断や除菌効果の確認に向いています。一方、内視鏡を用いる検査は、胃粘膜の状態を直接確認するため、より詳細な診断が可能です。
一般的な除菌方法
一次除菌
- 使用薬剤: クラリスロマイシン、タケキャブ、アモキシシリン
- 期間: 7日間
二次除菌
- 使用薬剤: メトロニダゾール、タケキャブ、アモキシシリン
- 期間: 7日間
三次除菌
(自費診療となります)
- 使用薬剤: タケキャブ、アモキシシリン、ニューキノロン系抗菌薬など
- 備考: ペニシリンアレルギーをお持ちの方も自費での除菌となります。また、その場合タケキャブ、メトロニダゾール、ニューキノン系抗菌薬を用います。
- 費用の参考:診察、検査、薬剤代を合わせて3万円~4万円前後の費用がかかります。
よくある質問
一次除菌、二次除菌の成功率は?
目安としては、大体下記の程度となります。
一次除菌:約80〜90%
二次除菌:約90%
除菌薬の副作用は?
下痢、味覚異常、発疹、肝機能障害など。症状が強い場合は医師にご相談ください。
除菌後の再感染リスクは?
年間0.3%程度と非常に低いため、ほとんど心配ありません。
除菌後に逆流性食道炎になる可能性は?
胃酸分泌が改善するため、軽度の胸やけを感じる場合がありますが、多くは一時的なものです。
ご予約はこちらから
当院では、ピロリ菌でお困りの方にもしっかりと診察と検査を行います。場合によっては、内視鏡検査のご提案もいたします。まずは、外来のご予約のうえご来院ください。24時間web予約が可能です。