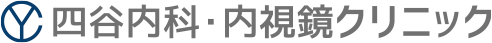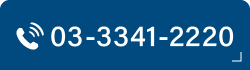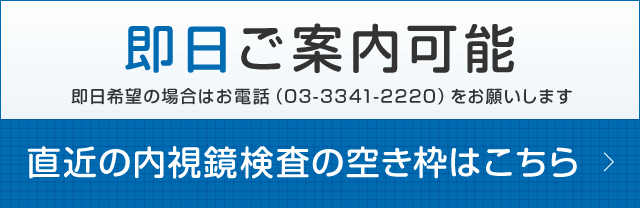甲状腺について
 ホルモンを生成する器官を内分泌と言いますが、甲状腺もそのひとつです。首の前方、喉仏すぐ下にあり、縦4cm、重さ15g程の大きさです。蝶が羽を広げたような形状で、後方の気管を抱き込むように存在します。通常、甲状腺は柔らかく、表面上に違和感を覚えることはありませんが、何らかの疾患により甲状腺に異常があると腫れを感じ、ゴツゴツと硬くなることもあります。なお、甲状腺ホルモンは、身体の発育促進や新陳代謝を活発にする機能があるほか、エネルギー産生や循環器調節などを行います。このため、ホルモン分泌が過剰に促進される、あるいは低下することにより身体の様々な個所に支障を及ぼします。
ホルモンを生成する器官を内分泌と言いますが、甲状腺もそのひとつです。首の前方、喉仏すぐ下にあり、縦4cm、重さ15g程の大きさです。蝶が羽を広げたような形状で、後方の気管を抱き込むように存在します。通常、甲状腺は柔らかく、表面上に違和感を覚えることはありませんが、何らかの疾患により甲状腺に異常があると腫れを感じ、ゴツゴツと硬くなることもあります。なお、甲状腺ホルモンは、身体の発育促進や新陳代謝を活発にする機能があるほか、エネルギー産生や循環器調節などを行います。このため、ホルモン分泌が過剰に促進される、あるいは低下することにより身体の様々な個所に支障を及ぼします。
甲状腺ホルモンとは
甲状腺ホルモンは2種類あります。ヨウ素の元素を4つ保持するT4(サイロキシン)と、ヨウ素の元素を3つ保持するT3(トリヨードサイロニン)があります。甲状腺では、主にT4を生成し、このT4が肝臓でT3になると、ホルモンとして働くようになります。甲状腺の状態を判断する検査においては、タンパク質と結合している状態であるT3やT4でなく、タンパク質と結合していない状態であるFT3やFT4を測定します。また、甲状腺の働きは、甲状腺刺激ホルモン(TSH)と呼ばれる、脳から甲状腺ホルモンの調整をするために送られるホルモンによって血液中で一定に保つようコントロールされています。
男性と女性における甲状腺の病気
甲状腺は、体内で重要なホルモンを分泌し、私たちの代謝、成長、発育、エネルギーバランスに深く関わる器官です。甲状腺ホルモン(T3、T4)は、体のほとんどの細胞に影響を与え、特に代謝の調整に重要な役割を果たします。そのため、甲状腺の機能に異常が生じると、体のさまざまなシステムに不調をもたらし、症状も多岐にわたります。甲状腺疾患は性別や年齢によって異なる傾向があり、男女で発症する病気の種類や症状に差が見られると言われています。
男性に多い甲状腺疾患
甲状腺疾患は、女性に多い病気と言われていますが、男性にも多くの患者が存在します。男性で最も多く見られる疾患は、甲状腺機能低下症、特に橋本病となります。橋本病は自己免疫疾患で、免疫系が甲状腺を攻撃し、甲状腺ホルモンの分泌が低下する病気です。橋本病は、女性に比べて男性には少ないですが、発症すると重症化することがあるため、男性にも注意が必要と言われています。
甲状腺機能低下症(橋本病)の症状
甲状腺機能低下症の症状は非常に多様ですが、主に体の代謝が低下することによって現れます。男性の場合、特に疲労感や無気力、体重の増加、乾燥肌、便秘、記憶力や集中力の低下などの症状が顕著に現れることがあります。橋本病が進行すると、高コレステロールや高血圧といった心血管系への影響も出る可能性があります。これらの症状は、他の疾患や加齢と間違えることも多いため、正確な診断を受けることが重要です。診断が遅れると、生活の質の低下や合併症を引き起こすことがあり、早期発見の治療が大切です。
男性においても、甲状腺機能低下症は年齢を問わず発症する可能性があり、特に40歳以上の男性の方は注意が必要です。橋本病は進行が緩やかであり、症状が軽微なうちに発見されることが難しいため、定期的な健康チェックを受けることが大切です。
女性に多い甲状腺疾患
甲状腺疾患は女性に多く見られ、特に甲状腺機能亢進症(バセドウ病)や甲状腺機能低下症(橋本病)が代表的となります。甲状腺機能亢進症(バセドウ病)は、特に20代から40代の女性に多く発症し、ホルモンの過剰分泌によって体の代謝が異常に亢進します。バセドウ病は、遺伝的要因や環境的要因が複雑に絡み合って発症するため、患者の症状や進行具合も様々と言われています。
甲状腺機能亢進症(バセドウ病)の症状
バセドウ病の主な症状には、急激な体重減少、過剰な発汗、動悸、食欲増進、手の震え、イライラ感などがあります。さらに、眼球突出(グレーブス眼症)と呼ばれる、目が飛び出すような症状も特徴的です。この眼球突出は、視力障害や目の乾燥感を引き起こすこともあります。特にこの眼球突出が身体的にも心理的にも強い影響を与えるため、早期の治療が重要です。また、バセドウ病の症状は、心血管系に大きな影響を及ぼすことがあり、動悸が続くと不整脈や心不全を引き起こす可能性もあります。これらの症状が進行すると、生命に危険が及ぶこともあるため、迅速に医療機関を受診することが必要となります。
甲状腺機能亢進症(バセドウ病)の治療法
バセドウ病の治療は、抗甲状腺薬によって甲状腺ホルモンの過剰分泌を抑制することが中心となります。メチマゾールやプロピルチオウラシルが代表的な薬剤であり、これらはホルモンの産生を抑える働きがあります。抗甲状腺薬による治療は数か月から数年続くことがあり、その効果を継続的にモニタリングすることが重要となります。
薬物治療が効果を示さない場合や重篤な症状が現れた場合、放射線治療(放射性ヨウ素療法)や手術によって甲状腺の一部を切除することもあります。放射線治療は、甲状腺組織を破壊してホルモンの過剰分泌を抑える方法となります。手術による治療は、甲状腺を一部または完全に切除することによって、症状を根本的に改善することができますが、術後のホルモンバランスの調整も必要となります。
女性の場合、特に妊娠を望む場合や妊娠中の治療においては、薬剤の選択や治療方法に慎重な治療が必要となります。妊娠中のバセドウ病は、胎児に影響を与える可能性があるため、早期に適切な治療を受けることが大切です。
妊娠中の甲状腺疾患
妊娠中の甲状腺疾患は、母体と胎児に大きな影響を与える可能性があります。妊娠性甲状腺機能亢進症や妊娠性甲状腺機能低下症は、妊婦と胎児の健康に深刻な影響を及ぼすため、妊娠中の甲状腺機能は特に注意深く監視する必要があります。
妊娠中に甲状腺機能亢進症が未治療のままであると、早産や流産、胎児の発育遅延などのリスクが増加します。逆に、甲状腺機能低下症では、胎児の脳発達に影響を及ぼし、知的障害や神経発達に問題を引き起こす可能性があるため、適切な治療が欠かせません。
甲状腺疾患の種類
甲状腺機能亢進症
甲状腺ホルモンが過剰に分泌されている状態を甲状腺機能亢進症と言います。女性に多く見られる疾患とされ、主に息切れや動悸、体重減少などの症状があらわれます。バセドウ病が代表的な疾患として挙げられます。治療方法は、内服、アイソトープ治療、手術が検討されます。甲状腺機能亢進症の主な症状は、以下の通りです。
よくある症状
- 甲状腺の腫れ(甲状腺腫)
- 動悸
- めまい
- 息切れ
- 頻脈
- 下痢
- 疲れやすい
- 多汗
- 暑がり
- 微熱
- イライラ(精神的な不安定)
- 食欲増加
- 体重減少
- 月経異常
- 睡眠障害(不眠)
- 手足の震え(振戦)
- 眼球の飛び出し(眼球突出)
など
甲状腺機能低下症
甲状腺ホルモンの分泌量が低下している状態を、甲状腺機能低下症と言います。代表的な疾患として、橋本病が挙げられますが、橋本病の患者様が全員甲状腺機能低下症というわけではありません。治療は、甲状腺ホルモンの内服を行います。甲状腺機能低下症の主な症状は、以下の通りです。
よくある症状
- 甲状腺の腫れ(甲状腺腫)
- 身体のむくみ
- 倦怠感
- 強い眠気
- 肌の乾燥・肌荒れ
- 便秘
- 徐脈(脈が遅い)
- 体重増加(食欲はない)
- 髪の毛や眉毛が薄くなる
- 無気力
- 肩こり
- 月経異常
など
甲状腺腫瘍
甲状腺に腫瘍(しこり)ができた状態です。ほとんどが良性で、機能異常などを伴わず、悪性であった場合でも進行が遅いものが多く、適切な治療をすることで寛解が期待できます。ただし、中には濾胞(ろほう)がんと言われる転移しやすいがんや未分化がんと言われる進行の早いものもあります。そのため、専門的な知識を有する医師による適切な診断・治療が重要になります。甲状腺腫瘍の主な症状は、以下の通りです。
よくある症状
- 甲状腺全体の腫れ又は部分的な腫れ
- 首前方の違和感
- 動悸
- 息切れ
- 多汗
- 体重減少
など
甲状腺疾患の原因
甲状腺は、体の代謝を調整するために重要なホルモン(甲状腺ホルモン)を分泌する器官であり、その機能不全は全身のさまざまな機能に影響を与えます。甲状腺疾患は多岐にわたりますが、いずれの疾患もその発症にはいくつかの要因が関与しています。
①自己免疫疾患
甲状腺疾患の中で最も多く見られる原因は、自己免疫疾患です。自己免疫疾患は、免疫系が正常な組織を誤って攻撃する疾患群で、甲状腺疾患にも多く関連しています。主に橋本病とバセドウ病が代表的となります。
(a) 橋本病(甲状腺機能低下症)
橋本病は、甲状腺に対する自己免疫反応によって引き起こされる疾患です。免疫系が甲状腺を攻撃し、甲状腺細胞が破壊されることで、甲状腺ホルモンの分泌が低下します。その結果、代謝が遅くなり、倦怠感、体重増加、便秘、寒がりなどの症状が現れます。橋本病は特に女性に多く、加齢とともに発症する傾向があります。
(b) バセドウ病(甲状腺機能亢進症)
バセドウ病は、免疫系が甲状腺を刺激し、過剰に甲状腺ホルモンを分泌させる疾患です。これにより代謝が異常に亢進し、動悸、体重減少、発汗、眼球突出(グレーブス眼症)などの症状が現れます。バセドウ病は女性に多く、特に30~40代の成人に発症しやすいです。遺伝的な素因や環境要因が発症に関与しており、ストレスや妊娠もリスクを高める要因とされています。
②遺伝的要因
甲状腺疾患の発症においては、遺伝的要因が大きな役割を果たしています。自己免疫疾患である橋本病やバセドウ病は、特に家族内に同様の疾患を持つ人が多いことが特徴と言われています。また、甲状腺癌についても遺伝的な素因が関与することが知られています。そのため家族に甲状腺疾患や癌の患者がいる場合、早期の診断と定期的なチェックが推奨されています。
③栄養不足
甲状腺ホルモンを正常に合成するためには、ヨウ素が不可欠です。ヨウ素が不足すると、甲状腺ホルモンの合成がうまくいかず、甲状腺腫や甲状腺機能低下症が発症します。特にヨウ素が不足している地域では、甲状腺疾患が多く見られることがあります。日本では、海藻や魚介類が豊富に含まれるため、通常はヨウ素の摂取不足は少ないですが、食生活の偏りや極端なダイエットを行っている場合には、注意が必要となります。
さらに、セレンや亜鉛など、甲状腺ホルモンの合成や活性化に関与する微量栄養素の不足も、甲状腺機能に影響を与えることがあります。これらの栄養素が欠乏することで、甲状腺の働きが低下することがあるため、バランスの取れた食事が非常に重要です。
④ストレス
ストレスも甲状腺疾患の発症に関わる因子として知られています。慢性的なストレスは、コルチゾールというホルモンの分泌を引き起こし、このホルモンが甲状腺機能に影響を与えることがあります。ストレスが長期間続くと、免疫系が過剰に反応し、自己免疫疾患が引き起こされることがあります。特に、ストレスが引き金となってバセドウ病や橋本病の発症リスクが高まることが示唆されています。また、ストレスは甲状腺ホルモンの分泌を乱し、代謝に異常をきたすことがあります。現代社会における高ストレス環境が、甲状腺疾患を増加させる要因の一つとも言われています。
勘違いされやすい甲状腺疾患
甲状腺疾患には、特有の症状が少なく、専門的な知識を持った医師でなければ、他の疾患やストレスなど心理的(精神的)なものと勘違いしてしまう疾患が数多くあります。そこで、下記に、他の疾患と勘違いされやすい症状と疾患を提示したいと思います。
身体に不調があるけれど改善しない、あるいはどの診療科(クリニック)に行けば良いか分からない、このようなお悩みがございましたら、当院までご相談ください。
日常生活が送れるだけでなく、より快適に過ごせるようにお手伝いできればと考えております。
甲状腺の検査
血液検査
甲状腺の検査では、血液検査で甲状腺ホルモン値を確認します。先ずは、下垂体から分泌される甲状腺刺激ホルモン(TSH)と甲状腺ホルモン(FT3・FT4)を測定し、甲状腺ホルモン値を調べます。異常が見られた場合は、その原因を探ります。また、バセドウ病が疑われる場合にTRAb(抗TSHレセプター抗体)やTSAb(甲状腺刺激抗体)、橋本病が疑われる場合にTgAb(抗サイログロブリン抗体)やTPOAb(抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体)を調べることもあります。なお、TgAbやTPOAbは橋本病などの診断指標としても用いられますが、バセドウ病でも陽性となることがあります。また、甲状腺ホルモンの生成や貯蔵の状況を確認でき、腫瘍マーカーとしても経過観察時に活用できるためHTg(サイログロブリン)を調べることもあります。
超音波検査
 甲状腺の大きさや、腫瘍の有無を確認します。甲状腺ホルモンの分泌異常が見られる場合は、甲状腺全体が大きくなったり、小さくなったりするほか、甲状腺自体が変化(橋本病などではデコボコ、がんではいびつな形)することがあります。また、腫瘍がある場合は、腫瘍の大きさや数、構造などを検査します。必要に応じて、甲状腺内部の細胞の一部を採取し、悪性かどうかを調べます。
甲状腺の大きさや、腫瘍の有無を確認します。甲状腺ホルモンの分泌異常が見られる場合は、甲状腺全体が大きくなったり、小さくなったりするほか、甲状腺自体が変化(橋本病などではデコボコ、がんではいびつな形)することがあります。また、腫瘍がある場合は、腫瘍の大きさや数、構造などを検査します。必要に応じて、甲状腺内部の細胞の一部を採取し、悪性かどうかを調べます。
甲状腺外来の受診をご検討中の方へ
当院では、内分泌を専門とする医師による甲状腺疾患の検査・診断・治療を行っております。甲状腺疾患の症状は、甲状腺の疾患と認識されず、疲れや怠けと誤解され、また患者様本人も疾患と気づきにくいものが多くなっています。特に甲状腺疾患は女性に多い傾向にありますが、妊娠や出産といった影響を受けやすい疾患でもあります。当院では、10代(思春期)から高齢者まで患者様の生涯に渡り甲状腺疾患と内科的・消化器的疾患、患者様の全身的なフォローをしていきたいと考えております。お気軽にご相談ください。